| |
|
| |
| ・「三科分類法」で読む |
『立正安国論』を様々な角度から読む。
・「三科分類法」で読む
・「四諦」で読む
・仏神・僧侶・人師の二択で読む
・「立正」と「安国」で読む
・「有事」と「平時」で読む
「三科分類法」とは、経典やその注釈書・先師の論述を理解するのに序分・正宗分・流通分と3つに分けることです。
また
『立正安国論』は客人と主人との十段の問答で構成されているとされています。
しかし実際は問答は八段までで九段目は天変地異、疫病等は法然聖人の選択集によるとやっと領解した客とその事を悦ぶ主人との対話であり、十段目は客のこれ までの懺悔とこれからの邪法対治の決意の表明で構成されています。
問答を取り交わす心理劇的要素も含み、時系列で序分・正宗分・流通分と振り分けられています。
先ず序分は
| 続いて本論に入ります。 |
| 続いて流通分です。
|
|
以上の三科の構成を見ると序分が第一問答から第八問答まで全体の殆どを占め、正宗分は第九段、流通分は第十の客の懺悔・決意だけとなり極めてバランスが悪いと思われます。
そこで序分は災難の由来と原因を糾明する「破邪」に大部分が費やされて「正法」の具体的内容や念仏以外の他宗の謗法たる由縁は安国論が幕府に用いられた時、公場対決の場で表明するということになっています。
確かに日蓮聖人はそのような御計画を胸中に秘めていたことでしょうが、安国論奏上の時点においては正嘉以来の大地震に始まって相次ぐ天変地妖飢饉疫病などで打ちひしがれた民衆の苦しみを共に嘆き、その災難対治の解決策を今日で言うところの国家緊急権の発動を最も影響力ある北条時宗に託し、万祈の諸対策より先ず一凶(法然念仏)を禁ずることが最優先課題であるという「有事」の書であるからです。
『毒矢のたとえ』でいう所の先ず毒矢(一凶)を抜くことであり、その緊急性と危機感を客と主人が共有し「先づ国家を祈って須らく仏法を立つべし。」となる訳です。
以上『立正安国論』を伝統的な区分法「三分」によって略述しましたが、次回は 『立正安国論』を「四諦」で読んでみたいと思います。 |
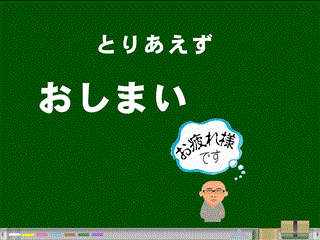
Copyright,Juhoukai matsudodoujou
u