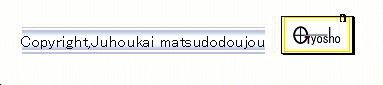原文
漢文
訓読(ルビ付き)
原文漢字対照
現代語対訳
原漢対照(返り点)
・「四諦」で読む
・「仏神、僧侶、人師」で読む
・「立正」と「安国」で読む
・「有事」と「平時」で読む
日蓮聖人がこの二つの難を『安国論』で預言されて、四年後の文永元年7月5日の大彗星出現により確信されます(安国論御勘由来)。更に四年後の文永5年1月18日蒙古が国交を要求し、その後の交渉の末、幕府の拒絶によって遂に「蒙古侵逼の難」が的中します。
日蓮聖人にとって『立正安国論』上奏以来、文永5年1月18日までの8年間はまさしく「蒙古侵逼前夜」であり、その間の「松葉谷」や「伊豆」の法難でした。
以後文永11年の「文永の役」と弘安4年の「弘安の役」の二度にわたる「蒙古侵逼」の国難中における佐渡流謫、帰還後は身延での御生涯でした。
九カ年間過ごされた身延を後にされたのも表向きはご両親の墓参りと常陸の湯での療養となっていますが、内心は蒙古襲来の未曾有の国難後の国状をご自分自身の目で確かめ、やがて政権は鎌倉から京都へ移行することを達見され、十三歳の経一麿に京都開教を付嘱されたのでした。詳しくは恩師著「日蓮大聖人の身延出山の真意」参照の事。
教学上、仏法軸において『本尊抄』『開目抄』著された佐渡を基点として「佐前」「佐後」として考察されますが、国家軸に当てはめると(「立正」と「安国」で読む)『立正安国論』上奏を基点として「安国論前」と「安国論後」に二分されます。当に日蓮聖人の御生涯は『立正安国論』で始まり、『立正安國論』で終わるのです。
改めて考えますと重畳する御法難の中で移り変わる四季や花鳥風月を愛で、ご供養のお酒で身を温められホッとされたことは当然あったでしょうが、まさに「有事」連続の御生涯でした。 参考資料「日蓮聖人と〈蒙古襲来〉関連年譜」PDF版
さて目を転じて現代を見れば、「有事」を想定するだけで「いつか来た道」と騒ぎ立て、憲法九条を振りかざし、「他国侵逼の難」前夜の兆候も見ようともせず、「戦争反対」「平和」を連呼すれば国家が安泰であると妄想する輩が跳梁跋扈しています。
『安国論』の文脈に沿って言えば、国家の安泰と永続を考える真のエリートと政治家という「正道の侶」が居なくなったのでしょうか。
「治(平時)に居て乱(有事)を忘れず」『易経・繁辞伝』。「国家の安危」は「安(平時)に居て危(有事)を思う」『春秋左氏伝』ことが国防政治外交上の鉄則。
北朝鮮の核や拉致問題も米国への一方的依存の口先外交であり、対中国も経済共存の習近平への忖度外交で、北方領土問題もプーチンの言いなり外交に成り果ててしまいました。
『安国論』中「有事」と「平時」で解釈の分かれるところは、次の一節ではないでしょうか。
「平和」とはただ戦争が無い状態をいうのではなく、自由と独立の「平和」でなければなりません。
現在のウクライナは自由と独立の「平和」のために侵略国ロシアと戦っているのです。「安國」抜きの「平和」は隷属国家に成り下がります。やはり「立正安国」でなければなりません。
日蓮門下は須く行学の二道に励むべし。 (*^_^*)
又は、「戈」は矛で武力、「一」は土地、「口」は領土を表した「或」が「くに」を意味し、後に、それが国構えをつけ「國」とした。
次に「平時」と「有事」に分けます。
「國家を祈る」ことと「仏法を立てること」はあくまでも有事での優先関係を表したもので「主従」「本末」「軽重」関係では無いのです。
国家の危機意識は客と主人は共鳴共感共有しているのです。
その解決法をめぐっての問答なのです。