
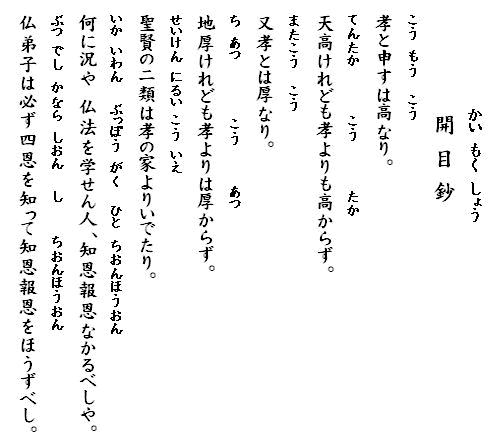
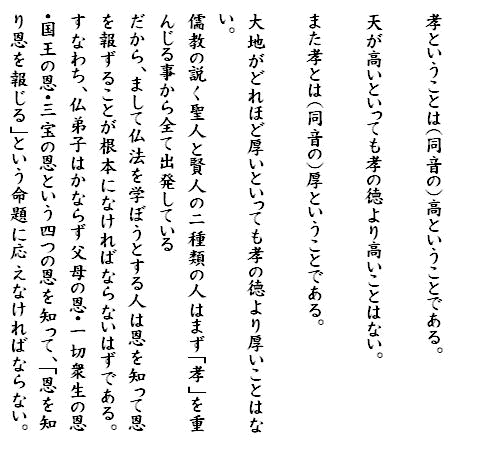
この間に日蓮聖人の許に集まった弟子・檀那は可成りの数に達したが、度々の追害に遭遇して中途で退転する者が続出し、ことに龍口法難から佐渡流罪にかけては
「かまくらにも御勘気の時、千が九百九十九人は堕ちて候」(『新尼御前御返事』)
とあるように、日蓮聖人教団は幕府の禁断の宗教となり、崩壊の危機に瀕した。
退転の理由が世間の恐ろしさにあるのはまだよいとして、
「日蓮聖人御房は師匠にておはせども余りにこは(剛)し。我等はやはらかに法華経を弘むべし」(『佐渡御書』)、
「我が師は法華経を弘通し給ふとてひろまらざる上、大難の来れるは、真言は国をほろぼす、念仏は無間地獄、禅は天魔の所為、律僧は国賊との給ふゆへなり」(『諌暁八幡抄』)
とて日蓮聖人の布教方法および迫害に疑問を懐いて退転したものもあるとすれば、弟子檀那のこれらの疑念を払拭しておかねばならなかった。
そこで過去19年間に日蓮聖人および弟子檀那が蒙った迫害の宗教的意味、およびそれを引き起こした折伏伝導の時代的正当性について説明せねばならなかった。
また配所における日蓮聖人の生命は、
「彼の国へ趣く者は死は多く、生は希なり」(『法蓮鈔』)、
「此国へ流されたる人の始終いけらるる事なし」(『種種御振舞御書』)
とあるように明日の命も知れぬ身であった。鎌倉からの下知でいつ頸切られるかも知れぬ。頸切られる前に是非「一期の大事」を記して「かたみ」(『開目抄』)としたい。
こうした動機で述作されたから、『開目抄』にも
「世間の疑といゐ、自心の疑と申し、いかでか天扶け給ざるらん。諸天等の守護神は仏前の御誓言あり。法華経の行者にはさるになりとも法華経の行者とがうして、早々に仏前の御誓言をとげんとこそをぼすべきに、其義なきは我身法華経の行者にあらざるか。此疑は此書の肝心、一期の大事なれば処々にこれをかく上、疑を強くして答をかまうべし」といわれている。
又やがて『観心本尊抄』を著述して自身が抱懐している法華本門の修行方法を開示するに先立ち、まず自身が末法の衆生にとっていかなる人物であるか法華経に照らし合わせて明示しておかなければならなかった。
つまり末法相応の大法を開顕する前に末法の導師が御自身であることを開顕するために述作されたのである。題意は、『報恩抄』に「日本国の一切衆生の盲目を開ける功徳あり」とあるのと同意である。
この様な日蓮聖人の折伏伝道もひとえに仏弟子としての報恩の為であった。
『日蓮宗事典』参照
その文字構造は老の省略体と子の組合せから成り、子が老人を助けささえることを表す会意文字。
つまり、子の父母に対する敬愛を基礎として成立する道徳であるが、それをやや拡大しては祖先崇拝、とくに祖先の祭祀をふくみ、さらにいっそう拡大しては老人尊重の思想にまで発展する。
中国社会のさまざまの局面に浸透した〈孝〉をとくに強調したのは儒家であって、《孝経》は五経につぐ重要な地位を与えられた。《孝経》においては、天子から庶人にいたるまでの各階層それぞれの〈孝〉のありかたが説かれるとともに、〈孝〉は天地人の三才をつらぬく宇宙的原理にまで高められている。
〈孝〉の徳が浸透する中国社会において、外来の文明、とりわけ宗教はさまざまの摩擦を引き起こした。沙門の剃髪は父母からうけた肉体の損傷であり、その出家主義は父母に対する孝養の放棄であり、その独身主義は祖先の祭祀の断絶であると仏教は攻撃された。
日本では、中国の影響のもとに国家がつくられ、制度が整えられたために、律令国家のもとで孝が道徳の基本とされたのは当然であった。律令制下の大学では《論語》とともに《孝経》が必修とされ、政府は事あるごとに孝子の表彰を行った。
管内の孝子を顕彰することは国司の任務の一つで、孝子は課役を免ぜられ、布帛(ふはく)などを下賜された。こうした中国の制度に倣う教化のほかに、日本人に孝を教えたのは仏教であった。
仏教は孝の教えを大幅にとり入れることを通じて、中国社会に受容されることを可能にしていたから、日本に伝えられた仏教も、因果の理と合わせて先祖や親の重んずべきことを説き、孝を強調した。
しかし、中国と日本とでは家族のあり方に大きな違いがあったので、日本では孝を親に対する子の義務としてよりも、親子のあいだの愛情のあらわれとして理解することが多かった。
中世に入って、父系を中心とする家の制度が明確な姿をあらわすようになると、孝が重視されはじめ、説話集や軍記物語には数々の孝行の話が収められた。しかし、そこでもなお孝行は恩愛と並べて愛情の発露とされることが多く、道徳的な色彩は薄かった。
近世に入って、家の制度が確立し、儒教が教学の中心に据えられると、孝は道徳の根本として取り上げられるようになった。幕府や諸藩は孝子の表彰を盛んに行い、教化に努めたが、他方で主君に対する忠が強調されるようになると、忠は孝に優先すると説かれることになった。
明治時代に国民道徳の根本を示すものとして発布された教育勅語は、忠を第一としながら、究極においては忠と孝が一致すると説いている。
第2次大戦後、家制度の解体の中で、孝を道徳の基本とする主張は大きく後退した。 日立デジタル平凡社《世界大百科事典 第2版》より抜粋
すなわち「もし説法を聞かんには、四種の恩ありて甚だ報じ難しとなす。何等をか四となすや。一には母、二には父、三には如来、四には説法の法師なり。もしこの四種の人を供養することあらば、無量の福を得て、現在には人の讃歎する所となり、未来世に於ては能く菩提を得ん」と説き、この四は供養する者に無量の福を与えてくれる四種の福田であるとされる。
なお同経の所説で注目されるのは、後の四恩説では重要な構成要素として必ず挙げられる国王の恩が説かれていず、むしろ「出家の人、王に近づくべからず」と国王への親近を厳しく誠めていることである。
②『大乗本生心地観経』第二には父母・衆生・国王・三宝の四をあげる。
すなわち同経第二報恩品には「世・出世の恩に其の四種あり。一に父母の恩、二に衆生の恩、三に国王の恩、四に三宝の恩なり。是の如きの四恩は一切衆生、平等に荷負す」と説いている。
そしてこの四恩を広説して、初めに父母の恩とは、父に慈恩あり、母に悲恩ありと説き、特に母に大地・能生・能正・養育・智者・荘厳・安穏・教授・教誠・与業の十徳をあげて、母の恩は須弥山よりも高く大地よりも重いと説き、父母に孝養すれば仏に供養するとその福異ることなしと説いている。
次に衆生の恩とは、一切の衆生は多生の間に互に父母となるから、一切の男子は慈父であり、一切の女人は悲母であるから、諸の衆生に対し一切の時において皆大恩を知るべしと説いている。
三に国王の恩とは、その国において山河大地より大海の際を尽すまで皆国王に属する。王がもし正治を失へば人に所依なく、もし正化を以てすれば八大恐怖はその国に入らないと説く。
四に三宝の恩とは、すなわち仏・法・僧の三宝である。
仏宝に六種の微妙の功徳を具足している。すなわち一には無上の大功徳田なり、二には無上にして大恩徳あり、三には無足二足及び多足の衆生中の尊なり、四には極めて値遇し難きこと優曇華の如し、五には三千大千世界に独一出現す、六には世出世間の功徳円満し一切義の依なりと説き、この六種の功徳を具えて常によく一切衆生を利楽するを、仏宝不思議の恩と名づけると説く。
法宝に教・理・行・果の四法があり、この四種の法宝は衆生を引導して生死の海を出でて彼岸に到らしめる。従って衆生は微妙の法宝を敬わなければならない。これを法宝不思議の恩と名づくと説く。
僧宝には三種がある。一に文殊・弥勒等の菩薩僧、二に舎利弗・目連等の声聞僧、三に別解脱戒を成就し、一切の正見を具足して能く広く他の為に衆の聖道の法を演説開示し、衆生を利楽する凡夫僧である。この三種を真福僧と名づける。
また福田僧と名づける一類の僧がある。すなわち仏の舎利および形像、諸の法僧聖所制の戒に於て深く敬信を生じ、能く正法を宣布し一乗を讃歎し、深く因果を信じて常に善願を発し、過犯する所に随って業障を悔除する人である。
これらの四種の聖凡僧宝は、恒に衆生を利楽して暫くも捨てることがない。これを僧宝不思議の恩と名づけると説く。
『心地観経』所説の四恩説が、中国や日本の仏教に与えた影響は多大なものがあり、日蓮聖人もまた『四恩抄』(二三七頁)に仏法修行者は必ず四恩を報ずべきであるとして、同経の四恩をあげている。
③『智覚禅師自行録』には師長・父母・国王・施主の四をあげる。すなわち「上報四恩とは、一に師長訓誘の恩に報じ、二に父母養育の恩に報じ、三に国王荷負の恩に報じ、四に施主供給の恩に報ず」と説いている。この四恩説は宋の延寿(1九七五)に由来するとされるが、これが『釈氏要覧』に継承され、次第に伝統的所説となったのである。
④日蓮聖人は『報恩抄』(一一九二頁B・C)において、父母の恩・師匠の恩・三宝の恩・国恩の四をあげ、特に師恩を重視しているが、これは同書が旧師道善房に対する報恩感謝追善回向のための撰述であることによると思われる。
『日蓮聖人遺文辞典』より抜粋
インドの仏教は縁起(相互依存)の思想によって人間の横の結びつきを重視したのにたいし、中国の儒教は忠孝を説く五倫五常(精神的秩序)の思想によって人間の縦の関係に注目したが、この考え方の違いが恩の観念にも反映した。仏教ではインド以来〈四恩〉が説かれたが、それは
《正法念処経》では母、父、如来、説法の師の恩とされ、《大乗本生心地観経》では父母、衆生、国王、三宝の恩とされている。このうち父母と国王の恩を強調する《心地観経》の思想は中国や日本で重視され、封建道徳と結びつけられた。
日本で恩の観念が鋭く意識されはじめたのは中世になってからであるが、そこには二つの考え方があった。
一つは親鸞や道元などの場合で、父母の恩や国王への礼拝を否定して、如来や衆生の恩を強調する宗教的な考えである。
もう一つは封建社会の主従関係にみられるもので、主君の恩と従者の奉仕(忠誠)が一種の契約関係にもとづくとされた場合である。
だが日本では前者の宗教的な恩の観念は発展せず、後者の上下の権力関係にもとづく恩がしだいに重視されるようになった。
もっとも日本の儒学は中国の場合と同様に恩をあまり問題にすることがなかったが、近世の中江藤樹や貝原益軒にいたって恩の考えが積極的にとりあげられ、忠孝があらゆる徳目の根源とされた。
近世末になって二宮尊徳が天地人の三才の徳に報ずることを説いたのも、そのような精神がうけつがれたためと考えられる。
こうして主君にたいする報恩(忠)と父母にたいする報恩(孝)の強調は、制度的には人倫の上下関係を秩序づけるとともに、家父長制と封建体制の安定化に貢献した。
そして心理的には上位のものが下位のものに恩恵をほどこす半強制的な温情主義(パターナリズム)を生みだした。
アメリカの文化人類学者 R. ベネディクトは《菊と刀》のなかで、近世以降に発達をみた恩のあり方に注目し、人が全力をあげて背負わなければならない負担、債務、重荷であると分析した。
上位のものが下位のものにほどこす恩も、下位のものがその恩に報ずる行為も、ともにけっして普遍的な道徳的義務であるのではなく、むしろ借金とその返済という関係に還元することができると考えた。
しかもそこにみられる恩返し(借金返し)の義務は無限の義務と感じられており、そこに日本人に固有の支配と服従の諸関係が胚胎するのだという。
これは要するに〈恩〉と〈恩返し〉の行為には、もともと経済関係的側面と心理関係的側面が重層していたということなのである。
経済関係的側面でいえば恩は返済可能の債務であるが、心理関係的側面でいえば返済不可能という負担感覚が底流しているのであって、その矛盾する反対感情の共存が日本人の義理と人情の世界を方向づけていると考えられる。 山折 哲雄 日立デジタル平凡社《世界大百科事典 第2版》より