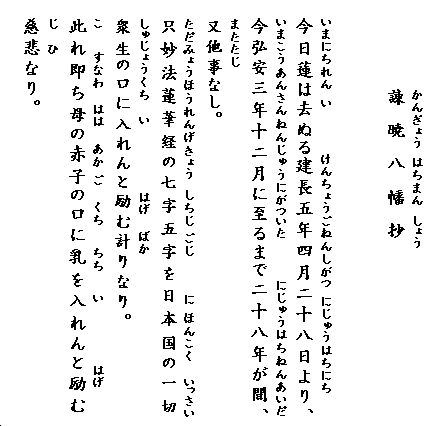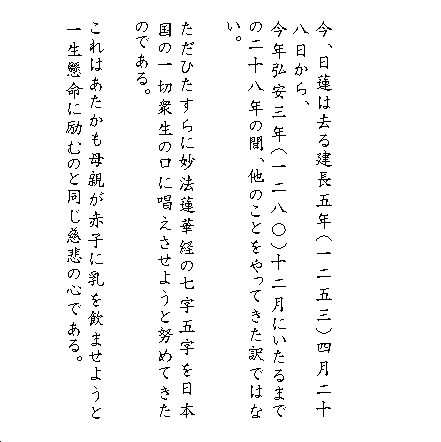|
| 【諫暁】 かんぎょう |
いさめさとすこと。日蓮聖人は、釈尊が末法に法華経を広めることは身命を捨てる覚悟でやりなさいと訓戒したことを、しばしば〈諫暁〉と称した。
転じて、後世幕府・民衆に法華信仰を勧める日蓮聖人の立正安国の運動を〈国家諫暁〉と呼んだ。
御遺文中「諌暁」用例
○教主釈尊、多宝・十方の諸仏の御前にして「今仏前において自ら誓言を説け」と諫暁し給ひしかば、……『神国王御書』
○されば宝塔品には、これらの大菩薩を仏我が御弟子等とをぼすゆへに諫暁して云く「諸の大衆に告ぐ、我が滅度の後、誰か能くこの経を護持し読誦する。今仏前において自ら誓言を説け」と。……『開目抄』
○又日蓮此れを知りながら人々を恐れて申さずば、「寧喪身命不匿教者(にょうそうしんみょうふのくきょうしゃ)(涅槃経如来性品)」の仏陀の諫暁を用いぬ者となりぬ。いかんがせん。いはんとすれば世間をそろし。止(やめん)とすれば仏の諫暁のがれがたし。進退此に谷(きわまれ)り。むべなるかなや、法華経の文に云く、「而も此の経は如来の現在にすら猶怨嫉多し、況んや滅度の後をや」。又云く、「一切世間怨(あだ)多くして信じ難し」等云云。……『報恩抄』
|
| 【建長五年四月二十八日】(立教開宗) |
釈尊一代の諸経典の教相もしくは教時ーその順序次第を判別解釈し,仏教経典の根本真理・釈尊の真意および仏道修行の究極目標を確立して一つの宗派を開くこと。
建長五年(1253)、京畿仏道研鑽を終えて清澄に帰られた日蓮聖人は、四月二八日払暁、昇り来る太陽に向ってお題目を唱え、ここに立教の宣言と伝道の誓願を立てたのである。次いで清澄山の持仏堂の南面において、自己の体得した法華信仰を宣説し、日本の仏教はすべて法華経に帰一すべきことを述べた。
日蓮宗では、聖人が法華経弘通を開始した建長五年四月二八日を、立教開宗の日と定めている。 |
| 【七字五字】しちじごじ |
御遺文中の「五字」「七字」の用例
○只南無妙法蓮華経と計五字七字に限て一日に一遍、一月乃至一年十年一期生の間に只一遍なんど唱ても……『法華題目鈔』
○今日蓮もかくの如し。かゝる身となるも妙法蓮華経の五字七字を弘むる故也。 『諸法実相鈔』
○この本門の肝心、南無妙法蓮華経の五字においては、仏なお文殊・薬王等にもこれを付属したまわず。いかにいわんやその已下をや。ただ地涌千界を召して、八品を説いてこれを付属したもう。
○事行の南無妙法蓮華経の五字、並に本門の本尊いまだ広くこれを行ぜず。『観心本尊抄』
|
|
「日蓮宗事典」 |
|
南無妙法蓮華経の題目を五字七字の題目とよぶ。『観心本尊抄』等に、末法の初めに地涌の菩薩が出現して妙法蓮華経の五宇を末代幼稚の者に服せしめる(定719頁)等と、日蓮聖人の唱題弘通の意義を表している。
ところで元来の趣意からすれば、妙法蓮華経の五字は経名・理法・法体を意味し、南無妙法蓮華経の七字はそれに帰依し、修行する意味であるが、日蓮聖人は「南無」に能証(智)と所証(境)の両意を含むとされた。
そこで「事行の南無妙法蓮華経の五字七字」(『法華題目抄』定三九一頁)や、「事行の南無妙法蓮華経の五字」(『観心本尊抄』定712・719頁)という表現がなされるゆえんがある。
われわれの帰依が南無妙法蓮華経によって確かめられるとともに、その当処に教が詮じ顕されるからである。 |
|
「日蓮聖人遺文辞典」 |
|
……必ずしも五字と七字を区別して用いているわけではない。それは題目南無妙法蓮華経は教法でありつつ観心であり、観心でありつつ教法であるという教観相即の意味を持つからである。
|
以上日蓮聖人御遺文中の「五字」「七字」の用例 と 「日蓮宗事典」「日蓮聖人遺文辞典」所載の抜粋を参考の為、掲げておいた。教学用語の難しさもありなんとなくピンとこない。
要するに日蓮聖人は「妙法蓮華経」も「南無妙法蓮華経」も同じと考えられていた。字数で云えば五字=七字である。普通は「南無」の二字+「妙法蓮華経」の五字で「南無妙法蓮華経」の七字となるのであるが若しそうであるならば、「妙法蓮華経」への「南無」が私達の信のあり方の深浅にかかわり、その信に根ざした行の強弱・多少に関わってくる。
「南無」と「妙法蓮華経」との間隙を埋めようと様々な行が展開される。「南無妙法蓮華経」といくら唱えても所詮二字と五字が離れている以上、「南無」と「妙法蓮華経」との狭間で永遠に苦しむことになるのであろう。所謂九界の因から仏界の果へ至る従因至果の行である。日蓮聖人以前の「南無妙法蓮華経」である。
「妙法蓮華経」はあくまでも久遠の本仏お釈迦さまから私達に付属されるもので、日蓮聖人はその「妙法蓮華経」を「南無妙法蓮華経」の七字ととらえられている。私達が勝手に「南無妙法蓮華経」と唱えるものでなくあくまでも付属なくしては唱えられないものである。付属された「妙法蓮華経」には私達衆生の「南無」もふくまれている。勝手に「南無」する訳にはいかない。
お題目は教主釈尊の付属なくしては「等覚の菩薩・文殊・弥勒・観音・普賢までもたやすく一句一偈をも持」てず、付属される「地涌の菩薩の出現にあらずんば唱え難き題目」であり「仏の御心の我等が身に入せ給はずば唱へがた」い「南無妙法蓮華経」なのである。
|
|
|