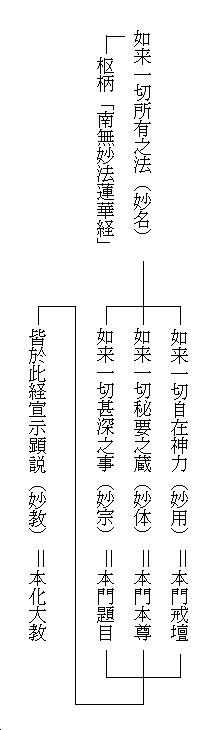自我偈随想 〔第三十四回〕
如来毎自の大本願力 ー その十 ー
○本法三段の正宗分と流通分
前回、私は、法華経の本迹不二・本迹一致という見方は、本門と迹門とを左右にならべた上で不二・一致をいうのではなく、迹門を本門の内に摂取した上でいうものであり、薬王菩薩本時品第二十三以下二十八までの流通分六品もまた本門正宗分の内に摂取したものであって、天台大師が方便品を中心として法華経全体を見たのに対して、日蓮大聖人が寿量品を中心に法華経全体を見たというのは、寿量品を中心としてその前後の諸品を見たのではなく、寿量品そのものの内に法華経全体を見られたのであると述べ、本門八品の儀相をあらわされた大聖人図顕の大マンダラの中に、前迹門の諸仏はもとより流通分の善徳仏をはじめとして迹化の菩薩・鬼子母神・十羅刹女までも勧請列座せしめられている例証をあげ、本誌プリント(八二八頁)に
法華経の見方として、本門八品、乃至寿量一品二半を中心として法華一経を見るということが、実は、本門八品の内に、乃至寿量一品二半の内に、法華一経を摂取し、更に、一切経をも摂取したものであった、ということです。
そこで、本門八品の儀相の再現は、そのまま法華経二十八品を再現することになるわけですが、本門八品の儀相を再現するには、久遠の本仏お釈迦さまを本尊とし、その因行果徳の題目を、如法に受持する外はありません。
即ち、題目を如法に受持する時、その当処に、本門八品の儀相が顕現し、八品の内より二十八品の法華経全体が顕現され、更にそれらすべてが八品の中に摂取されることになるわけです。
と述べておきましたが、私のこの主張に深く心を留められた方は、直ちに大聖人の教判である「本法三段」の中、大聖人が敢えて触れられなかったその流通分に、思いを至されたことと思います。
去る九月二十九日、九州から上京したばかりの玉川道場に、松戸の町行象師が、私の娘の病気見舞をかねて訪ねて来ました。会えば話は、初めから法華経の法門に及び、法華経の説法が無始以来、娑婆世界において繰りかえし繰りかえされて来たものであり、また未来永遠に繰りかえされて行くものであるということが反芻された時、私は観心本尊抄の中に示された方法三段の中の「寿量」の二字の正宗分と、示されていない流通分の示されなかった謎について、私なりの見解を述べてみました。
今、そのことを、次に、もう一度、ふりかえってみたいと思うのです。
さて、本法三段というのは、四種三段の第四項目にかかげられているものですから、まず一往四種三段の概要から述べてみましょう。「日蓮辞典」(一〇八〜一〇九頁)には次のように説明されています。
四種三段
「観心本尊抄」で示された日蓮独自の教判。
三段とは経論の分科に用いられる序分・正宗分・流通分をいい、仏教の全体系をこの三段に区分し、区分の対象を一代・十巻・本迹二経・本法と次第に局限して、妙法蓮華経の五字こそ本法の正宗分であり、十方三世の経々は、衆生をそこに導入するための方便であると帰結する。
一に一代三段。智 の五時教判により、前四時の経を序、法華三部十巻を正宗、「涅槃経」を流通と見る。
の五時教判により、前四時の経を序、法華三部十巻を正宗、「涅槃経」を流通と見る。
二に一経三段、または十巻三段。開経の無量義経と法華経序品を序、方便品から分別功徳品の前半まで十五品半を正宗、その後の十一品半と結経の観普賢経を流通とする。
三に二経六段、または十巻六段。これに迹門と本門との両三段があり、ここを離開して五重三段とも呼ぶ。
迹門三段は、無量義経と法華経序品を序、方便品から人記品まで八品を正宗、法師品から安楽行品まで五品を流通とする。
本門三段は、涌出品の前半を序、その後半と寿量品と分別品の前半の一品二半を正宗、分別品の後半から観普賢経までを流通とする。
迹門は、教主は始成正覚、所説は本無今有の百界千如、大通結縁を説く故、方便として斥けられる。本門は、教主は久遠実成、所説は十界久遠、久遠下種を説いて、迹門と「天地」の相違があり、本門観心とは「竹膜」の僅差にすぎないと賞揚される。
四に本法三段、または文底三段・法界三段・観心三段ともいう。大通仏の法華説法以来の十方三世諸仏の微塵の経々を序とし、末法下種の要法たる「題目五字」を文底に秘めた寿量の一品二半を正宗とする。流通分については言及されないが、日蓮の末法弘通を流通分に当てる解釈もある。
四種三段は教判である以上、おのずから重々の勝劣関係が示されたことにはなるが、最後の本法三段中の正宗分を取って、その他を捨てる取捨の関係を示すと見るよりも、妙法五字を帰結とし、その他をここに導入するための妙法方便とした、と見る方が適切である。
以上は四種三段の項の全文ですが、なお「日蓮辞典」(二七〇頁〜二七一頁)には特に本法三段について更に詳しく説明されていますので、煩瑣でもその全文を次に引用してみましょう。
本法三段
「観心本尊抄」に説かれる四種三段の最後の三段で、
「また本門において序正流通あり。過去大通仏の法華経より乃至現在の華厳経、乃至迹門十四品、涅槃経等の一代五十余年の諸経、十方三世の諸仏の微塵の経々は、みな寿量の序分なり。
一品二半よりの外は小乗経(略)その機を論ずれば徳薄垢重(略)。爾前・迹門の円教すらなお仏因に非ず(略)、たとえ法は甚深なりと称すとも、未だ種熟脱を論ぜず、還って灰断に同じ、化に始終なしとはこれなり(略)、之等はしばらくこれをおく」
の文をいう。
前の本門三段が、本門十四品の文上に関する判釈であったに対して、今はその文底、観心の段階において三段を分別するから観心三段・文底三段とも異称し、また法界に、ありとあらゆる微塵の経々の中から本法を詮顕するから法界三段ともいう。
本法とは種熟脱三益の根本法たる妙法五字をいう。「一品二半」といえば本門三段のときの正宗分たる「寿量品と前後の二半」と同じことのような感を受けるが、今は一品二半という経の文底に沈められた妙法五字を指す。これを「寿量」ともいい、後には「内証の寿量品」「寿量品の肝心たる名体宗用教の南無妙法蓮華経」とも呼ぶのである。
十方三世の諸仏の微塵の経々は、妙法五字を詮顕するための序分であり、妙法五字は、それらの経々の帰趣たる本法であるというのが、ここでの主張である。
また前の三種の三段のときは三段が具備していたが、今は流通分について述べられていないが、末法に弘めらるべき南無妙法蓮華経であるとも、また本鈔の次下に末法における上行菩薩たる日蓮の弘通が説かれることに着眼すれば、次下の日蓮末法弘通こそが流通分であるとも解釈されている。
さて、ここで注意しなければならないことは、本法三段の正宗分について、四種三段の説明文では「末法下種の要法たる題目五字を文底に秘めた寿量の一品二半を正宗とする」といい本法三段の説明文では「一品二半という経の文底に沈められた妙法五字を指す。これを「寿量」ともいい、後には「内証の寿量品」「寿量品の肝心たる名体宗用教の南無妙法蓮華経」とも呼ぶのである」と述べられていることです。
もとより「妙法五字を文底に秘めた一品二半」と「一品二半の経の文底に沈められた妙法五字」とでは、内容はともかくとして形体はまったく異なっているものです。然るに、同じ「日蓮辞典」の中で、観心本尊抄の本法三段正宗分の「寿量」の二字を、或は妙法五字といい、或は一品二半というのは、一体どういうことでしょう。
文上文底については「日蓮辞典」(二九〇頁)に、
文上文底
「開目抄」の「一念三千の法門は、ただ法華経の本門寿量品の文の底に沈めたり……」の文により、寿量品の文上と文底をいう。
日蓮の意は、「一念三千の法門は、久遠釈尊が寿量品の文の心において示されたものである」というのであって、文上と文底を比較相対したものではない。
すなわち、本門寿量品の文を捨てて底をとるのではなく、文を通した底(文の義意)に一念三千の法門があるのである。
日蓮正宗で、文上と文底に相対を立て、前者を釈迦仏法にして文上脱益、後者を日蓮仏法にして文底下種とし、日蓮本仏を説くのは誤りである。
と説明されている通りであって、文上に対する文底なるものがあるのでなく、寿量品の自我偈の冒頭にも、
我れ仏を得てよりこのかた経たる所の諸々の劫数、無量百千万億載阿僧祇なり。常に法を説いて無数億の衆生を教化して仏道に入らしむ。しかしよりこのかた無量劫なり。
という久遠の本仏お釈迦さまと、仏道に入らしめられた無数億の九界の衆生との不二相即する十界互具の当処、既に久遠劫来、事成の一念三千の顕現されているのを、時いまだ至らざるが故に、付嘱の人に非らざるが故に、等々の理由によって、龍樹・天親・天台・伝教等の正法像法の先師は、知っていても、これを拾い出さず、判っていても、これを説きあらわすことはなかったため、あたかも一念三千の法門は寿量品の文の底に沈められていたようなものであった、と申されたのです。
一念三千の法門は、ただ法華経の本門寿量品の文の底に沈めたり。龍樹・天親知って、しかも拾い出さず、ただ我が天台智者のみこれをいだけり。
とは、まさしくこの意であって、「事の一念三千」は寿量品の文の底に沈められていたのでなく、文上、既に顕現していたものであり、これを宣説する者は、正法像法の人師ではなく、末法々滅尽時に大地より涌出する本化地涌の菩薩のみに選ばれていたのです。
今、まさに末法の時、この時、顕現されたのは「事の一念三千」のみでなく、実はお釈迦さまの久遠実成の仏身が顕現され、それによってはじめて一念三千は真の一念三千となり、久遠の本仏お釈迦さまと、久遠の本法一念三千の妙法五字と、久遠の所化地涌の菩薩との三者不二一体を中心とする久遠の仏界の顕現している当処をさして、本法三段の正宗分に、ただ「寿量」と仰せられたのです。
大聖人は観心本尊抄のこの段において、明らかに「寿量」と明示されたのであって、「寿量品」と書かれてはいないのです。また「妙法五字」とも記されてはおりません。「寿量」とは「寿量品」の三字の中、「品」の一字を書き落とされたのでもないのです。
大聖人が敢えて正宗分を「寿量」といい、更に敢えて流通分を示されなかったのは、迹門所説の三千塵点劫の昔、大通智勝仏をはじめとする三世十方の無量の諸仏の説かれた経々、それは本門一品二半を除くすべての経々、たとえ一品二半以降に説かれた法華経、或は涅槃経をも序分とし、更に五百億塵点劫来、脈々として継承されて来た本仏、本化本法の本門の三宝を中心とする躍動の仏界を正宗分とし、その仏界が未来永劫、娑婆世界に間断なく繰りかえし繰りかえして展開されて行くことを流通分としたためであった、と申されましょう。
九月二十九日のお昼すぎ、玉川道場で町行象師に語ったことは以上のようなことでした。この時、町師はエリアーデの著「聖と俗」を読んでいたせいもあってか、私の説に賛同し、
「法華経の法門が無始以来、全く同じ儀相のもとで、同じ内容を繰りかえし繰りかえして説かれたものであり、また未来永遠に同じことを繰りかえして行くという見解に立つならば、本法三段の正宗分はそのまま流通分にも該当するといえるわけで、大聖人が本法三段の流通分に言及されなかった理由も、納得されそうです」
と答えていました。
然し大聖人は、本法三段の項においては流通分の内容を、正宗分の寿量の仏界と全く同一のものと仰いでいたため、敢えて流通分の内容には触れられてはいませんが、この寿量の仏界、本仏・本法・本化の本門の三宝一体不二という動的世界を如何にして娑婆世界に実現するかという方法論については、観心本尊抄の末尾にあたって、
我が弟子、これをおもえ。地涌千界は教主釈尊の初発心の弟子なり。寂滅道場にも来らず、雙林最後にも訪わず、不幸の失(とが)これあり。迹門十四品にも来らす、本門六品には座を立って、ただ八品の間に来還せり。
かくの如き高貴の大菩薩、三仏に約束して、これを受持す。末法の初めに出てざるべきか、まさに知るべし、この四菩薩、折伏を現ずる時は、賢王となって愚王を誡責し、攝受を行ずる時は、僧となって正法を弘持す。
と述べ、また、
この時、地涌千界出現して、本門の釈尊の脇仕となり、一閻浮提第一の本尊、この国に立つべし。
と勅し、或は、
一念三千を識らざる者には、仏、大慈悲を起して、五字の内にこの珠をつつみ、末代幼稚の頸にかけさしめたもう。四大菩薩、この人を守護したまわんこと、大公周公の成王を摂扶し、四皓が恵帝に侍奉せしに異らざるものなり。
と示されている通りなのです。
「日蓮辞典」における本法三段の説明文によれば、
「日蓮の本法弘通こそが流通分であるとも解釈されている」
と述べられていますが、本法弘通とは、ただ題目を弘め、題目を唱える人の声を増すというのではなく、本法三段正宗分の寿量の仏界、本仏・本法・本化という本門の三宝不二一体の世界を復活再現することであり、この大眼目のために、大聖人のみでなく、末法にして題目を唱うる者は悉く地涌千界の本化の菩薩として、本門八品の間を来還しつつ、みずから本仏お釈迦さまの脇士となり、一閻浮提第一の本尊を日本国に建立し、摂受・折伏の伝道を展開して行くのです。
如何に摂折二門の弘通よろしきを得て多くの信徒を擁し、見事な仏像を造立し、壮大なる寺院殿堂を建立したとしても、本門一品二半寿量の仏界を再現するという大眼目をはずしては本法三段の流通分にはならないのです。
今、私は、
「末法にして題目を唱うる者は悉く地涌千界の本化の菩薩として、本門八品の間を来還しつつ、みずから本仏お釈迦さまの脇士となり、一閻浮提第一の本尊を日本国に建立し……」
と申しましたが、地涌の菩薩が本門八品の間を来還するのは、お釈迦さま御在世当時霊山虚空会説法の時だけではないのです。末法娑婆国土において法華経を受持する毎に題目を唱うる毎に、八品来還が常に繰りかえされるのです。人ごとではありません。私たち自身が題目を唱えながら本門八品の間を来還するのです。そして、この行動を称して「法華経を色読する」といわれているのです。
なお「日蓮辞典」では、本法三段の流通分のことを、
「末法にして弘めらるべき南無妙法蓮華経であるとも……解釈されている」
と説明されていましたが、本法三段の流通分を云々する以上、それは題目そのものでなく、題目を唱えることによって本門寿量の仏界(本仏・本法・本化という本門の三宝不二一体なる動的世界、五百億塵点劫来、常に変わることなき久遠の仏界)を、眼前に再現することでなければなりません。
元来、正宗分というのは実体を論ずるものであり、流通分というのはその実体を具現する方法を論ずるものであるはずです。ところが「日蓮辞典」においては実体論と方法論とが混同されてしまっており、このため、流通分を「南無妙法蓮華経」の題目であるとか、或は「日蓮の本法弘通」である等と説明されているようです。
それというのも、正宗分の「寿量」の二字が、本門三宝の不二一体なる動的仏界であるという実体を、しっかりと把握し、踏まえていなかったせいであるかも知れません。そのため本法三段正宗分の「寿量」の二字を説明するのに、「四種三段」の項においては、
末法下種の要法たる「題目五字」を文底に秘めた寿量の一品二半を正宗とする。
といい、「本法三段」の項においては、
「一品二半」といえば、本門三段のときの正宗分たる「寿量品と前後の二半」と同じことのような感を受けるが、今は、一品二半という経の文底に沈められた妙法五字を指す。
これを「寿量」ともいい、後には「内証の寿量品」「寿量品の肝心たる名体宗用教の南無妙法蓮華経」とも呼ぶのである。
というように、「寿量」の実体が、妙法の五字なのか、一品二半なのか、そのいずれともつかない曖昧さを露呈してしまっているのです。そして、そこに強調されているのは、四種三段の第三にあげられている本門三段の正宗分一品二半と、第四にあげられている本法三段の正宗分「寿量」の一品二半とは、「竹膜を隔てた」ような差ではありながらも、妙法五字を文底に秘めているか、秘めていないか、という重大な相違があるということにすぎないのです。
勿論、本法三段の正宗分「寿量」を一品二半とみなし、この一品二半の文底に妙法五字が秘められているとするため、本門三段の正宗分一品二半と区別して、敢えて「題目五字を文底に秘めた寿量の一品二半」といい、或は「内証の寿量品」という文を引き、または逆に言い廻して「一品二半という経の文底に沈められた妙法五字」といい、或は「寿量品の肝心たる名体宗用教の南無妙法蓮華経」の文を引きあいに出しているにすぎません。
然し、前にも述べましたように文上文底というのは大聖人の教判ではなく、大聖人が「一念三千の法門は、ただ法華経の本門寿量品の文の底に沈めたり」と仰せられていたのは、仏滅後、正像二千年の間の先師は、龍樹にしても天親にしても、天台・伝教にしても、時の至らざる故に、付嘱の人に非らざる故に、寿量品所顕の事成の一念三千の法門を宣説せず、末法に出現する地涌の菩薩にそれを譲られたため、あたかも正像二千年の間は、一念三千の法門が寿量品の文の底に沈められていたようなものであったというのであって、文上と文底の相対、教観相対を主張しているのではなく、むしろ末法にしてはじめて開顕される教観一体の寿量品の大事を強調されているのです。
従って、四種三段の第三にあたる本門三段の正宗分一品二半は、いうところの文底の妙法五字に相対した文上の教ではなく、既に、妙法五字を顕現している一品二半であり、またそうであればこそ、寿量の立体的仏界、久遠劫来、躍動してやまない本因本果不二の動的世界と、わずかに竹膜をへだてているにすぎない、と申されたのです。
すなわち、本法三段正宗分の「寿量」とは、そうした動的仏界そのものであり、本門三段正宗分の一品二半は、動的仏界を説いた教えであるということが出来ましょう。ここに「日蓮辞典」にいう「寿量」の説明文が正鵠を得たものではない、といえるのです。むしろ、「題目の五字を文底に秘めた寿量の一品二半」であるとか、「一品二半という経の文底に沈められた妙法五字」であるといった説明は、却って混乱を増すばかりでしかありません。
大聖人は四種三段の教判をもって、一代三段の広より、一経三段の略へ、更に本門三段の要へと迫り、八萬法蔵の教々を広略要と詮じ来った上、窮極の本門一品二半の教が示している久遠の本仏お釈迦さまを中心とする本因本果不二一体なる立体的・動的仏界に転じられたのです。
この大転換は、八萬法蔵という一切経を対象として、これを教相判釈して来った静的批判の立場を一擲し、対象の立体的仏界に転入し、その動的仏界に自己の立場を定められたということであり、今度は、その立場に立って一切経はもとより、三千塵点劫の昔大通智勝仏の説かれた経々をはじめ三世十方の諸仏の説かれた経々、宇宙法界のすべての経々をも悉く、この寿量仏界へ導入する序分として摂取開会しようとしたのが、本法三段の構成となったのです。
寿量仏界、それは五百億塵点劫来、娑婆世界に完成されていた不滅の仏国土であり、従地涌出品に示されている通り、顛倒の衆生には見ることも出来なかった大地の内の虚空浄土でした。
その浄土は、久遠実成の本仏お釈迦さまを中心として、六萬恒河沙の本化地涌の菩薩たちがその脇士となって囲繞充満し、師弟共に、父子一体となって妙法の題目を唱えあっている躍動の世界であり、三界の衆生の顛倒流転より超越したところの「三災を離れ四劫を出でたる常住の浄土」でした。この浄土こそ、無始無終に宇宙法界の中心軸となっている厳然たる実在でした。如来久遠の大本願と、毎自の大本願呪力の充満し躍動してやむことなき救済の世界でした。
この寿量世界のことを、観心本尊抄に、
今、本時の娑婆世界は、三災を離れ、四劫を出でたる常住の浄土なり。仏、既に過去にも滅せず、未来にも生ぜず、所化もって同体なり。これすなわち己心の三千具足三種の世間なり。
と仰せられているのです。
思えば、四種三段は宇宙の核心を顕発した壮大なる教判でした。大聖人は宇宙核心たる寿量仏界の実在を信じ、この世界をそのまま地上に実現する使命に生涯を捧げられたのです。そこで必然、大聖人一期の弘通が本法三段の流通分であるということになって来るわけですが、その弘通は、単に題目信仰を弘めるというのでなく、題目信仰を弘めることによって寿量仏界を地上に実現せしむることであった、ということに注意しておかねばなりません。
観心本尊抄に、本門の戒壇の戒壇本尊を密釈されたという有名な一句があります。
この時、地涌千界出現して、本門の釈尊の脇士となり、一閻浮提第一の本尊、この国に立つべし。
上行・無辺行・浄行・安立行という四大菩薩を上首とする六萬恒河沙の本化地涌の菩薩が、本門の教主久遠の本仏お釈迦さまの脇士となって囲繞充満する世界、それはまさしく本法三段正宗分の寿量仏界でした。その寿量仏界がそのまま末法娑婆世界に本門戒壇の戒壇本尊として密釈されているのです。
ここに四大菩薩を東西南北に配座した「一尊四士」本尊様式が現されて来るのですが、この一尊四士本尊様式こそ、寿量仏界の中心核を象徴するものであった、ということに深く心を留めておかねばなりません。
現在、中山法華経寺の法華堂内陣に秘仏として格護されている二具十体の二組の一尊四士仏像は、大聖人が身延山中、みずから開眼された戒壇本尊の雛形であったとも申されましょう。
なお日蓮宗学上、本尊様式として二仏並座の儀相にもとずいた二尊四士様式や、大マンダラの中核を図像化した一塔両尊四士様式もありますが、かねて多宝如来とは生身のお釈迦さまの久遠実成を開顕するための秘妙方便身であったと、これまで縷々述べて来たことによっても、一尊四士様式をもって正意とすべきでありましょう。
私は最近、読経唱題の前に、御宝前に伏して本門の三宝諸天を勧請するに当たって、必ず、
「霊山虚空会上、本門八品の儀相を整え奉り……」
と述べることを常としていました。祈願の時も霊供養の時も、朝夕のお勤めの時も、欠かさず、この言葉を述べていました。これを述べることによって、お釈迦さま御在世当時の霊山虚空会上の本門八品の儀相が現在前していることを確信しようとしていたのです。
そして目には見えないながらも、八品浄土の儀相の中にあって、八品以前の序品・方便品・提婆達多品を読み、八品以降の普門品・陀羅尼品等々も読んでいました。それは迹門の諸品であれ、本門流通分の諸品であれ、それらは悉く本門八品の中に摂取されているもの、と信ぜられていたからです。
あれは、去る九月二十三日、秋の彼岸の中日の午後四時三十分から六時までの一時間半の祈願中のことでした。この日、午後一時二十分、新幹線で東京につき、病気中の娘の潤子を見舞い、玉川道場の御宝前にぬかずいて、娘の当病平癒の御祈願に入ったのです。娘は数え年十六才でしたから、年の数だけ自我偈を繰りかえして唱えていました。
何巻目を唱えていた頃でしょうか、御宝前のお釈迦さまの仏像のお顔を仰ぎながら自我偈を読誦していた時、全く思いもかけずに、
「本法三段の正宗分〈寿量〉の二字は、本仏・本法・本化の三宝不二一体なる動的仏界をいう。流通分はその仏界を地上に再現することである」
という想念が、我れにもあらず湧き起こり、全身に満ちみちて、身ぶるいするほどでした。
子供の病気平癒を御祈願している最中、突如、突拍子もなく、こういう想念が湧き起こったのでしょう。かねて頭で考えて三宝勧請のさい、「霊山虚空会上、本門八品の儀相を整え奉り……」と述べていたことが、子供の一命をかけた真剣な御祈願をすることによって、はじめて実感されたからでしょうか。
若し、この想念を感応教示というならば、或いはそうであるかも知れません。幸い娘はこの御祈願によって一命をとりとめ、九月三十日、無事退院することが出来たのですが、それにしても忘れることの出来ないのは、この感応教示の如き想念の湧き起こったことです。
これによって私が、これまで、そうではないか、と想定していた本法三段正宗分の「寿量」の意味、そしてそこに流通分の示されていなかった意義に対して、一層の確信を深めることが出来たのは事実です。
九月二十九日、松戸より来堂した町行象師にも、この体験を語ったのですが、先師は「寿量」の二字、或は流通分をどのように解釈していたのでしょう。「日蓮辞典」における説明文に対する批判は、これまで、くどくどと述べて来た通りですが、ここで私が参照したかったのは山川智応博士の見解でした。
私が所持する山川博士の著「観心本尊抄講話」は、身延の釈迦牟尼堂の書棚の中に入れてあって、これを取りに、わざわざ東京・身延の間を往復するのも大儀なことと思っていた処へ、渡りに舟とはこのことでしょう。横浜の猪瀬秀成氏から電話が入り、
「十月五日、従業員およそ二百名ばかりをつれて身延山に参拝し、上ノ山の井上清純先生の宝塔の前で法要をいとなむことになったので、その際、一時間ばかり法話をしてもらいたい」
ということでした。快諾したことはいうまでもありません。
さて十月五日、身延山上ノ山での法要後、一時間ばかりの法話にも本法三段正宗分の「寿量」の仏界を語り、その流通分にも及んだのですが、その後、直ちに釈迦牟尼堂へ登り、さっそく山川博士の「観心本尊抄講話」を開いてみました。
本法三段については同著(四八一頁より四九六頁)十六頁にわたって詳細に語られていました。その書説については、全面的に賛同できないものがあり、批判も加えねばならないと思うのですが、曽って、一度読んだ時に赤線を引いていた箇所がありましたので、それを次に引用してみましょう。
大体が流通ということは「能流通」ということで、流通せらるべき法体、即ち「所流通」たる正宗分の法体を流通することである。だから流通分は、正宗分と別の法体があるのでなく、正宗分の法体を流通する行法や、流通の法軌や、流通の功徳や、流通の依師などが説かれているのが流通分なのである。
既に、
「過去大通仏ノ法花経ヨリ、乃至現在ノ花厳経、乃至迹門十四品・涅槃経等ノ、一代五十余年ノ諸経、十方三世ノ微塵ノ経々」
を序分としてあるが、さういう黄巻赤軸の経巻はないはずだし、正宗分の「内証ノ寿量品」という「寿量品ノ肝心妙法蓮華経ノ五字」でも、二十八品のいずれを繰り返しても、そういう文字はない。
そこで知らねばならぬ。この本法三段は、序・正ともに既に黄巻赤軸の文字でない。流通分もそうであろう。文字でなければ何であるか。それは文字でなくて、その「所流通」の正宗なる、「内証ノ寿量品」を流通するところの、「能流通」の地涌の菩薩の弘通化導が、即ち、この本法三段の流通分なのであろう。
ここで私が同意を表する処は、本法三段の正宗分にしても流通分にしても「黄巻赤軸の文字でない」というのです。
但し、その序分までも「黄巻赤軸の文字でない」というのは言い過ぎというよりは、むしろ誤りといわねばなりません。大聖人は明らかに、
過去の大通仏の法華経より、乃至現在の華厳経、乃至迹門十四品・涅槃経等の、一代五十余年の諸経、十方三世の諸仏の微塵の経々は、皆、寿量の序分なり。
と仰せられているのですから、序分に当たるそれらの経々は、あくまでも黄巻赤軸の文字であり、その義でなければなりません。それらの経々を導入方便の序分として、本門一品二半に顕現している寿量の動的仏界に入るのです。
そしてその仏界から、ひるがえって、それら悉くの経々、並びにその経々による信行と信行者を一人も漏れなく開会摂取して行くのです。
山川博士は「観心本尊抄講話」(四八三頁)に、本法三段について研究を要する四項目をかかげ、その第二項目に、
つぎは、序分として挙げられた中に「本門十四品」が除かれていることである。除かれているのは正宗分であるからというには、正宗分は「寿量」と挙っているのだから、そういうわけには考えられない。正宗分でもなく三段を含んだ全体でもないとすれば、流通分であろうかというと、その中に正宗として挙げられた「寿量品」があるのだから、流通分であるともいえない。これはよく考えねばならぬとなる。
と述べていますが、みずからこの提唱に対して何も答えてはおりません。答えられないのが当然であるかも知れません。
何故ならば、山川博士自身、開目抄の「文底秘沈」の意義を取りあやまって、文上文底相対(底上相対)という教判を起こしてしまっていたからです。
山川博士が本法三段の序分の中に「本門十四品」が除かれていることに着目されたことは、さすがに学者であると敬意を表する処ですが、文上の寿量品に対して文底の寿量品を主張する以上、本門十四品も必然、文底寿量品の序分に入っていなければなりません。すると大聖人が序分の中に本門十四品を、ことさらに除いておられたかという意義は、いよいよ不明になってしまいましょう。
山川博士をはじめ、これまでの宗学者の殆どは、本門三段の正宗分一品二半の文底に本法三段が設定されていると錯覚し、本法三段を文底三段とか法界三段とも別称して来ていました。
ところが、教観一体不二の立場にあられた大聖人は、本門三段の正宗分一品二半に顕現している寿量の仏界を、本門十四品の上に、そのまま観取されていたのです。そのため本法三段の序分にわざわざ本門十四品が除かれていたのです。
厳密に言うならば、本門十四品ではなく、本門八品というべき処でありましょう。本門十四品とされたのは天台教学の科分体系を借りに踏襲されたのにすぎないのです。
本門三段正宗分一品二半に顕現されている本因本果不二なる躍動の仏界、それが本法三段正宗分の「寿量」の世界であり、その世界を末法娑婆世界に再現することが本法三段の流通分であり、その網格は、既に本門三段の流通分(本門八品の中、序分と正宗一品二半を除く間)に示されていたものであり、特に、常不軽菩薩品には、常不軽菩薩の三世にわたる行軌として示されていたものであったのです。
山川博士は本法三段について研究を要するという第三項目に次のように述べています。
つぎは正宗として挙げられた「寿量」の二字である。この寿量を単に十四品の中の寿量品とすべきであろうか。または一品二半をば「法華取要抄」に、「広開近顕遠ノ寿量品」といわれた、その寿量品の意味であろうか。
それとも、その文上の一品二半によって顕わされたる文底の一品二半、即ち、九界衆生を愛子とし所具とする本仏の無始実在と、その無始の本仏を父とし所具とする九界衆生と、この生仏父子を一体不二とする一念三千の本仏所証の教義、それをいうのではなかろうか。
それからまた、次下の御文には、単なる「寿量」でなく、「内証ノ寿量品」というのがある。すなわち、
迹化他方ノ大菩薩等ニハ、我ガ内証ノ寿量品ヲ以テ授与スベカラズ。末法ノ初メハ謗法ノ国悪機ナルガ故ニ、之〔迹化他方ノ弘通ノ誓願〕ヲ止メ、地涌千界ノ大菩薩ヲ召シテ、寿量品ノ肝心タル妙法蓮華経ノ五字ヲ以テ、閻浮ノ衆生ニ授与セシムルナリ。
で、この御文を見ると、初めに迹化他方の誓願を止めて授与せられなかったものが「内証ノ寿量品」であって、地涌本化を召し出して授与せられたものが「寿量品ノ肝心タル妙法蓮華経の五字」であるのだから、妙法五字すなわち「内証ノ寿量品」「寿量品ノ肝心」であることには、異論ができない。
そこで、「寿量ノ序分ナリ」と、上のおびただしい法界的の経々を序分とする正宗「寿量」とは、妙法五字ではなかろうかということ。
(中略)
だから一品二半の所詮となり、四十五字の法体によって顕わされている本仏果上、本法受持の一念三千の教義か、または下の文に「内証ノ寿量品」と仰せになっている妙法五字かを、本法三段の正宗としなければならないようになる。
所謂、山川博士は本法三段正宗分の「寿量」を、寿量品文底の一念三千の教義であり、大聖人が仰せられた「内証の寿量品」であり「寿量品の肝心たる妙法蓮華経の五字」であるとし、その主張を「観心本尊抄講話」の全体にわたって力説されているのです。「日蓮辞典」の解説も、これに準じたものと申せましょう。
然し、ここに彼等の大きな錯覚があるのです。たしかに本法三段正宗分の「寿量」とは本因本果不二一体なる仏界であり、本仏果上の一念三千の世界ではありますが、一念三千の教義とか「内証の寿量品」とか「寿量品の肝心たる妙法五字」という付嘱の法体ではないのです。
無始無終に躍動してやまない寿量仏界においては、久遠の本仏お釈迦さまを中心として、これを囲繞する本化地涌の菩薩たちが、父子一体となって、本仏お釈迦さまの因行果徳の題目を唱えあっています。
今、その様相を、仮に平面図の上で見つめれば、地涌の菩薩は四方の地平線のかなたにまでもひしめき、その中央に上行・無辺行・浄行・安立行という四大菩薩が群を抜いてそびえ、その四大菩薩の中央に久遠の本仏お釈迦さまが常説法印をむすんで端坐され、本仏と本化の唱える題目の大合唱は、こだまとなって全宇宙に轟いている、と申せましょう。まさに広大無辺なる仏界というほかはありません。
大聖人が「内証の寿量品」といわれたのは、このような動的仏界の様相を顕説した寿量品という経であって、こういう経が迹化他方来の菩薩たちに付嘱されるはずはありません。
また本化地涌の菩薩に付嘱された妙法五字というのは、この動的仏界において既に久遠劫来、唱えられて来た題目であったのです。
山川博士をはじめ多くの宗学者たちが錯覚したのは、動的仏界そのものを、或は内証寿量品(文底の寿量品)と思い、或は文底秘沈の妙法五字と思ったことにあるようです。
それには「一秘即三秘」という先入観が潜んでいたせいであるかも知れません。ここに再び「一秘三秘」を問題としてとりあげねばなりませんが、「一秘三秘」は大聖人の法門でなく、後世の宗学者によって造りあげられた誤った思想にすぎないのです。
ここにいう一秘とは三秘総在の妙法五字のことであり、三秘とは本門の本尊・本門の題目・本門の戒壇のことです。山川博士は同著(五六一頁〜五六二頁)に次のように述べています。
「妙法蓮華経五字」とあるのは、三大秘法を総じて含めたる妙法五字で、単なる本門題目なのではない。(中略)
その理由として、
第一に、逆縁のために、法華経に帰命せよ、南無妙法蓮華経と唱えよ、と勧める題目が、若し、三秘の中の題目だけの内容だとするならば、本尊と戒壇とは、いずれから来るのであろうか。
その題目以外のいかなるところから来るのか、それを答えねばならなくなるが、それは決して、その南無妙法蓮華経以外のところから来るということはいえないはずである。
すると、逆縁のために、ただ妙法蓮華経の五字に限るのみといわれている妙法五字は、当然に三秘総在の妙法五字でなければなるまい。
と論じているのですが、心ある人が右の理由を聞いたならば、思わず吹き出してしまうことでしょう。
「題目が、若し、三秘の中の題目だけの内容だとするならば、本尊と戒壇とは、いずれから来るのであろうか」
という設問は、本門の三宝一体不二、三秘相即の実在を知らない者の愚問にすぎないのです。
山川博士は、この設問を反論として三秘の出処を、三秘総在する一秘の妙法五字とし、更にこれを本法三段正宗分の「寿量」に当てて会通しており、また或る人々は、
「本尊の実体も一念三千・妙法五字、題目の実体も一念三千・妙法五字・戒壇の実体も一念三千・妙法五字であるから、三秘は一念三千・妙法五字より開出される。総在の一秘があってこそ三秘の修行門が開かれるのである」
と主張しています。こういう主張は日蓮門下大半にわたってなされているようです。
これに対して、
「大聖人がいわれる一念三千は、宇宙の理法ではなく、本仏お釈迦さまによって成就された事成の一念三千であり、妙法五字にしても本仏お釈迦さまの因行果徳の二法であるのだから、一念三千にしても妙法五字にしても、お釈迦さまの功徳体として、お釈迦さまより開出されたものである」
と反論する人もないではないようです。
ここに人本尊・法本尊という論争が起こり、両者を折中した人法不二論も起きて来るわけですが、こういう発想は、前にも述べたことがありましたように、
「ニワトリが先か、タマゴが先か」
という幼稚な論争と何ら変わらないものなのです。
若し、ニワトリとタマゴと、そのいずれが先かと言い争うならば、無限の過去にさかのぼっても果てることはないでありましょう。それと同様に、お釈迦さまと妙法五字とは、いずれが先かということを決めるにしても、如何に五百億塵点劫の昔にさかのぼったとしても到底、決めることは出来ないでありましょう。
こういう思考は、因果を縦に見た相対的時間観念にもとずくものであり、若し、相対を超越した絶対時間・久遠の時間に立つならば、両者を横に見て、そこに不二相即している前後際断の独立境が実在しているはずです。即ち、三秘相即する本門の三宝不二一体という実在です。
そこには、三秘相即する奥に、三秘総在する一秘など存在するものでなく、その必要もなく、またそういう一秘の存在を想定すること自体、既に相対観念におち入った妄想というほかはありません。
一秘即三秘、三秘総在の一秘という法門を説き出したのは、「祖書網要」二十三巻をあらわし近世宗学の基礎をなしたという一妙院日導上人(一七二四―一七八九)であったともいわれていますが、いずれにしても、この法門によって如何に日蓮大聖人の教学がゆがめられたか、その弊害の大きさに悲憤すら覚えしめられるほどです。
たとえば三秘総在の一秘思想は、大聖人図顕の大マンダラ観にも及び、山川博士は、同著(五七一頁)に次のように述べているんです。
大曼荼羅の中尊の南無妙法蓮華経は、名は法であっても体は仏でなければならない。左右の釈迦・多宝は、妙境妙智を表して、八品会上の能説を示し、また五百億塵点劫来の能覚を示し、中央の南無妙法蓮華経は、所説に約しては、境智冥合の常住の仏果を表し、所覚に約すれば、無始の本覚を示されたもので、ともに本仏釈尊の久遠本有常寂常照の一念三千で、本仏の本体をお挙げになったものである。
この文章は非常に難解なものに思えますが、要するに大マンダラ中央の題目こそ、三秘総在の一秘であり、二仏並座のお釈迦さまと多宝如来とが境智の二法を表しているのに対して、中央の妙法五字は境智冥合の仏果をあらわし、お釈迦さまが、たとえ五百億塵点劫の昔に成道された仏であったとしても、なお能覚の仏(始覚の仏)であり、これに対して妙法五字こそ、五百億塵点劫を超える無始の本覚体であり、久遠実成の本仏の本体である、と述べているのです。
また同著(一〇〇頁)には次のようにも述べています。
況わんや聖文の付嘱の段は、上の本仏果上の一念三千を説かれたる後、
迹門十四品ニ未ダ之ヲ説カズ、法華経ノ内ニオイテモ時機未熟ナルガ故カ。コノ本門ノ肝心南無妙法蓮華経ノ五字ニオイテハ、仏ナオ文殊・薬王等ニモ付嘱シタマワズ、イカニ況ヤ、ソノ已下オヤ。タダ地涌千界ヲ召シテ、八品ヲ説イテ之ヲ付嘱シタモウ。
と叙したまえる後、上をうけて「ソノ本尊ノ体タラク」と仰せられ、「ソノ」とうけられたことは明らかで、自然に所属の法体は、三秘総在の南無妙法蓮華経なることを物語っているではないか。
即ち、付嘱の法体は、三秘総在の一秘である大マンダラ中央の南無妙法蓮華経であり、それがそのまま本尊の本体であるといっているのです。
然し、「その本尊の体たらく」という「その」とは、三秘総在の一秘の題目をさしていっているのではなく、地涌千界の本化の菩薩を脇士と召して、これらに三秘相即する題目を付嘱している本仏お釈迦さまをさしているのです。
また「その本尊の体たらく」以下の文章として、
本師の娑婆の上に、宝塔空に居し、塔中の妙法蓮華経の左右に釈迦牟尼仏・多宝仏、釈尊の脇士は上行等の四菩薩、文殊・弥勒等は四菩薩の眷属として末座に居し、迹化他方の大小の諸菩薩は、萬民の大地に処して雲閣月卿を見るが如し。十方の諸仏は大地の上に処したもう。迹仏迹土を表する故なり。
と大マンダラ仏界と菩薩界の宇宙大の様相を叙述された後、これをうけて、
かくの如き本尊は、在世五十余年にこれなし。八年の間にも、ただ八品に限る。
と仰せられた「かくの如き本尊」とは、上述の未曾有大マンダラそのものでもなく、また大マンダラの中の「塔中の妙法蓮華経」でもなく、「地涌千界を召して、八品を説いて」妙法蓮華経を付属されている久遠の本仏お釈迦さまに外ならないのです。
従って、大マンダラ仏界の様相を叙述された後をうけて、
正像二千年の間は、小乗の釈尊は、迦葉・阿難を脇士となし、権大乗ならびに涅槃・法華経の迹門等の釈尊は、文殊・普賢等をもって脇士となす。
これ等の仏をば正像に造り画けども、今だ寿量の仏ましまさず。末法に来入して、始めて、この仏像、出現せしむべきか。
と仰せられているわけです。
勿論、ここにいう「「寿量の仏」とは、右の文章の後をうけて、
問う、正像二千余年の間は、四依の菩薩ならびに人師等、余仏、小乗・権大乗・爾前・迹門の釈尊等の寺塔を建立すれども、本門寿量品の本尊ならびに四大菩薩をば、三国の王臣ともに未だこれを崇重せざる由これを申す。
このこと、ほぼこれを聞くといえども、前代未聞の故に、耳目を驚動し、心意を迷惑す。請う、重ねてこれを説け、委細にこれを聞かん。
と述べられているところの上行・無辺行・浄行・安立行という本化の上首四大菩薩を脇士とする本門寿量品の本尊、久遠実成の本仏お釈迦さまのことであり、山川博士も同著(四七一頁)に、
本門寿量品の本尊(たる釈尊)並びに(その脇士たる)四大菩薩
と説明されているところです。
そして、右の文章の問いに答えたのが、この文に続く四種三段(或は別称五重三段)の項であり、四種三段の展開によって本法三段正宗分の「寿量」の動的仏界が打ち出されたのですから、この寿量仏界の実在こそ、「耳目を驚動し、心意を迷惑す」という正像二千年間、前代未聞の「一尊四士」本尊様式の出処を明らかにしたものであった、と申されましょう。
ここに本法三段正宗分の「寿量」とは、決して三秘総在の一秘の妙法五字ではなく、寿量品に顕現された久遠の本仏お釈迦さまを本尊とし、この本尊を中心として本化地涌の菩薩が脇士となって囲繞し、本仏お釈迦さまの久遠の因行果徳の二法である妙法五字を父子一体となって唱えあい、実践している宇宙大の躍動する久遠の仏界であったということが、改めて確認されるのです。
ところで観心本尊抄には、本法三段正宗分の「寿量」という外に、先に掲げた「寿量の仏」という用語と、「寿量の法門」という用語が挙げられています。「寿量」と「寿量の仏」については、これまで述べて来た通りですから、次に「寿量の法門」ということについて考えてみましょう。
この用語は、観心本尊抄の中の「末法為正」を論ずる段に用いられているものです。
また弥勒菩薩、疑請して云く、
経に云く、我等はまた、仏の随宜の所説、仏の所出の言、未だ曽って虚妄ならずと信じ、仏の知しめす所は、皆悉く通達すといえども、然も、諸の新発意の菩薩、仏の滅後において、若しこの語を聞かば、或は信受せずして而も法を破する罪業の因縁を起さん。
ただ願わくは世尊、願わくは為に解説して、我等が疑いを除きたまえ。及び未来世の諸の善男子、この事を聞きおわって、また疑いを生ぜじ、等云々。
文の意は、寿量の法門は、滅後のために、これを請するなり。
ここにいう弥勒の疑請というのは、いうまでもなく従地涌出品の後半において、娑婆大地の内から涌出した地涌の菩薩が、あたかも百才の翁の如くであるのに対して、二十五才の青年の如きお釈迦さまが、地涌の菩薩を、悉く我が子なりといわれ、地涌の菩薩も、青年の如きお釈迦さまを我が父と仰いだということに対する疑いであり、新発意の菩薩は、この疑惑のために、この事実を信ずることが出来ずに破法罪業の因縁を作ってしまう恐れがあるから、その疑いを晴らして頂きたい。そうすれば未来世の人々も、お釈迦さまと地涌の菩薩との父子の関係について疑いを起こさないでありましょう、とお願いしているのです。
そこで、この「文の意は、寿量の法門は、滅後のために、これを請するなり」と仰せられているわけですが、山川博士は「寿量の法門」の語を同著(五二二頁)に、
寿量(の本仏開顕)の法門
と註釈し、またこの御文章に 段をつけて
段をつけて
涌出品(正宗分)弥勒の請を挙げて、寿量品は滅後のためなるを證す
と述べてしまっているのです。
なるほど「寿量の法門は、滅後のために、これを請するなり」の文につづいて「寿量品に云く」と書き出され、寿量品の中の本心を失える者、本心を失わざる者の説明があり、更に、寿量品の中の「遺使還告」「是好良薬」の文についても、
地涌千界は、末法の始めに必ず出現すべし。今の遺使還告は地涌なり。是好良薬は、寿量品の肝心たる名体宗用教の南無妙法蓮華経これなり。この良薬をば、仏なお迹化に授与したまわず。如何に況んや他方をや。
と説明されているのですから、「寿量の法門」とは、いかにも寿量品のことであるようであり、また地涌の菩薩に対するならば「寿量(の本仏開顕)の法門」でもあるように思われもしましょう。
然しながら、若しそうであるならば、敢えて「寿量の法門」という表現を用いずに、端的に「寿量品」といい、或は「寿量の仏」と仰せられて然るべきでありましょう。それにもかかわらず「寿量の法門」と表現されたのには、それだけの意味があったと考えねばなりません。では、それはどういう意味であったのでしょう。
ここに今、本法三段正宗分の「寿量」の二字が、久遠の本仏お釈迦さまと、久遠の本弟子地涌の菩薩とが、久遠の本法妙法五字の実践によって因果不二、父子一体となっている動的仏界を中心核とし、法界全体のすべてを包摂して通一仏土となっている世界そのものを現していることと思いあわせた時、「寿量の法門」とは、その中心核の動的仏界における本門寿量の三宝の義をさすものということが出来ましょう。
すると、山川博士のいう「寿量の本仏開顕の法門」というのは、「寿量の法門」の中の一部に触れたものにすぎなくなり、また山川博士のいう「寿量品」の文に限定されたものでもないということになるわけです。
繰りかえしていうならば、「寿量」とは本仏・本法・本化という久遠の三宝不二一体なる躍動の世界そのものをいい、「寿量品」とは文字として示した経であるということです。
これを五種の妙行に配するならば、
寿量──────────受持行
寿量の法門───────解説行
寿量品─────────読誦行(並びに書写行)
とも申されましょう。
勿論、文上寿量品の経文の奥に、文底寿量の法門があり、更にその奥に動的寿量仏界があるというのではありません。本来、この三者は相即不二のものなのです。ところがそれを見落とす処に底上相対、教観相対というゆがめられた法門が起きて来ているのです。
大聖人が「四信五品抄」に、
妙法蓮華経の五字は、経文に非ず、その義に非ず、ただ一部の心のみ。
と仰せられたのは、文上の教相にとらわれ、或は文底の秘義にこだわっていることを誡めて、この妙法蓮華経の五字こそ、寿量仏界における本仏お釈迦さまの久遠の因行・久遠の果徳の二法不二なるものであり、現に本仏お釈迦さまと本化地涌の菩薩によって久遠劫来、瞬時も絶え間なく唱えられ、実践されているものである、ということを示されたものであったのです。
建長五年の朝より弘安五年の夕に至るまで大聖人の一代忍難慈勝の法華弘通は、末法万年の一切衆生をして、この寿量仏界に入らしめることでした。私たちの日常の安住もこの寿量仏界の外はありません。生存の戦いの激化し、人間社会の顛倒狂乱する今日、三宝御宝前に端座し、霊山虚空会上、本門八品の儀相を整え、神力付嘱の題目を唱え奉るほどの法楽はありません。
そしてこの無上の法悦の中から、顛倒狂乱している世の人々にむかって、常不軽菩薩の行軌にならい、妙法五字を受持宣布し、下種結縁を成就して行かねばならないのです。
常不軽菩薩の礼拝授記行については、常不軽菩薩品の中に、
しかも、この比丘、専ら経典を読誦せず、ただ礼拝を行ず。
と述べられていますが、それは経典の読誦が出来なかったのでもなく、経典読誦自体を否定したものでもなく、或は法門の解説を否定したものでもなく、当時の小乗教徒や大乗教徒の殆どすべての人々が、専ら経典の読誦・法門の解説をこととし、それに通達することによって、生仏不二なる絶対境に入ろうとめざしていたのに対して、常不軽菩薩は、経典の読誦・解説を正覚への段階とはせず、久遠の本仏(当時では威音王如来)の慈悲神通大本願力に乗じて、一挙に久遠の仏界、本因本果不二なる動的寿量仏界に入ると共に、一切衆生をも一挙にこの仏界へ導入せしめんとして、同じく読誦・解説を修行の段階とせず、ただひたすらに寿量仏界より直接発起して来る礼拝行・授記行を行じてやまなかった、ということなのです。
常不軽菩薩が、行きあう人ごとに礼拝授記した言葉は、
我深敬汝等 不敢軽慢 所以者何 汝等皆行菩薩道 当得作仏
我れ深く汝等を敬う、敢えて軽慢せず。所以はいかん、汝等みな菩薩の道を行じて、当に作仏することを得べし。
というのですが、この漢文二十四字と妙法五字とを対照された大聖人が、
「彼の二十四字と、この五字とは、その語ことなりといえども、その意これ同じ」
と仰せられたのも、二十四字と五字とが共に、本仏の因行果徳の二法として寿量仏界より流出したものであったからです。
即ち、この二十四字の表面は本仏久遠の因行をあらわしながらも、その裏面に作仏を保証する本仏久遠の果徳が、厳然として相即しているものであり、作仏とは始覚を成就することでなく、衆生本来内具する「五百塵点、乃至所顕の三身にして無始の古仏」を顕発するものであったのです。
ここに、常不軽菩薩が如来使として礼拝因行を修しながらも、観心本尊抄に、
不軽菩薩は、所見の人において仏身を見る。
ということが出来たのです。
「所見の人」とは、出あうすべての人々ということであって、それらの人々に仏身を見るというのは、その人の現身に仏身を見たというのでもなく、内具の仏性を見たというのでもありません。山川博士は同著(三二〇頁)に次のように述べています。
「不軽菩薩ハ所見ノ人ニ於テ仏身ヲ見ル」と、謗法上慢の者を仏身と見るという。天台が仏性といい、本化が仏身といわれる。この立脚地の相違を軽々に看過してはならぬ、とはこれまた師説である。
ここにいう「師説」とは、山川博士の恩師である田中智学氏の説のことですが、その説にしても「立脚地の相違」を指摘されただけのことであって、所見の人の現身をそのまま仏身と見たというのか、それとも所見の人に内具する仏身を見たというのか、或はその仏身が久遠の本仏の仏身と同一のものなのかどうか、ということについては判然とされておらず、また不敬菩薩が所見の人に、どうして仏身を見ることが出来たのか、ということについても触れてはいません。
これについては私は、いうまでもなく仏身とは衆生内具の仏身であり、しかもそれは久遠の本仏お釈迦さまと全く同一の仏身であると確信しているものですが、では、どうして不軽菩薩がそういう見方をすることが出来たのかというならば、不軽菩薩自身、常に寿量仏界に住し、久遠実成の本仏威音王如来に面奉しており、その本仏が娑婆世界の一切衆生を悉く吾が子としていつくしみ、みずから衆生の心田に仏種を下し、若し衆生が仏種の一仏乗を信受し、本化の菩薩道を行じて退転することがなければ、必ず本仏と全く同一なる仏身を顕現し成就することが出来る、と本願し約束されていたことを堅く確信していたからである、と申せましょう。
衆生が久遠の本仏と全く同体の仏身を顕現し成就するのであるならば、顕現し成就した仏身は、今、始めて成就した始覚の仏ではなく、久遠実成の仏でなければなりません。ここに大聖人もまた観心本尊抄に、
我等が己身の釈尊は、五百塵点、乃至所顕の三身にして無始の古仏なり。
と仰せられている所以があるのです。
お釈迦さまは方便品に、
我れ、本(もと)誓願を立てたり。一切の衆をして、我が如く等しくして異なることなからしめんと欲しき。
と、久遠の大本願を示されています。「我が如く等しくして異なることなからしめん」とは、久遠の本仏と全く同一の仏身を成就するということです。お釈迦さまのこの大本願は、無始以来の無量無辺なる過去仏の一人一人の成道という先蹤、並びにお釈迦さまみずからの成道体験にもとずいて、一切衆生に久遠の本仏と同体なる仏身の内在していることが裏付けられていたことによる、と申されましょう。
如来を信ずるとは、如来の本願を信ずることであり、如来の本願を信ずるとは、如来が衆生本具の仏身を信じているように、みずから如来と同じ仏身の本具していることを信ずることでなければなりません。
では、本具の仏身を顕現するには、どうすればよいのか、というならば、お釈迦さまが方便品に、
仏種は縁によって起こると知ろしめす。この故に一乗を説きたまわん。
と示されているように、お釈迦さまの説かれた一仏乗を如法に受持信行する外はありません。
この場合、一仏乗そのもの本仏の因行果徳が自然に衆生の心身に譲与されることによって、それがそのまま仏種となるのですが、本具の仏身をさしおいて、その仏種の種から芽が出、花が咲き、そして仏果の実をみのらせるのではないのです。
また或は、一仏乗を持つことによって、久遠の本仏より因行果徳の功徳が次第次第に譲り譲られ、すべての功徳を悉く譲り与えられることによって、本仏と同体の仏身が育成され完成されるのでもないのです。
若し、そのようであったならば、成就された仏身は、なお始覚の仏にすぎないものであって、本仏と同体の久遠実成の仏とはいわれないでありましょう。
たしかに一乗仏種とは、方便品に、
十方仏土の中には、ただ一乗の法のみありて、二もなく、また三もなし。
と仰せられているように、唯一無上の仏種なのですが、この仏種によって生まれるのは実は本化の菩薩なのです。そして本化の菩薩がひたすらに一仏乗を行じ、その行を成就するやいなや、本具する久遠の仏身が忽然として顕現し、菩薩の心身がそのまま仏身化するのです。
妙法五字の仏種から、直接、仏身が生まれるのではありません。生まれるのは父なる本仏の仏身に即する仏子としての本化の菩薩であり、しかもその菩薩も、今はじめて菩薩となったものでなく、久遠劫来、本仏によって教化されて来た偉大なる仏子であったことはいうまでもありません。
観心本尊抄には、つぎのようの示されています。
譬えば、王女たりといえども、畜種を懐妊すれば、その子、なお旃陀羅に劣るが如し。
ここでは、下種される種と質と、生まれる子供の質が問題とされており、また開目抄にも、これと同様のことが次のように激しい口調で語られています。
今、久遠実成あらわれぬれば、東方薬師如来の日光・月光・西方阿弥陀如来の観音・勢至、乃至十方世界の諸仏の御弟子、大日・金剛頂等の両部の大日如来の御弟子の諸大菩薩、なお教主釈尊の御弟子なり。
諸仏、釈迦如来の分身たる上は、諸仏の所化申すにおよばず、いかに況んや此の土の劫初よりこのかたの日月衆星等、教主釈尊の御弟子にあらずや。
しかるを天台宗より外の諸宗、本尊にまどえり、倶舎・成実・律宗は三十四心断結成道の釈尊を本尊とせり。天尊の太子、迷惑して我が身は民の子と思うが如し。
華厳宗・真言宗・三論宗・法相宗等の四宗は、大乗の宗なり。法相・三論は勝応身に似たる仏を本尊とす。天王の太子、我が父は侍と思うが如し。
華厳宗・真言宗は釈尊を下して廬舎那・大日等を本尊と定む。天子たる父を下して、種姓もなき者、法王の如くなるにつけり。
浄土宗は、釈迦の分身の阿弥陀仏を有縁の仏と思いて、教主を捨てたり。
禅宗は、下賎の者、一分の徳ありて父母を下ぐるが如し。 仏を下げ、経を下す。これ皆、本尊に迷えり。例せば、三皇已前に父を知らず、人みな禽獣に同せしが如し。
寿量品を知らざる諸宗の者は、畜に同じ、不知恩の者なり。故に妙楽の云く、
「一代経の中、未だ曽って遠を顕わさず。父母の寿、知らざるべからず。若し、父の寿の遠を知らずんば、また父統の邦に迷う。徒らに才能というとも全く人の子に非ず」等云々。
妙楽大師は唐の末、天宝年中の者なり。三論・華厳・法相・真言等の諸宗、並に依経を深く見、広く勘えて、寿量品の仏を知らざる者は、父統の邦に迷える才能ある畜生、と書けるなり。
ここでは、仏と衆生との師弟の関係を、父と子、君主と太子の関係にとらえて、仏種の正統的系譜を論じ、寿量品の本仏お釈迦さまを我が父と知らない者は、禽獣・畜生・不知恩の者と厳しく批難されているのですが、この主論の中に、寿量品の久遠の本仏お釈迦さまを一切衆生の父とし、父の種子である妙法五字を仏種として、本化の菩薩が父の子、本仏の仏子として生まれるものであるという思想の歴然としていることを知ることが出来るのです。
ここに本尊と題目の重大さがあります。若し、父をあやまり、仏種をあやまるならば、持つ経典は如何に殊勝であっても、たとえ法華経であっても、生まれた子供は父の嫡子、本仏の嗣法の仏子、本化の菩薩ではありえないのです。
これに対して、
「たとえ貧女といえども王種をうくれば、その子は太子たるべし」
という大聖人の言葉もある通り、一文不知の者であっても、寿量の仏を本尊と仰ぎ、仏種の題目を如法にたもつ者は、本化の菩薩として新生する、ということも出来るのです。
最近の日蓮宗教学では、観心本尊抄に、
釈尊の因行果徳の二法は、妙法蓮華経の五字に具足す。我等、この五字を受持すれば、自然に彼の因果の功徳を譲り与えたもう。……(中略)……妙覚の釈尊は我等が血肉なり。因果の功徳は骨髄にあらずや。
と仰せられている受持譲与を盛んに強調されているようですが、財産譲渡をうける「もらい根性」ばかりが強くなり、題目を受持しておれば、何時かは成仏するであろうという怯懦な安心感がかもし出され、厳しい常不軽菩薩道の実践はおろか、衆生本具の仏身顕現に対する究極の悲願も忘れ、教学上でも功徳譲与と仏身顕現との関係が漠然とされてしまっている状態です。
その反面、宗門全体には古くから本具の仏性を開顕するという迹理にもとずく信行論が潜在しており、中には題目によって八識九品の無明を断破して、九識心王真如の都を顕発しようとする苛烈な信行の動きもあるようですが、所詮、禅的発想、或は修験道的発想よりでるものではありません。
宗学は信行実践を勧発するものであり、宗学の混迷は、そのまま信行実践の混乱をまねくものです。今日、日蓮宗大荒行堂や身延山における信行道場における混乱と堕落、或は統一信行と称する唱題行の幼稚さ、それらはすべて宗学の混迷に帰因していると申せましょう。
ここに日蓮宗教学は原点に立ち帰り、本法三段正宗分の「寿量」仏界を再検討し、その流通分とは、寿量仏界を今日娑婆世界に復活再現するものであるという認識に立って、本化地涌の菩薩道の亀鑑となった常不軽菩薩道の意義を究明しなければならないと思うのです。
今日、日蓮宗教学の癌となっているものの中に、文上文底を云々する底上相対思想と、三秘総在の一秘を標榜する一秘即三秘の思想とをあげることが出来ましょう。この二つの思想は互いに関連性をもっているものですが、既に前述のように「日蓮辞典」の中の「文上文底」の項においては、その相対的見方が否定され、教観一体観が打ち出されてはいるのですが、十九名の執筆者による同辞典の中には、なお各処に文底思想が散見されているようです。こういうことでは日蓮宗教学の混迷を払拭することは容易なことではないといわざるをえません。
特に、癌になっているのは三秘総在の一秘思想であり、田中智学氏や山川智応博士をはじめとして、この思想が鼓吹され、立正大学の望月歓厚博士もその著「日蓮教学の研究」の中で、一秘と三秘の関係を、宗門先師の論功に徹しながら体系化に苦心されたようにうかがわれるのですが、それは全く無駄なことであり、苦心するならば、この思想が大聖人のものでなく、むしろ大聖人の教学をあやまらしめた元凶として、これを破折払拭することでなければならなかった、と思われるのです。
これを破折し払拭し去らない限り、弊害は本尊問題にも及び、たとえば大聖人図顕の大マンダラ中央の題目を三秘総在の一秘とみなし、このため二仏並座の釈迦・多宝は境智の二法を象徴するものと化され、更に応身迹仏に転落せしめられてしまって、寿量品の久遠開顕の本旨にもそむいてしまう結果となるのです。
では、三秘総在の一秘という思想は、何を根拠として起きて来たのかと尋ねるならば、学者によっては、妙法五字は、名・体・宗・用・教の五重玄義を具足しているという処から、五重玄義の第二の「体玄義」を本仏の仏身とみなすという説もあり、また或は神力別付嘱の法体は妙法五字であり、この五字から三秘が開出されるという説もあるようです。
然し、体玄義とは本仏の仏身ではなく、妙法五字の是好良薬としての体であり、因行果徳の実体なのです。また神力別付嘱においては、付嘱される妙法五字から三秘が開出されて来るのではなく、既に付嘱の当処において、妙法五字を地涌の菩薩に付嘱される本仏お釈迦さまがおられるのであり、このお釈迦さまが本門の本尊なのです。
戒壇にしても妙法五字から開出されるのでなく、既に本門八品の虚空会上に現成しているのです。娑婆世界に地涌の菩薩が建立する本門の戒壇は、一閻浮提統一の戒壇であれ、国ごとに建立される国立戒壇であれ、或は在々処々、行者所住の処に造立される戒壇であれ、本門八品の儀相を再現するものでなければなりません。
「日蓮辞典」(九〇頁)には、一秘と三秘の関係を次のように説明しています。それは「三大秘法」という項の中で、特に「一大秘法との関係」と題して述べているものです。
「法華取要抄」には、
「一閻浮提、みな謗法となりおわんぬ。逆縁のためには、ただ妙法蓮華経の五字に限るのみ。例せば不軽品の如し」(定八一六頁)
と述べている。
日本国の衆生は、おしなべて仏法に違背している謗法の衆生であり、仏の慈愛に対して逆縁のものである。そのような悪国時の仏の教化については、法華経常不軽菩薩品第二十に示されているところである。
日蓮が、このような目標によって折伏逆化の教化を押し進めた結果、日蓮に帰依する門弟(一門)が形成され、日蓮自身が上行菩薩の応現たる使命を果たすため、末法万年の法華経信受の要諦を明示する必要に迫られた結果、三大秘法が発表されたものと見られる。
すなわち、
「問うて云く、如来滅後二千余年に竜樹・天親・天台・伝教の残したまえる所の秘法とは何物ぞや。
答えて云く、本門の本尊と戒壇と題目の五字となり」(定八一五頁)
と三大秘法をあげて前掲の文に至り、次いで、
「我が弟子は順縁、日本国は逆縁なり」(定八一六頁)
と述べることは、一大秘法と三大秘法は、末代衆生救済の教法としては同じであるが、三大秘法は、一大秘法に目覚めた者が、更に信行をたかめ、末代の教法のあかしとして、そのはたらきを確固なものにするための役割を持つことが分かるのである。
これによれば、一大秘法と三大秘法とは「教法としては同じである」が、一大秘法は逆縁の者のため、三大秘法は順縁の者のために設けられたものであるとされています。
然し、それは本質論と方法論の混同でしかありません。解説者は、同辞典の「三大秘法」の項の中、「本門の題目」と題して、また次のように述べています。
竜口法難以後、上行自覚が発表されて、 上行所伝の結要付嘱の法であり、末代幼稚の者に授与されていることが説かれるとともに、
上行所伝の結要付嘱の法であり、末代幼稚の者に授与されていることが説かれるとともに、 五重玄具足の妙法蓮華経の意義、
五重玄具足の妙法蓮華経の意義、 本因本果具足の法であり、一念三千と表裏一体の法たること等が明らかにされ、これが三大秘法の一として説かれるとともに、一大秘法の意義が明示されるに至った。
本因本果具足の法であり、一念三千と表裏一体の法たること等が明らかにされ、これが三大秘法の一として説かれるとともに、一大秘法の意義が明示されるに至った。
解説者は、一大秘法の妙法五字と、三大秘法の中の本門の題目とは同一の法体であり、逆縁の者には題目をもって折伏逆化し、順縁の者には題目の外に本尊と戒壇とを加えることによって三秘を明確にし、その「信行をたかめ、末代の教法のあかしとして、そのはたらきを確固なものにするため「と考えているように見うけられるのですが、若し、そうであるならば、三大秘法の外に、ことさら一大秘法を立てる必要はないわけです。
まして逆縁の者に対する折伏逆化に、本尊や戒壇を宣説しないでよいという道理はありません。逆縁の人々が本尊をあやまり、戒壇に象徴される娑婆本国土観をあやまっているが故に、妙法五字による折伏逆化が展開されるのですから、逆縁に対して一大秘法順縁に対して三大秘法という配当的説明は、正しいものということは出来ません。
注意してみなければならないことは、「三大秘法」の項の説明文の何処にも、一大秘法が本質的に三秘総在の一秘であるという言葉が見当たらないばかりでなく、一大秘法の題目も、三大秘法の中の本門の題目も「教法としては同じである」といい、更には、前掲の如く「 ……
…… ……
…… ……これが三大秘法の一として説かれると共に、一大秘法の意義が明示されるに至った」と述べていることです。
……これが三大秘法の一として説かれると共に、一大秘法の意義が明示されるに至った」と述べていることです。
この辺を思いあわせれば、この解説文を執筆された学者は、これまでの日蓮宗教学上金科玉條の如く固定して浸透し切っている三秘総在の一秘という法門を、心の内では否定しながらも、それを言葉としては言い出す勇気がなく、といって一秘即三秘という構格を、これまでの伝統的解釈にもとずいて説明するわけにもゆかないため、一秘の題目と三秘の中の題目は同一といったり、或は、一秘は対逆縁、三秘は対順縁と言いのがれしているのではないか、という気がしないではありません。
若し、そうであるならば、この説明文は、日蓮宗という小さな教団の枠の中で、自己の所信よりも、自己の学者としての地位を先にしたものにすぎないのではないか、とも申せましょう。
こういう説明文は、却って人々をまどわしてしまう結果を生ずるものです。むしろ小才を弄さず、少なくとも一秘三秘の構格に対して疑問を呈し、陋説を破折すべきであった、と思うのです。
いずれにせよ、この説明文の中からは、三秘総在の一秘という思考が、何を根拠として起きて来たのか、ということは明確にされてはおりません。
ところで山川博士は、その著「観心本尊抄講話」(五四一頁〜五四二頁)に、神力品の結要付嘱を義釈するに当たって、天台大師の法華文句と、妙楽大師の記を引用し、結要付嘱の四句要語と、題目の五重玄義とを配当する図をかかげて、次のように述べています。
義釈
十神力は何故に顕わされたか。それは上行等の地涌の菩薩に、法華経を付嘱せられるためである。その付嘱の時に「如来一切」などの四句をもって付嘱せられたから天台は結要付嘱といわれた。
それが妙法蓮華経の五字であるのだが、それらの釈は、御本文(観心本尊抄の本文)には略されている。即ち、「文句」〔会本二十九〕に、左の如くある文だ。
結要ニ四句アリ。
一切法トハ一切ミナ仏法ナリ。コレ一切ミナ妙ノ名ヲ結スルナリ。
一切力トハ通達無碍八自在ヲ具フ。コレ妙ノ用ヲ結スルナリ。
一切秘蔵トハ一切処ニ シテ皆コレ実相ナルハ コレ妙ノ体ヲ結スルナリ。
シテ皆コレ実相ナルハ コレ妙ノ体ヲ結スルナリ。
一切深事トハ因果ハコレ深事ナリ。コレ妙ノ宗ヲ結スルナリ。
皆於此経宣示顕説トハ総ジテ一経ヲ括ルニ、タダ四ナラクノミ、ソノ枢柄ヲ撮リテ、シカモコレヲ授与ス。
この文には、名と用と体と宗との四句で一結を括りて、その枢柄をとって、これを授与せられたとあるが、文義幽遠で、凡慮では解し難い。そこで妙楽大師が「記」〔同上〕に扶釈して、
結要ニ四句アリトハ、本迹二門ニ各々宗ト用トアリ。二門ノ体ハ両処コトナラズ。名、コノ三〔体・宗・用〕ニ冠シテ、シカモ三ヲ総ブ。一部ノ要、豈コレニ過ギンヤ。故ニ総ジテコレヲトリテ、以テ流通ヲ成ズ。
といわれている。
迹門と本門では、その宗とする所、用とする所は異なるが、迹本二門の体は実相であるからことならない。名というのは、この宗と用と体とに冠って、しかもこれを総べる。(だから)一部の要(四句をくくったそのまた要、即ち枢柄)は、何とコレニ過ぐるものがあろうか。故に(この名の中に)総じて(体宗用の三)をとって、以て流通を成就するようにせられた、というのだ。
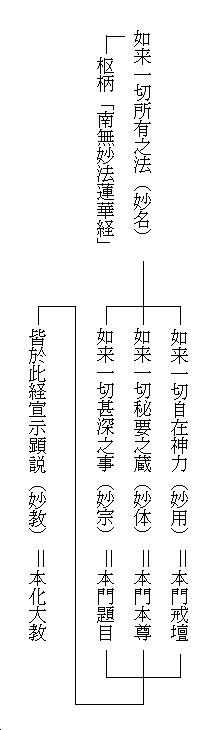
ということになるのである。それだから上に、「寿量品ノ肝心タル名体宗用教ノ南無妙法蓮華経ナリ」とあったのである。
右のように山川博士は、四句要語と五重玄義と一秘三秘とを互いに習合せしめた上で、一大秘法は三秘総在の一秘であり、この一秘より三秘が開出され、三秘は一秘に帰納する、と主張しているものであって、この三者習合図を一見した人々の中には、一秘即三秘という法門が正しいものであるかのように思われる人も少なくはないかも知れません。
然し、この習合図の中より三秘を抜き出してみれば、それは妙楽大師が天台大師の「法華文句」の意をうけて、更に統計的に組織化したものであって、これに三秘を習合せしめたのは山川博士の牽強附会にすぎない、と思わしめられるのです。
若し、妙楽大師が山川博士の習合図を見たならば、むしろ唖然としてしまうのではないでしょうか。何故ならば、四句要語にしても五重玄義にしても、あくまでもそれは教法の範疇より出るものでなく、本尊とか戒壇という事相をも含んだ立場に立っていたのではなかった、と思われるからです。
たとえば天台大師は、
「一切秘蔵とは、一切処に して、皆これ実相なるは、これ妙の体を結するなり」
して、皆これ実相なるは、これ妙の体を結するなり」
といい、妙楽大師は、
「(本迹)二門の体は、両処異ならず」
と説明しているように、迹門の諸法実相は、そのまま本門の諸法実相であり、本迹二門に一貫するその実相こそ、五重玄義の中の体玄義である、と述べているにすぎないのです。
もとより天台教学における実相観は、迹面本裏、凡夫の陰妄の一念に立っていたものであって、開目抄に、
迹門方便品は一念三千・二乗作仏を説いて、爾前二種の失(とが)一つをのがれたり、しかりといえども、未だ発迹顕本せざれば、まことの一念三千もあらわれず二乗作仏も定まらず、水中の月を見るが如し、根なし草の波の上に浮かぶるに似たり。
と述べられているように、大聖人における実相観・一念三千観は本仏果上のそれであって、天台とは根本的に違っていたものであったのです。
それにしても、体玄義として結せられている諸法実相・一念三千は、本仏お釈迦さまの正覚の内容をさすものであって、本仏の仏身そのものであったのではありません。
然るに、山川博士の場合「如来一切秘要の蔵」という体玄義が、そのまま「本門の本尊」とみなされるに至ったのは、五百億塵点の仏といえども有始の方便を帯しており、妙法蓮華経こそ無始無終の実体、無作三身の法号であって、お釈迦さまをはじめ三世十方の諸仏といえども、妙法蓮華経を悟ることによって仏となることが出来たのであるから、妙法蓮華経こそ本仏であり、本尊である、という法本尊観をいだいていたからである、と申されましょう。
更に、これをつきつめてみるならば、本法三段正宗分の「寿量」の二字を、「寿量品の肝心たる名体宗用教の南無妙法蓮華経」と解釈してしまった処に、誤謬の源を発していたということが出来るのです。
本来、本法三段正宗分の「寿量」とは、本門三段正宗分一品二半に顕現されている久遠の本仏お釈迦さまと、久遠の本法題目と、久遠の本化地涌の菩薩との本門の三秘相即する動的仏界であり、三千塵点劫の大通智勝仏以来の一切の経々を序分とし、その動的仏界を末法万年の娑婆世界の復活再現することを流通分とするものでした。
然るに、田中智学氏・山川博士をはじめとして日蓮門下の殆どの教学者が、「寿量」の二字を文底の教と推量し、「内証の寿量品」の字に当てたり、更に「寿量品の肝心たる名体宗用教の南無妙法蓮華経」の字に当ててしまった結果、必然、その題目を三秘総在の一大秘法とみなしてしまい、神力別付嘱の法も一大秘法に当てて、一大秘法を実現する処に、その一大秘法より三大秘法が開出される、と錯覚してしまったのです。
この錯覚は、更に大聖人図顕の大マンダラ解釈にも及び、大マンダラ中央の題目を三秘総在の一大秘法とみなしたため、二仏並座の釈迦・多宝は境智の二法に当てられてしまい、遂には方便迹仏に転落せしめられ、五百億塵点劫来の寿量品のお釈迦さまも、有始始成の仏、方便を帯する迹仏応身とみなされ、寿量品の久遠開顕の真意すら、再び隠没してしまっているのです。
三秘総在の一大秘法、一秘即三秘という観念は、本法三段正宗分「寿量」の二字を読み違えた処に起こった妄説にすぎないのです。しかもそれは、妙楽大師が五重玄義を体系化して、
名、この三〔体・宗・用〕に冠して、しかも三を総ぶ。一部の要、豈にこれに過ぎんや。故に総じてこれをとりて、以て流通を成す。
と述べていたことを本とし、その中の体・宗・用の三重玄を、本尊・題目・戒壇の三秘に置き替えた小細工にすぎなかったのです。
この幼稚な小細工から、三秘総在の一大秘法という妄説が、金科玉條の如く宗門教学に定着し、一大秘法は本法三段正宗分の文底の秘法、三大秘法は一大秘法より開出された流通分の施設と化されたことは、まさに悲しむべき推移というほかはありません。
これまでの日蓮門下教学者の殆どは、三秘総在の一秘・一秘即三秘という考えを、大聖人によって開顕された本化教学の一大特色と鵜呑みして、その普遍的解釈に努力してきました。然し、その結果、題目を仏種として下種された父なる本仏お釈迦さまの絶対的存在を見失い、「父統の邦」を迷い出てしまったのです。「父統の邦」をさまよい出たものに、本門の本尊の建てられるはずもなく、また本門の戒壇の建立されるはずもありません。
一秘より三秘が開出されるという思考のもとでは、仏種を下す父なる本仏お釈迦さまを本尊として立てようもないのです。神力品における法華経の別付嘱段にしても、付嘱された一秘から三秘が開出されるというならば、開出された三秘の中の本門の本尊と、初めに法華経を付嘱された本仏お釈迦さまとの同異が問題となりましょう。若し、同じ仏であるというならば、一秘から三秘の開出される以前、既に一秘付嘱の当処において三秘は顕現しているということになり、一秘即三秘という観念は、全く不必要な空廻り観念という外はありません。
三秘総在の一秘思想、それは本法三段(文底三段、或は法界三段)正宗分の「寿量」の意味する処を取り違えたことに発しているようですが、こうした取り違え、錯覚の起こったのも、一面、ふりかえってみれば、無理からぬものがあったとも申されましょう。
四種三段(或は五重三段ともいう)は、一代三段の広から、本門三段の略へと詮じつめて来ました。そして本門三段正宗分が一品二半と結したならば、次に大通智勝仏の法華経をはじめ十方微塵の経々をはじめ今番法華迹門十四品、並びに涅槃経等までも悉く、「寿量」の序分という以上、日蓮門下の者ならば、勢い、「寿量」そのものを妙法蓮華経五字と解釈し勝ちなことと思われましょう。
まして大聖人図顕の大マンダラの中央には題目が大書されており、
総じては、如来とは一切衆生なり。別しては日蓮の弟子檀那なり。されば無作の三身とは、末法の法華経の行者なり。無作の三身の法号を南無妙法蓮華経というなり。寿量品の三大事とはこれなり。
といった「御義口伝」などの理本覚思想を鼓吹した一連の偽作遺文までが、大聖人の真蹟遺文と肩をならべて尊重されている以上、偽書を偽書として見破ることの出来ない人々が、「寿量」を妙法五字、三秘総在の一大秘法、寿量文底の題目とみなしてしまうのも、無理からぬものと思われもするのです。
そういう人々に「寿量」の真意が理解されるには、まず偽書が偽書であることを論証することから始めなければならないでしょうが、この論証作業は容易なことではありません。
まず第一に、そうした一連の偽作遺文には、一つとして大聖人直筆の原本が現存していないのです。原本があるならば、その筆跡や紙質等によって真偽の鑑定も出来ましょう。ところが、あれほど多くの偽書とみなされるものに一つとして原本がないというのは、一体、どうしたわけでしょう。偽作に関連した人々が、真偽の鑑定を恐れて、原本を残さなかったとも考えられましょうか。
いずれにせよ、原本の鑑定が出来ない以上、真蹟遺文と偽作遺文との思想的矛盾対立を指摘し、真蹟思想と水火あい容れないものは偽書、或は偽書に類するものとして、一往、棚あげにし、真蹟思想を中心として大聖人の教義の大綱を決しなければなりません。
私の立正大学時代には、浅井要麟教授は「祖書学」と題して、御遺文の真偽問題を講じていました。今の大学には祖書学を継承する講師もなく、真っ向から御遺文の真偽を論ずる宗学者もおりません。
いな、今や宗門には宗学を専攻する学者も学徒も乏しく、末法法滅尽の様相は、宗門学者畠の中にも顕著に呈して来ているのです。
そして殆どの人々は、伝統宗学の温床の中で、真蹟思想と偽作思想を併用し、両者の会通、調和を計ることを主として、大聖人の真実の教学を顕彰することすら怠っている状態なのです。
こういうことでは、御遺文集の中に竄入している偽書を、偽書として論証する作業はいよいよ困難であるといわねばなりませんが、このままでは本尊も題目も戒壇も定まらず、人間成仏も国土成仏も定まらない、ということになってしまいましょう。
現在、宗門の若い学究者の殆どは、大聖人の教学を明確にすることを敢えて避け、大聖人滅後七百年間の宗門教学史を専攻しているようですが、宗門先師の教学を探究整備するならば、その功罪をも明らかにし、誤りがあるならば、仮借なく糾弾しなければなりません。
それを怠って、未発掘のものを発掘することによって、自己の学的地位の栄達を計るようであっては、広宣流布の悲願も地に堕ちたという外はありません。私は、一秘即三秘という法門を創設したのは、多分、一妙日導上人あたりではないか、と推定しているのですが、たとえ彼でなくても、日蓮門下の学匠が提唱したものであったことが明らかにされるならば、一秘三秘は大聖人の法門でないという立場から、それを徹底的に破折することが出来るのです。
そのことによって、大マンダラに対する解釈も根本的に変わって来ることでしょう。まず第一に、大マンダラ中央の題目は、三秘総在の一秘ではなく、三秘の中の題目であり、これを仏種として付嘱されている父なる佛は、二仏並座のお釈迦さまであり、この教主お釈迦さまこそ久遠実成の本仏である、ということが鮮明にされるのです。
但し、大マンダラ全体が本尊であるのではありません。大マンダラ中央の題目が本尊であるのでもありません。二仏並座の久遠の本仏お釈迦さまが本門の本尊であり、私たちは本門八品の儀相である大マンダラの内に入って題目を唱え、法華経を実践するのです。
「日蓮辞典」(一六七頁)に「塔中」という語を次のように説明しています。
日蓮は「観心本尊抄」に、
「その本尊の体たらく、本師の娑婆の上に宝塔空に居し、塔中の妙法蓮華経の左右に釈迦牟尼仏・多宝仏・釈尊の脇仕上行等の四菩薩。文殊・弥勒等の、四菩薩は眷属として末座に居し、迹化・他方の大小の諸菩薩は万民の大地に処して雲閣月卿を見るが如し。十方の諸仏は大地の上に処したもう。迹仏迹土を表するが故なり。」
と述べ、本門八品における妙法付嘱の体相をもって、南無妙法蓮華経の本尊としている。
この場合、「塔中」とは付嘱の儀相に約して表記されたもので、単なる塔内を意味するものではない。多宝如来は久遠釈尊の分身として位置づけられ、釈尊の本因本果は妙法五字に具足されるゆえに、二仏並座の塔中は妙法蓮華経の五字そのものであるといえる。
塔中に能説の仏と所説の教を示し、次下に「釈尊の脇士は……」と表記するのもこの意にほかならない。
右の中、観心本尊抄の原文は、漢文体なのですが、それは、
塔中の妙法蓮華経の左右に釈迦牟尼仏・多宝仏。釈尊の脇士は上行等の四菩薩。文殊・弥勒等は四菩薩の眷属として末座に居し……
と読み下さねばなりません。説明文での読み下し方は間違っているのです。
次に、右説明文の中で全く理解に苦しむ表現は、
本門八品における妙法付嘱の体相をもって、南無妙法蓮華経の本尊としている。
という言い廻し方です。
このような表現では、本門八品の儀相全体が本尊なのか、八品中の神力品における妙法別付嘱の体相全体が本尊なのか、それとも本門八品の儀相を整えた別付嘱段における題目が本尊なのか、全く要領を得ないものです。
おそらく「その本尊の体たらく」という言葉にひっかかり、大マンダラをもって本尊としているのでありましょう。そして大マンダラの中でも、中央の題目をもって本尊の実体とみなしているのではないかと思わしめられることは、「塔中」の二字を「妙法蓮華経の五字そのもの」と解釈し、その「塔中に能説の仏と、所説の教を示し、次下に釈尊の脇士は……」と述べている処から、
妙法五字こそ三秘総在の一大秘法である観念が潜在しているように思われるからです。
この「塔中」の語を解説された学者は誰なのか、もとより知る由もありませんが、
「塔中」とは付嘱の儀相に約して表記されたもので、単なる塔内を意味するものではない。
といい、或は、
二仏並座の塔中は、妙法蓮華経の五字そのものであるといえる。
と述べていることは、一見、斬新な解釈のように見うけられるようですが、実は、伝統的な一塔両尊四士本尊形体を、別付嘱の時点において正統づけようとしているにすぎないのです。
種明かしをすれば、斬新的な思惟と思わしめられる「塔中即妙法」というのは、偽書中の偽書ともいえる「阿仏房御書」の中に既に述べられているのです。
末法に入って法華経をたもつ男女の姿より外には宝塔なきなり。若し、しからば貴賎上下をえらばず南無妙法蓮華経と唱うる者は、我が身宝塔にして、我が身また多宝如来なり。
妙法蓮華経より外に宝塔なきなり。法華経の題目、宝塔なり。宝塔また南無妙法蓮華経なり。
今、阿仏上人の一身は地水火風空の五大なり。この五大は題目の五字なり。しからば阿仏房さながら宝塔、宝塔さながら阿仏房。これより外の才覚無益なり。聞信戒定進捨慚の七宝をもって飾りたる宝塔なり。
多宝如来の宝塔を供養したもうかと思えば、さにては候わず、我が身を供養したもう。我が身また三身即一の本覚の如来なり。かく信じたまいて南無妙法蓮華経と唱えたまえ。ここさながら宝塔の住処なり。
おそらく、この解説者は、右の阿仏房御書の中の「題目即宝塔」「宝塔即題目」という言葉から「塔中即妙法」ということを言い出し、更に塔中において二仏並座したお釈迦さまと多宝如来を、境智の二法に配して来た伝統宗学にもとずいて、お釈迦さまを能説の仏、多宝如来を所説の教と説明したのでありましょう。
このようにみて来るならば、「塔中とは付嘱の儀相に約して表記されたもので、単なる塔内(建造物)を意味するものではない」といった不可解な表現も、彼らしい表現と納得されて来るのです。
然し、多宝塔というものは、本来、無量の過去仏の仏舎利塔を総括象徴したものであり、この塔中、二仏並座することによって、現身のお釈迦さまと、無量の過去仏を総括象徴した多宝如来との不二なることを通して、お釈迦さまの久遠実成を実証する方便施設であって、「宝塔即題目」「題目即宝塔」という義をもつものではないのです。
考えようによっては、無量の過去仏はそれぞれに久遠の本仏として、滅後といえども塔中常説法教化され、地涌の菩薩に法華経を付嘱して来られたのですから、宝塔の中には妙法五字の付嘱の題目が充満している、と見ることも出来ましょう。
仏舎利塔は、単なる物質的建造物ではなく、如来の仏身そのものであったという、原始仏教々団の見方を思い起こすことも出来ましょう。そしてそこから、宝塔が如来の仏身を象徴しているならば、如来の魂である妙法五字をも象徴している、と言えなくもありません。
然し、注意しなければならないことは、多宝塔というのは久遠の昔に滅度した多宝如来の仏舎利塔であり、多宝如来に総括象徴された無量の過去仏の仏舎利塔を総括象徴したものであったということです。
そこで、宝塔の内には付嘱の妙法五字が充満しているといい、「宝塔即題目」「題目即宝塔」というには、無始以来の無量の過去仏の一人一人がすべて、それぞれに久遠実成の本仏であり、地涌の菩薩を教化して妙法五字を付嘱してきた仏である、という説を立てなければなりません。
そして更に多宝如来とは、そういう無量の過去仏を総括象徴した仏であり、多宝塔もまた無量の過去仏の仏舎利塔を総括象徴した宝塔である、ということを主張しなければならないのです。
然し、現在の日蓮門下教学者の中で、こういうことを述べた人は一人もおりません。わずかに松本文三郎博士が、その著「真空より妙有へ」の中で、
多宝如来は過去仏を代表するものである。
と述べている、といわれているにすぎません。他の学者は殆ど、単独の過去仏としてとりあつかってしまっている状態です。
代表していることと、象徴していることでは根本的に意義を異にしてしまいます。多宝如来が過去仏を代表したり、或は過去仏の一人としてお釈迦さまと並座したのであれば、その二仏並座の意義は、失われてしまうか、ゆがめられてしまうことでしょう。
多宝如来が無量の過去仏を悉く総括象徴した仏としてお釈迦さまと二仏並座することにより、その仏身の不二を介して、お釈迦さまの久遠実成と、常説法教化の活動が実証され、二仏並座の意義が全うされるのです。
然るに、私の主張している以上のようなことを考えもせず、阿仏房御書や御義口伝の如き一連の理本覚思想を鼓吹した偽作遺文を本として「塔中即題目」を主張することは城者破城、みずから大聖人の教学を内部から、まことしやかにゆがめているという外はありません。
阿仏房御書の内容については以前、さんざんに批判しましたが、要するに真言の五大思想に毒され、法本尊から己身本尊へ転落した邪義にすぎないのです。ところが、こういう邪義が日蓮門下の中で堂々と罷り通っているから驚く外はありません。
今年の何月号であったか記憶に確かではありませんが、月刊誌「大法輪」の誌上、久保田正文博士が、大聖人の教えを述べるに当たって、この阿仏房御書の一節を引用し説明されていました。宗門の最高指導的立場にある人々が、偽作遺文をかかげ、これを説明することによって大聖人の教学を論ずることは、厳につつしむべきことなのです。
また立正大学教授影山堯雄博士は、その著「日蓮宗布教の研究」の中で、
衆生の成仏は、題目の宝塔の内に入ることである。
という意味のことを力説されていました。今その書は身延の釈迦牟尼堂においたまま手許にありませんので、その文章を引用することは出来ませんが、衆生の成仏が宝塔の内に入ることであるという発想は、代表的偽書ともいわれている「日女御前御返事」の中に強調されていたものであったのです。
「日女御前御返事」は、大マンダラ本尊を前提として、大マンダラの儀相を最も詳細に説明されたものとして有名ですが、この大マンダラに対する説明の後、次のように述べられています。
このご本尊も、ただ信心の二字におさまれり。以信得入とはこれなり。日蓮が弟子檀那等、「正直に方便を捨て」「余経の一偈をも受けず」と信ずる故によって、この御本尊の宝塔の中へ入るべきなり。たのもし、たのもし。如何にも後生をたしなみ給うべし。あなかしこ。
これによれば即身成仏・後生成仏の要諦は、妙法五字をたもつことによって大マンダラ本尊の宝塔の中に入ることであるとされていますが、果たして衆生は宝塔の中に入ることが出来るのでしょうか。
曽って私は、見宝塔品における多宝如来の本願として、多宝塔の扉を開いて塔中の多宝如来の仏身を大衆に示さんとするならば、今、法華経を説いている仏(ここではお釈迦さま)の十方分身の諸仏を一人も残さず、悉くその会座に来集せしめねばならないとされていたその意義を明らかにしたことがありました。
その意義とは、既に無量の過去仏がそれぞれに久遠の本仏である以上、多宝塔も従って本仏の塔であるため、その塔を開くには、唯仏与仏の本仏でなければならない処から多宝如来の本願としてお釈迦さまが本仏としての尊容を示現する必要があったということです。即ち、本仏の塔は、本仏によってしか開くことは出来ないということです。
このため、三変土田という宇宙大の大儀相が三度にわたって展開され、これによって来集した十方分身の無量の諸仏は、それぞれに従えて来た眷属を代表する菩薩をお釈迦さまのもとへ御挨拶につかわし、娑婆世界におけるお釈迦さまの化導をねぎらわせると共に、諸仏もみな悉くお釈迦さまによって多宝塔の扉の開かれんことを願っているということを奏上せしめています。
分身の諸仏が多宝塔の開扉をお釈迦さまにお願いしたということは、たとえ分身の諸仏の総力をもってしても多宝塔の扉を開くことは出来ないということであり、分身の諸仏に対する本仏としてのお釈迦さまによる外はない、ということを意味しているのです。
次いでお釈迦さまは、娑婆大衆の願い、分身の諸仏の願いによって虚空に昇り、右の手をもって宝塔の扉を開かれるのですが、その時の有様は、
大音声を出すこと、関鑰をさけて大城の門を開くが如し。
といわれており、宝塔の扉を開く大音響は、あたかも頑丈なかんぬきが裂けて、大城の門が開かれるようであったということは、本仏によってしか開くことの出来ない扉が今、はじめて本仏によって開かれたという、その壮大さをあらわしているのです。
そういう宝塔の中に、法華経の行者といえども、どうして入ることが出来ましょう。地涌千界の上主である上行・無辺行・浄行・安立行という四大菩薩でさえ、宝塔の外に分身の諸仏もまた塔外にあって、二仏並座の宝塔を囲繞している有様なのです。
或る人は言うかも知れません。
「なるほど、閉ざされている宝塔の扉を開くことは困難なことであり、それが出来るのは今のお釈迦さまだけかも知れない。然し、今はもはや宝塔の扉は開かれているではないか。開かれ放しになっている宝塔の中に入るのに、何でむづかしいことがあろう。
観心本尊抄の末文にも、
四大菩薩、この人を守護したまわんこと、大公・周公の成王を摂扶し、四皓が恵帝に侍奉せしに異ならざるものなり。
といわれているではないか。塔外の四大菩薩も、我々を導いて塔中に入れてくれるはずである。遠慮することはない」
これでは、まるで空き巣ねらいであり、盗人たけだけしいとはこのことでしょう。ましてや多宝塔は、嘱累品の結びにおいては扉を閉ざし、本仏お釈迦さまの命によって、十方分身の諸仏がそれぞれの本土へ帰って行くように、多宝如来の本土と設定されている東方宝浄世界へと帰ってしまうことによって、本門八品の儀相は完結し、終幕となっているのです。
多宝如来といい多宝塔というものは、それによって総括象徴されている無始以来の無量の過去仏とその仏塔とを、お釈迦さまの前身であり、前身の仏塔であると明かすことによって、お釈迦さまの久遠実成と久遠の化導を実証する秘妙大方便の設定であったのです。
従って、寿量品においてお釈迦さまの久遠実成とその久遠劫来の常説法教化とが開顕され、更に神力品における妙法五字の別付嘱、嘱累品における総付嘱が完了されるや、多宝如来の任は終わり、方便身として方便の浄土である東方宝浄世界へと帰って行くわけです。
そういう方便を帯した多宝塔の中に、何故、入ろうとするのでしょうか。本門八品説法中の二仏並座の多宝塔は、本仏以外、分身の諸仏も本化の上首四大菩薩も入らずに、宝塔を囲繞・脇仕していたのにもかかわらず、何故、敢えてこの宝塔の中に入るとしたのでしょうか。
本門八品の説法の完了した後、もはや多宝塔は方便の塔となって東方方便土へ帰って行くのにもかかわらず、それでもその宝塔に入るのを願ったのでしょうか。おそらく彼等の願った宝塔は、東方の方便土へ帰った多宝塔ではなく、八品説法中の二仏並座の宝塔を指すものでありましょう。
然し、その宝塔の中には久遠の本仏しか入ることは出来ないのです。そういう宝塔の中に、敢えて入ろうとするのは、みずから久遠の本仏と思い上がり、或は阿仏房御書にいうが如く、みずからを多宝如来と思い、或は多宝塔と思い、或は三身即一の本覚の如来と思い上がっているからでしょうか。
それとも、宝塔の中に入るのでなければ、如何にお題目を唱えても、即身成道も来世成仏も成就したことにはならない、と思い込んでいるのでしょうか。
或は、法門のことを深く考えもせず、阿仏房御書や日女御前御返事の中の言葉に幻惑され「宝塔の内に入る」ということが、何となく恰好のよい言葉であり、耳ざわりもよいように思われることから、布教の方便として、単純に言ってみたまでのことにすぎなかったものでしょうか。
「いや実は、日蓮宗の寺院教会にしても、檀信徒の家庭の仏壇にしても、一塔両尊に大聖人の御尊像を安置して、これを三宝さまと仰いでいるから、この御本尊と信行者との感応道交の境を得せしめるため、宝塔の中に入るほどの心がけを持たしめようとしていたにすぎないのだ。要は、本尊との感応にある。宝塔の中に入るというのも、眼前の方便にすぎない」
と弁明されるかも知れません。
若し、こういう弁明がなされるならば、こともあろうに、本尊との感応に嘘の方便と用いたことになってしまいましょう。嘘の方便では、誠の感応の得られるはずはありません。
法華経は世界最大第一の聖典でありながら、その教学が世界にも通用せず、わずか数千個寺の日蓮宗内部においてすら混沌としている現状では、広宣流布も単なる掛け声にすぎないものとなってしまいましょう。
さて、先に私は、本法三段正宗分の「寿量」とは、「内証の寿量品」のことでもなく、また「寿量品の肝心たる名体宗用教の南無妙法蓮華経」のことでもなく、久遠実成の本仏お釈迦さまを本尊として、この本尊を中心に本化地涌の菩薩が宇宙大に充満し、本仏と本化とが互いに題目を唱えあい、法華経を実践している躍動の仏界そのもののことであって、これを象徴したものが、いわゆる一尊四士本尊形体であると言い、更に、この本尊形体こそ、二尊四士、或は、一塔両尊四士といった本尊形体よりも正意とされているものであるとも申しておきました。
ところが、本門八品の儀相にしても、大聖人図顕の大マンダラにしても、それは一尊四士を核とするものでなく、二尊四士・或は一塔両尊四士をもって核としているものです。
それにもかかわらず、何故、一尊四士をもって正意とするのか、何故、観心本尊抄の流通分段に一尊四士本尊を密釈した文意が頻出しているのか、という問題を次に考えてみることによって、本法三段正宗分「寿量」に関する考察を一往しめくくりたいと思います。
○一尊四士を核とする寿量世界と、塔中二仏並座を核とする大曼荼羅世界
本法三段正宗分の「寿量」とは、ここに改めて申すまでもなく、久遠の本仏お釈迦さまと、久遠の本弟子である本化地涌の菩薩と、久遠の本法である題目という本門の三宝不二一体なる躍動の仏界そのもののことであって、今、その文拠を法華経に求むるならば、従地涌出品にお釈迦さまみずから地涌の菩薩の由来を説明されて、次のように申された言葉をあげることが出来ましょう。それは本門正宗分、略開近顕遠をあらわす文拠でもあるのです。
この諸の大菩薩摩訶薩の無量無数阿僧祇にして地より涌出せる、汝等、昔より未だ見ざる所の者は、我れ、この娑婆世界において阿耨多羅三藐三菩提を得おわって、この諸の菩薩を教化示導し、その心を調伏して、道の意をおこさしめたり。
この諸の菩薩は、皆この娑婆世界の下、この界の虚空の中において住せり。諸の経典において読誦通利し、思惟分別し、正憶念せり。
阿逸多(弥勒菩薩よ)、この諸の善男子などは、衆にあって多く所説あることをねがわず、常に静かなる処をねがい、勤行精進して、未だ曽って休息せず。また人天に依止して住せず。常に深智をねがって障碍あることなし。また常に諸仏の法をねがい、一心に精進して無上慧を求む。
また重ねて偈を説いて次のように申されてもいます。
この諸の大菩薩は、無数劫よりこのかた、仏の智慧を修習せり。悉くこれ我が所化として大道心をおこさしめたり。これ等は、これ我が子なり。この世界に依止せり。常に頭陀の事を行じて、静かなる処を志楽し、大衆の 閙を捨てて、所説多きことをねがわず。かくの如き所子等は、我が道法を学習して、昼夜に常に精進す。
閙を捨てて、所説多きことをねがわず。かくの如き所子等は、我が道法を学習して、昼夜に常に精進す。
仏道を求むるをもっての故に、娑婆世界の下方の空中にあって住す。志念力堅固にして、常に智慧を勤求し、種々の妙法を説いて、その心、畏るる所なし。
我れ、伽耶城・菩提樹下において坐して最正覚を成ずることを得て、無上の法輪を転じ、しこうして乃ちこれを教化して、初めて道心をおこさしむ。
今、皆不退に住せり。悉く当に成仏を得べし。我れ、今、実語を説く、汝等、一心に信ぜよ、我れ久遠よりこのかたこれらの衆を教化せり。
ここにいう「我久遠よりこのかた、これらの衆を教化せり」と示されている「我れ」とは、無始以来の無量無辺なる過去仏を悉く我が身とし、我が過去の前身とした久遠実成の「我れ」釈迦牟尼世尊のことであり、その成道の久遠をあらわすために、今番出世のお釈迦さまが中インド・ブッダガヤ、尼連禅河の菩提樹の下で成道された事実にもとずき、お釈迦さまの前身である無量の過去仏の成道の場所も「伽耶城・菩提樹下」とされ、畢竟して無始久遠の昔における初成道時の場所も「伽耶城・菩提樹下」とされているのです。
問題は、久遠初成道時の場所が、果たして「伽耶城外、尼連禅河畔の菩提樹下」であったかどうか、ということではなく、今番成道の内容も、時も、場所も、みな悉く同一のものとして、繰りかえし繰りかえして無限の過去にさかのぼることによって久遠ということ、不変ということ、常住ということが象徴されているということです。
しかも、無限に繰りかえされて来た諸仏の成道が、「伽耶城・菩提樹下」と明確に具体的に表記されているように、この現実の娑婆世界から一歩も離れたものでなく、従って久遠劫来の常説法も、娑婆世界において無限に繰りかえし展開されて来たものであったことが強調されていることを見落としてはなりません。
地涌の菩薩が、大地より涌出する以前、久遠劫来、昼夜常精進していた住処を「この娑婆世界の下、この界の虚空の中」といい、「娑婆世界の下方の空中」といわれていますが、そういう虚空浄土が、娑婆大地の底に、地底世界の如く存在するというのではありません。
本仏本化不二なる久遠の浄土が現実の娑婆全世界に実在しながら、衆生の顛倒した盲目により、或は二乗・迹化の盲目によって、見出されないばかりでなく、顛倒の業によって、おおいかくされてしまっていることを、娑婆大地の下方の虚空浄土と象徴しているにすぎないのです。
前にも述べたことがありましたが、インドでは一年間に平均一ミリの砂塵が積もるとされています。この割合で計算すれば、十年間に一センチ、百年間に一メートル、千年間には十メートル、一万年間には百メートルの砂塵が積もることになります。
大乗仏教の興起した西北インドの人々は、西方との交易の間、シルクロードのオアシス都市が廃墟と化し、やがて積もる砂塵に埋没してしまった幾多の実例を知っていました。インド国内においてもインダス文明をになっていたモヘンジョダロとかハラッパーという古代都市が、紀元前一五〇〇年の頃、廃墟と化し、地中深く埋没してしまった歴史も知っていたはずです。
このような誰でも見聞している埋没都市の事実に照らして、娑婆地上の仏国土が、衆生の顛倒・妄想の塵埃におおわれ、埋没してしまったことを、大地の下方の虚空浄土として表現したのです。
然し、地下に埋没した虚空浄土が、決して衰退したものでもなく、廃墟と化したものではないことは、本仏本化の躍動によっても明らかなはずです。またその埋没した虚空浄土が、大地の内の中心部分とか一部分といったものでなく、大地全域に及ぶものであったということは、従地涌出品に、
娑婆世界の三千大千の国土、地みな震裂して、その中より無量千万億の菩薩摩訶薩あって同時に涌出せり。
と述べられていることによっても明らかでありましょう。
この時、震裂したのは大地の一部分でなく、大地のすべてであり、地涌の菩薩は大地の一部分から蟻の行列の如く涌出したのではなく、大地のありとあらゆる処から同時に出現したのです。このことは大地のすべてが虚空浄土であったということなのです。
大聖人は観心本尊抄の四十五字法体段において、
今、本時の娑婆世界は、三災を離れ、四劫を出でたる常住の浄土なり。仏、既に過去にも滅せず、未来にも生ぜず、所化もって同体なり。
と仰せられていますが、ここに、このように示されている「本時の娑婆世界」こそ、顛倒の衆生の妄想・妄見によっておおいかくされていた本仏本化の父子一体となって常住している仏国土であったのです。
それは、あくまでも現実の大地の世界であり、「娑婆即寂光」といったような観念観法の世界でもなく、また捕らえようもない四次元のような霊界でもないのです。
「本時の娑婆世界」は、久遠の本仏お釈迦さまを中心として、その嫡子である本化地涌の菩薩によって、無始の昔に建立され、未来永劫に変わることのない娑婆仏国土であり、如来秘密神通之力・如来毎自の大本願呪力の題目の充満し躍動している現実の世界でした。
ここでは、もはや多宝如来や多宝塔の出現する必要もなく、十方分身の無量の諸仏の来集する必要もなく、またそれを必要とする迹化の菩薩も、声聞・縁覚という二乗者もおらず、もとより六道流転の衆生も存在してはいませんでした。
何故ならば、既に本化の菩薩のすべては、本仏より下種され、大道心を起こさしめられ、常説法の教化をうけて来た体験を通して、お釈迦さまの久遠実成の本仏たることと、その無始の化導の永遠なることを、身にあてて確信しており、またここでは、三乗方便の教々は尊重されても実修されることはなく、実修される処は、無二亦無三の一仏乗のみであったからです。
多宝如来と多宝塔の大地涌出は、無始以来の無量の過去仏のすべてを前身とされたお釈迦さまの久遠実成を知らない人々に対して、これを知らしめ信受せしめんがため、無量の過去仏を総括象徴した方便客仏として出現し、塔中二仏並座の儀相を整えたのであり、十方分身の無量の諸仏とその眷属を代表する迹化の菩薩の来集もまた、分身の諸仏に対してお釈迦さまこそ本仏であることを知らない人々に対して、これを知らしめ信受せしめんがためであったのであり、更に地涌の菩薩の大地涌出は、お釈迦さまの久遠の本仏としての久遠の化導の事実を知らない人々に対して、これを知らしめ信受せしめんがためであったのです。
お釈迦さまの久遠の開顕と本仏の開顕、そして地涌の菩薩の出現によって、本因本果不二ということが現実のものとしてあらわされ、妙法五字も因行果徳の二法であることが明確にされるのですが、既に方便品に、
十方仏土の中には、ただ一乗の法のみありて、二もなく、また三もなし。
と宣言されているように、本仏久遠の仏国土には、仏弟子として充満するのは、この因行果徳の一仏乗を専修する本化地涌の菩薩のみであって、余乗を修する迹化の菩薩も二乗の声聞・縁覚もいるはずはなく、まして六道の人天がいるはずはないのです。
本法三段正宗分の寿量仏界とは、まさしくこのような久遠の本仏お釈迦さまを中心とする本化地涌の菩薩の充満する世界でした。その中核は、地涌千界の上首上行・無辺行・浄行・安立行という四大菩薩が、本仏お釈迦さまの脇士となって東西南北に囲繞しているものでした。ここに寿量仏界における本尊様式として、一尊四士本尊形体が形成されて来るのです。
ところが、見宝塔品より嘱累品に至る霊山虚空会上は、二仏並座を中核としており、大聖人図顕の大マンダラも本門八品の儀相によって二仏並座を中核としていて、一見、寿量仏界の中心核である一尊四士様式と矛盾しているかに思われもしましょう。
然しながら、これまで幾度も繰りかえして述べてきましたように、多宝塔の大地涌出に始まって三変土田・分身来集・宝塔開扉を経て、二仏並座に至った儀相展開は、難信難解とされる生身のお釈迦さまの久遠の仏身を、未だ知らず、未だ信じられない一切衆生に対して、これを知らしめ信受せしめんがための一大秘妙方便であったのです。
若し、このような方便施設を行わずに、突如として寿量品において久遠実成を開顕し、無始久遠劫来の常説法教化の実体を回顧披瀝して、
我れ成仏してよりこのかた、またこれ(五百億塵点劫)にすぎたること百千万億那由陀阿僧祇劫なり。これよりこのかた、我れ常にこの娑婆世界にあって説法教化す。また余処の百千万億那由陀阿僧祇の国においても衆生を導利す。
諸の善男子、この中間において我れ燃灯仏等と説き、またまたそれ涅槃に入ると言いき。かくの如きは、皆、方便をもって分別せしなり。
と述べ、更に、
度すべき所に随って、処々に自ら名字の不同・年紀の大小を説き、またまた現じて当に涅槃に入るべしと言い、
と繰りかえしてみたところで、地涌の菩薩以外、誰がこれを信ずることが出来ましょう。如何に仏陀とはいえ、地上有限の人間が、久遠であるとは、到底信じられない処です。口先だけのことならば、どんなに不可能なことでも言えるでしょう。然し、これが信ぜられるには実証が必要なのです。
お釈迦さまの場合も同様であって、お釈迦さまが無始の昔に成道され、たとえ名字の不同・年紀の大小という差違はあっても、燃灯仏とか無量の過去仏として出現しては常説法教化の化導をほどこし、方便現涅槃を繰りかえして来たものであるという以上、その事実が実証されなければなりません。
ここにお釈迦さまと無量の過去仏とが同体不二であることを証するため、無量の過去仏を総括象徴した多宝如来の真実証明が本願として公表され、二仏並座という塔中の儀相が展開されたのであり、また久遠の化導を実証するため、地涌の菩薩が大地より涌出し、お釈迦さまを父と仰ぎ、お釈迦さまはこれらの菩薩を我が子なりと呼びかけるドラマが展開されたのです。
そして、こうした数々の実証を経て、はじめて寿量品における久遠本仏の仏身開顕と久遠の化導開顕が大衆に納得され、信受歓喜されるに至ったのです。まさに寿量品は、失本心の顛倒の衆生に対して、寿量仏界の実在を知らしむるものであったと申されましょう。
塔中二仏並座は、お釈迦さまの久遠実成の本仏たる仏身を実証せんがための秘妙大方便でした。従って、見宝塔品第十一より嘱累品第二十二に至る霊山虚空会は二仏並座を固定して見る限り、それは方便の仏土であり、従地涌出品第十五において地涌の菩薩が涌出することによって、真実の寿量仏界が、方便の虚空仏界に重層したのですから、本門八品は寿量仏界を本として見なければならないのです。
即ち、二仏並座についていうならば、並座した多宝如来に総括象徴されていた無量の過去仏は悉く、並座したお釈迦さまの仏身中に摂取され、これによって塔中のお釈迦さまは寿量仏界の一尊四士の一尊としての面目を顕現すると共に、内味を失った名目だけの多宝如来は、分身の諸仏と同じ客仏となって宝塔の扉をみずから閉じ、東方宝浄世界へ帰って行かねばならないのです。
そこで説かれたのが嘱累品であったわけですが、嘱累品において多宝如来が宝塔の扉を閉じて東方の本土とされる処へ帰るよう、お釈迦さまより命ぜられたわけを考えねばなりません。それはおそらく以上のような事由によるものでありましょう。
これまでの日蓮宗教学者の中には、見宝塔より安楽行品第十四までは、真の虚空浄土ではなく方便の空中浄土であり、従地涌出品以降、地下の虚空浄土が顕現することによって、真実の虚空浄土に転じていると主張する人もいるようです。
ここに本門八品の二仏並座の儀相が絶対化され、固定化され、二仏を境智の二法に配当したり、或は能説の仏、所説の教と考え、更には大マンダラ全体が絶対化され、日女御前御返事の中の大マンダラ観の如き思想が蔓延して行くのです。
若し、八品の儀相が絶対的なものであるならば、多宝塔の開扉、帰国の勅も起こらず、嘱累品の「余深法中、示教利喜」という付嘱も起こらなかったことでしょう。嘱累品におけるこの二個の告勅は、本門八品の中になお真実の寿量仏界と、そうでない方便の仏界とが、二重に重層していた、と見ることが出来ましょう。更に言うならば、その方便の仏界は、八万法蔵の経々に説かれている方便土へも拡大されましょう。
寿量仏界より方便土への働きかけは、神力品の別付嘱となり、方便土より寿量仏界への指向は、嘱累品の「如世尊勅、当具奉行」という誓願となっているのです。
〈執筆の時間がなくなりました。この項は改めて述べることにします。〉