自我偈随想 〔第二十八回〕
如来毎自の大本願力 ーその四ー
前回のプリントの後半は、九州の上野峡道場で執筆したため、必要な資料を欠き、曖昧なことしか述べられませんでした。四月上旬、東京から身延へ廻りわずかな資料ですが、それによって確認されたことが二・三ありますので、「五百億塵点劫来の因果」、それにともなう「如来久遠の大本願力」について述べる前に、その二・三を補足しておきたい、と思います。
○二乗の浄土における黄金の縄
さて、前回、法華経迹門における二乗授記作仏の実態を解明する中で、譬喩品における舎利弗尊者に対する授記内容を主として取りあつかってみました。そしてその授記での舎利弗の建立する未来浄土の様相と、自我偈に明らかにされている本仏お釈迦さまの常住の浄土の様相とを対比し、その両者があまりにも酷似していることを考えてみました。
自我偈にいう浄土とは、
我が此の土は安穩にして、天人常に充満せり。園林もろもろの堂閣、種々の宝をもって荘厳し、宝樹華果多くして衆生の遊楽する所なり。諸天、天鼓をうって常にもろもろの伎楽をなし、曼荼羅華をふらして、仏および大衆に散ず。
ということであり、舎利弗の建立する浄土とは、
その土、平正にして清浄厳飾に、安穏豊楽にして天人熾盛ならん。瑠璃を地として、八つの交道あり。黄金を縄となして以てその側(ホトリ)を界(サカ)い、その傍(カタワラ)に各々七宝の行樹あって、常に華果あらん。
ということです。
無上正等正覚の仏の浄土ですから、両者の浄土が類似しているのも当然であると申されましょう。厳密にいえば、舎利弗の浄土は「始成の浄土」、本仏お釈迦さまの浄土は「久成の浄土」という相違はあるはずです。
然し、この二つの浄土は、決して別個のものでもなく、対立するものでもありません。何故ならば、舎利弗が授記の通り、未来無量劫の間、無量の諸仏のもとにおいて、ひたすらに一仏乗を修するならば、必然本化地涌の菩薩の自覚と使命に立つようになり、従って、他土において浄土を建立するという授記は、末法娑婆世界において浄土を建立するという付嘱と転じ、他土も此土に転じて来るからです。お釈迦さまの授記にしても、二乗の建立浄土が、敢えて指方立相の浄土でなかったのも、こういう内意を踏まえられていたからでありましょう。
ところで、二乗授記中の建立浄土が、二乗の本化地涌の自覚にともなって、末法娑婆世界へ指向している証佐として、その浄土の様相の中に述べられている「八つの交道」と「黄金の縄」をあげることが出来ましょう。
「八つの交道(きょうどう)」については、岩本裕博士は岩波本の法華経上巻(一四六頁)に「八つの交われる道」と訳し、(三四四頁に)、
東西南北に四隅を加えて、この八つの方向に通じて往来する道
と註していますが、おそらくそれは縦四本・横四本の道路が碁盤の目のように交叉している状態をさすのではなく、中央から四方・四隅にむかって八本の道路が放射状に設けられている状態をいうのでありましょう。
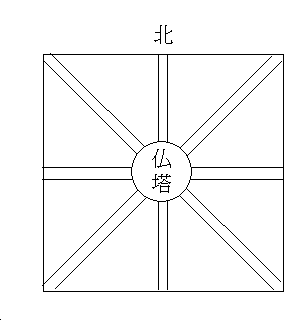
若し、そうであるならば、八道の集中交叉する中央部は、国土の祭政をつかさどる集会堂であったのではないか、と思わしめられるのです。
お釈迦さま御在世当時の非アーリヤン社会の聚落・城邑には、東西南北の四方に門があり、その中央に祭政をつかさどる壁のない屋根と四本柱の集会堂がありました。丁度、相撲の土俵のような形です。
お釈迦さまが入滅されたクシナガラの町もそうでした。そうと思われることが、お釈迦さまの入滅後、遺骸を荼毘にふすまで記録によって、うかがうことが出来るのです。渡辺照宏博士はその著「新釈尊伝」(四七八頁〜四七九頁)に次のように述べています。
夜が明けると、アーナンダはアニルッダの意を受けて、クシナガラのマルラ族の人たちに仏陀の入滅のことを知らせました。その時も一同は集会堂に集まって相談している最中でしたが、知らせを聞くと、世尊の入滅があまりにも早かったことを嘆きました。
やがて人々はクシナガラにあるありとあらゆる香木と花と、そして、あらゆる音楽の支度とをととのえました。これらと葬儀の用意とを携えてサーラ樹の林に行き、仏陀の遺骸を供養し、舞踏、歌、音楽を演じ、花や香を供えてその日を過ごしました。次の日もまた次の日も同様に過ぎました。こうして七日目になると、火葬をすることになったのです。
マルラ族のうちから最も尊敬されている八人がえらばれ、頭を洗い、真新しい衣服を着けて、世尊の棺を持ちあげようとしたが、どうしても持ちあげることができません。
人々は不思議に思って、アニルッダにその理由を訊ねると、人々の考えと、神々の考えとが食い違っていることが判りました。人々の考えでは、クシナガラの町の外側をめぐり、南門の外において火葬を行うつもりでした。ところが神々の考えでは、北門から町に入り、町の中央部に達し、そこで神々の供養をすませてから、東門を出て、宝冠(マクタ・バンダナ)とよばれている社に行き、そこで火葬を行うというのです。
そこでアニルッダの教えに従い、神々の意志のとおりに棺を運び、宝冠という社に棺を安置しました。そこでマルラ族の人々はアーナンダに火葬の方式を訊ねました。アーナンダの説明により、転輪聖王に対する礼をもって仏陀の遺骸を布で包み、金属の棺に納めました。
この記事によっても、クシナガラの町には東西南北に門があり、町の中央広場に集会堂のあったことがうかがわれます。お釈迦さまの遺骸が、沙羅双樹のもとから町の北門を通って、中央集会堂へ運ばれ、ここで神々の供養をうけたということはおそらく史実でありましょう。
渡辺博士は同書(四六一頁)に、まさに涅槃へ入られようとしているお釈迦さまに対して、最後の別れを告げるべく、多くの神々の蝟集したことを、次のように紹介します。
ウパヴァーナというビクがいました。久しく仏陀の近くにいて仕えていたが、この時になって仏陀は、ウパヴァーナを身辺から遠ざけられました。アーナンダは不思議に思って、その理由を伺うと、次のように説明されました。
「アーナンダよ、今やクシナガラのサーラ樹林の周辺は、毛一本さしこむすきもないほど多くの神々がつめかけて、如来に最後の別れを告げようとして待っているが、如来の前に、偉力あるビクが立っていて近づくことができない、といって嘆いている。それ故に、ウパヴァーナを遠ざけたのである。」
ウパヴァーナという仏弟子が如何なる人物であったかは判りませんが、相当な呪力をもった比丘であったのでしょう。その呪力にさえぎられて蝟集した神々もお釈迦さまのそばに近づくことが出来なかったのかも知れません。修行者の呪力が激しく猛々しい場合、神もこれを避けることがあるものです。
おそらく、こうしたこともあって、神々の総意が、お釈迦さまの遺骸をクシナガラの町の中央広場の集会堂へ運び、そこで改めて神々の供養を捧げる、ということになったのかも知れません。或は、荼毘にふす前に最後の盛大な供養を営む場所として中央広場を選定するのに神の意志を用いたのかも知れません。
いずれにせよ、非アーリヤン社会における聚落・城邑にあっては、集会堂を中心とする中央広場があり、それより東西南北の四方に、或はそれに四隅を加えて八方に、放射状に道路がつけられていたようです。当時の都市国家の構築がどのようなものであったかは判りませんが、少なくとも、そういうような町造り、国造りを理想として、舎利弗の建立する浄土に「八つの交道あり」とうたわれたのは事実でありましょう。
すると、舎利弗が遠い遠い未来世に建立するという「離垢」という名の浄土は、決して抽象的なものではなく、あくまでも現実に即した大地の浄土ということが出来ましょう。
非アーリヤン社会は、その聚落・城邑の中央集会堂における合議・選挙による政体でした。その政体は、やがてアーリヤンの専制政治に併呑され、或は破壊されてしまうのですが、然し、その合議主義の体制は、そのまま仏教の僧伽の中に継承されて行くのです。
仏教は、非アーリヤン的合議政体からアーリヤン的専制政体へ移行する過渡期に成立しました。従って仏教の国土観の中に、両方の政体が当然加味されて来ているのです。たとえば俗的には人間平等・階級打破を主張しながらも転輪聖王の出現が待望され、聖的には一切衆生の成仏を鼓吹しながらも、久遠の本仏お釈迦さまを中心とすることが主張されているのです。
お釈迦さまが入滅の地をクシナガラに選ばれた理由として、クシナガラこそ久遠の大昔、大善見王という転輪聖王の統治していた首都であり、ここで大善見王が入滅された聖地であり、ということがあげられています。またお釈迦さまは、滅度の葬儀を転輪聖王の葬儀の仕方でなすように遺言され、そのように実施されたと伝えられています。
お釈迦さまが生誕された時、占師が、
「王位にあれば転輪聖王となり、王位をすてて出家すれば仏陀となるであろう」
と予言したといわれていますが、今やお釈迦さまの臨滅度時にあっては、転輪聖王と仏陀とは、別々の存在ではなく、一つのものとして重なりあっているのです。
この重複は、もともとお釈迦さまが法界の転輪聖王であられる以上、至極当然のことのようではあっても、注意しなければならないことは、曽って国土の中心、聚落城邑の中心、家屋の中心といった物質的中心崇拝が、転輪聖王とか仏陀といったような精神的中心崇拝に転じ、更に転輪聖王という世俗的中心崇拝が、仏陀という聖的中心崇拝に重なって一つになっているということです。
寺院の本尊を安置する壇を、通称「須弥壇」とも申しますが、須弥壇とは須弥山の頂上大地のことであり、須弥山とは地下をつらぬき天竺をつらぬく円筒形の宇宙軸である以上、寺院の須弥壇は、当然、宇宙の中心軸という意義をもっていたはずです。ところが最近では、すっかりそういう宇宙軸という意義を忘れ去れてしまい、須弥壇下にぬかずく者自身、宇宙の中心点に立っているという自覚も失われてしまっています。
古代遊牧民族の移動用天幕の頂上は、北極星をさしていると信じられていました。ここにも宇宙軸の信仰がうかがわれます。古代家屋の中心は暖炉でした。暖炉の火は生活の火であり、同時に神に祈る火でした。ここにも中心軸の思想があります。
現在、地鎮祭を行う時、四方を結界し、その中央に土を盛り、榊を立てて神の降臨を仰いでいますが、それは家の中心点に立って、その家が宇宙軸となる儀式でもあるのです。然し、今や地鎮祭は形式に流れ、家における宇宙軸思想は、文字通り地を払い、仏壇や神棚は邪魔にならないように隅の方へ追いやられてしまっているのが通常です。こういうことでは家庭に信仰の興る道理はありません。
寺院も一般家庭も唯物化した現代、もう一度、舎利弗の建立浄土における「八つの交道」をふりかえってみる必要がありましょう。その仏国土の中に「八つの交道」の交叉する中央広場、その広場こそ、国土を単位とする宇宙軸であり、非アーリヤン社会に建てられていた中央集会堂は、仏国土においては仏舎利塔となるのです。その典型的な造形は、ガンダーラ地方の仏舎利塔であり、それを代表するものは、パキスタンのペシャワール東南一キロの所に発掘されたカニシカ大塔と申されましょう。
この大塔は、基壇の地下から銅製の仏舎利容器が発見されたことで有名になっていますが、「NHK未来の遺産取材記―刻まれた情念」(二八〇頁)には、次のように報ぜられています。
この塔は、円形を基本とするインド中央部の塔とは違い、四方に突出部のある方形基壇であった。方形の一辺は八七メートルもあるという巨大な塔である。基壇の地下からは銅製の舎利容器が発掘された。筒形の容器で、蓋の上には仏陀と梵天・帝釈天の三尊像が乗っている。文字も刻まれていた。それによって、この舎利容器は、カニシカ大王の元年、カニシカ寺に奉献されたものであることが分かった。(中略)
カニシカ大塔のことは、三蔵法師玄奘をはじめとする中国のインド求法僧の紀行文にみえる。玄奘の「大唐西域記」によれば、塔の基部は一周一里半、基壇は五階で、高さ一五〇尺(唐の尺度についても諸説があるが、だいたいにおいて一里は四〇〇メートル前後、一尺は三〇センチ前後)、さらにその上に二五層の金銅の相輪がつくという高大なものであった。
カニシカ大塔は完全に崩壊しており、今日、その全体の構造を明らかにすることは出来ないが、幸いにローリヤン・タンガイ出土の小塔などによって、ガンダーラの仏塔の姿を想像することは出来る。
即ち、ここにいう方形基壇とは、そのまま国土を象徴し、その中の円形塔身は、国土の中央、八つの交道の交叉する中心広場に建てられるべき仏舎利塔が国土一面に拡大されたものであって、そのまま天地をつらぬく宇宙軸となっていることをあらわしているのです。
この大塔の基壇地下より発掘された舎利容器(ペシャワール博物館所蔵)の上部三尊像(仏陀と梵天・帝釈)の真下の筒形正面にカニシカ大王の立像が浮彫りされていますが、その写真をよくよく見つめていると、円筒の容器そのものが須弥山に代わる宇宙軸であり、法界の転輪聖王たるお釈迦さまに脇仕する梵天・帝釈は諸天を代表してマンダラ仏界を形成し、カニシカ大王は世俗の転輪聖王として、宇宙軸の中にあって仏界を背負い、ささえているかの如く感ぜしめられて来るのです。
若し、そうであるならば、お釈迦さまが臨滅度時において、「クシナガラの地は曽って大善見王という転輪聖王が統治の都をおき、ここにおいて入滅された故事によって、私の滅度の地をクシナガラに選んだのである」と仰せられた言葉の中の、世俗の転輪聖王と仏陀の不二相即性は、カニシカ大塔の舎利容器の造形に遺憾なく象徴されていると申されましょう。
転輪聖王、それは神話や説話の中に留まるものでなく、仏陀が地上にお釈迦さまとして出現されたように、必ず地上に出現するものとして信じられ、待望されていた大王であったのです。マウリヤ王朝を代表する阿育大王がみずから大善見王と称したのもこのためであり、カニシカ大王がカニシカ大塔の仏舎利容器の側面にみずから自分自身のレリーフを造形せしめたのも、こうした思想系譜によるものと申せましょう。
曽って、インドの民衆にとっては、太古より伝承して来た過去仏思想の中に、お釈迦さまが仏陀として出現されたことは、まさしく神話が現実化したほどの驚きであり、この驚きの中に、神話伝承の過去仏の実在が確証されると共に、転輪聖王もまた必ず現実のものとして顕現するという確信を強くしたことでしょう。この確信に応えたのが阿育大王であり、カニシカ大王であったのです。
その後、転輪聖王の思想は西域を渡り、中国を経て日本に伝来し、日蓮大聖人の観心本尊抄にあらわされてきます。同抄に、
我が弟子、これをおもえ、地涌千界は教主釈尊の初発心の弟子なり。(中略)
かくの如き高貴の大菩薩、三仏に約束してこれを受持す。末法の初めに出でざるべきか。当に知るべし。この四菩薩、折伏を現ずる時は、賢王となって愚王を誡責し、摂受を行ずる時は、僧となって正法を弘持す。
と仰せられているのが即ちそれです。ここにいう折伏を現ずる賢王とは、申すまでもなく転輪聖王にほかなりません。同抄には、つづいて、
この時、地涌千界出現して、本門の釈尊の脇仕となり、一閻浮提第一の本尊この国に立つべし。
と宣言されているところから、転輪聖王が四大菩薩の一人として、久遠の本仏お釈迦さまの脇仕となって、ここに一尊四士本尊形態が一閻浮提第一の本尊として日本国に実現する、ということになって来るのです。
大聖人の一尊四士本尊形態については、曽って中山法華経寺の法華堂内陣の秘仏とされている大聖人開眼による二具十体(二組の一尊四士)の形態に徴して、本仏お釈迦さまを中心として、東西南北の四方に本化の四大菩薩を立体的に配置さるべきものであると述べたことがありましたが、このような一仏を中心とする四人の座配形態は、真言密教の金剛界マンダラにも図示され、造立仏としては京都の東寺講堂にも現存しており、中国においては敦煌の莫高窟の内にも見かけられるものです。
面白いと思うのは、敦煌石窟内の一尊四士形態です。中央のお釈迦さまの前方両脇には有髪の菩薩の立像が配置され、後方両脇には剃髪の仏弟子の立像が配置されています。仏弟子の名前も、菩薩の名前も、今のところ不明ではありますが、お釈迦さまに脇仕する四人が、在家と出家に分けられて造形されている有様は、観心本尊抄にいう折伏の賢王と摂取の聖僧という分け方にも一脈通ずるものがあるように思われましょう。
私は、観心本尊抄の一尊四士像の中、本化の四大菩薩は、僧形の菩薩像と有髪在家の菩薩像に分けられ、更に摂受と折伏の二門にも配されるべきではないか、と至念しつづけているものです。そしてこのような造形によって、お釈迦さまの生誕臨滅度時以来の転輪聖王思想も、ここにきわまって来ると思えるのです。
譬喩品における二乗浄土の「八つの交道」という文字から、国土の中心思想・宇宙軸思想という話に及び、国土の中心広場における集会堂は仏舎利塔と転じ、更に宇宙軸の仏舎利安置の仏像が、転輪聖王をふくむ一尊四士本尊様式として、これが一閻浮提第一の本尊たるべきである、というように話は飛躍してしまいましたが、要するに、二乗声聞の未来世に建立する仏国土の構造というものは、気も遠くなるほどの遠い遠い未来世の、架空にも等しいもの、蜃気楼のようなものでなく、あくまでも今日只今における現実的なものであり、地上に初めて国造りされる創造的世界であるということです。
二乗声聞によって建立される仏国土の具体的構造は、そのまま本門如来寿量品の自我偈にいう「我此土安穏」の仏国土、本仏常住の仏国土においても同様にいわれなければなりません。
自我偈の仏国土には「八つの交道」とか「黄金の縄」といったものは示されてはいません。「八つの交道」という境界をしきるような線は消えて、線は平面となっています。
九州大学の宗教学助手笠井正弘氏は、先月(三月)私が氏の自宅を訪ねたとき、「八つの交道」に対する私の見解について、
「古代の統一国家というものは、ポリス(都市)とポリス(都市)を結ぶ主幹道路を統治するものであって、点と線によって構成されていた。そして主幹道路より少しでもはずれた処は未開の蛮地に等しいものであった。そうした点と線を統治していた国家が、平面全体を統治するようになるのは、もっと後代である」
と述べていましたが、自我偈の仏国土は、まさしく点と線が平面化し、仏日のあまねく国土全体を照耀している様相を物語るものであり、二乗の建立浄土より発展したものとも申されましょう。
然し、自我偈に「我此土安穏」という仏国土は、中心もない単なる平面的な国土ではなく、転輪聖王を脇仕としてふくむ一尊四士本尊塔が、その中央に宇宙軸として厳然としていることを、亡失してはならないでありましょう。
日蓮大聖人の大マンダラにおいても、題目が三世十方をつらぬく中心軸となっており、その中心軸に必ずといってよいほど転輪聖王は勧請されていました。一仏乗による国造りには、必ず転輪聖王の出現がなければならないのです。転輪聖王が本化の菩薩として国造りの行政をしなければならないのです。出世間の仏陀や僧侶によって国造りの出来るはずはありません。
宗教者は為政者の思想を諌暁しても、直接行政にたずさわってはならないのです。お釈迦さまもそうでした。大聖人もそうでした。精神の指導者であっても、行政の指導者ではありませんでした。宗教と政治とは、決して車の両輪でもなければ、鳥の両翼でもなかったのです。
八つの交道の交叉する仏国土の中央に位いする宇宙軸は、行政府でなく、本尊塔であったのです。転輪聖王が地涌の菩薩と共に礼拝・護持し、讃歎宣布する本仏お釈迦さまの仏塔であったのです。
さて次ぎに、二乗の建立する仏国土の中の「黄金の縄」について考えてみましょう。先にも挙げてみましたように、譬喩品には舎利弗の建立浄土の様相を、
瑠璃を地となして、八つの交道あり。黄金を縄となして、以てその側を界い、そのかたわらに、おのおの七宝の行樹あって、常に華果あらん。
と述べています。
また授記品第六の初めには、大迦葉が未来世において三百万億の諸仏(本門では、この諸仏が開顕統一されて本仏お釈迦さまに包摂されるに至るのですが)を供養して後、みずから「先徳」という仏国土を建立すると授記されているのですが、その仏国土の様相にしても、
瑠璃を地となして宝樹行列し、黄金を縄となして、以て道の側を界い、もろもろの宝華を散じ、周 して清浄ならん。
して清浄ならん。
と述べられており、同じ授記品に、大迦旃延が未来世においてまず八千億の諸仏を供養し、更にまた二万億の諸仏を供養して後、仏陀となって建立する仏国土の様相にしても、
その土、平正にして頗黎を地となし、宝樹荘厳し、黄金を縄として、以て道の側を界い、妙華、地をおおい、周 清浄にして、見る者、歓喜せん。
清浄にして、見る者、歓喜せん。
と述べられているのです。
大迦葉の仏国土と、大迦旃延の仏国土には「八つの交道」という文字はみえませんが、共に「黄金を縄として、以て道の側をさかい」すると述べられている以上「八つの交道」という言葉は省略されていると申せましょう。
すると、二乗の建立する仏国土には、中央で交叉する「八つの交道」という主幹道路があり、それぞれの道に両側には、「黄金の縄」が延々として張りめぐらされ、その縄のかたわらには、華も実もある宝樹が天をおおって延々として繁茂しているという風光をうかがうことが出来るわけです。
なお、そのいずれの国土には、山も谷もなく、大地平正であるというのは、大乗経典の成立した西北インド、特にヒンズークシュ山脈を越えた西方の西域地方、或いはイラン高原につらなる中近東地方の、雨も乏しく、草木もなく、赤茶けた山塊の重畳する乾燥地帯に対して、緑輝く沃野の、地平線の彼方まで延々としてひろがっている国土を理想の国土として画いたものであって、山もなく谷もなく大地平正であるということを教学上、それは「平等」を象徴したものであるという説を述べる人もあるようですが、平等というよりも、大地の豊饒と文化文明の円融をうたいあげようとしたものというべきでありましょう。
八つの交道の沿道両側に、常に華も実もある宝樹が天をおおって延々として繁っているということも、国土の豊饒・生産・通商の繁栄をあらわしているのです。宝樹は聖樹ともいい、樹神信仰の対象でした。樹神は殆ど女神であり大地母神でした。ここに樹下美人というモチーフが起こり、「樹下の仏陀」という構図が生じて来るのです。法華経の各処に「宝樹下の獅子座上の諸仏」というのが即ちそれです。
宝樹は地下幾由旬・地上幾由旬という巨大なものであり、宝樹そのものが宇宙軸でした。宝樹によっては上は梵天に至り、枝葉は三界をおおうと述べている経文もあるほどです。仏陀の坐られている獅子座にしても宇宙軸でした。
現在ブッダガヤのお釈迦さまの成道の聖地を供養する大塔の西面の菩提樹の下の金剛宝座、それは阿育大王が造形したものともいわれていますが、その金剛宝座の岩が地下無限につながっているといわれているのも、獅子座が宇宙軸であるという信仰をあらわしているのです。
なお、獅子座というのは、もともとエヂプト王の玉座であり、またアケメネス王朝ペルシャ帝国の帝王の玉座でした。そして大帝国の王の玉座がそのまま仏陀の玉座として用いられるようになったのですが、ここにも仏陀と転輪聖王との不二相即すべき一端をうかがうことが出来ると申せましょう。
次ぎに、仏国土には、瑠璃をもって地となすとか、頗黎(水晶)をもって地となすという表現がなされていますが、要するに大地が七宝の宝石でおおわれているということであって、それは単なる装飾ではなく、抽象的な美的表現でもなく、仏陀の威徳・神通呪力が国土全体に遍満し、一礫一塵に至るまで、その呪力の光明を放っているということなのです。
八つの交道の沿道両側をさかいする縄が黄金によって作られたものであるというのも、そういう仏陀の呪力をあらわしているものであって、それらの宝樹・宝石・黄金の縄という神通呪力とその光明は、八つの交道の交叉する国土の中央仏塔、本仏お釈迦さまより発せられているものであり、またそのお釈迦さまに帰納しているものであることを忘れてはなりません。
ところで、何故、八つの交道の両側に、わざわざ黄金の縄をもって境を作ったのでしょう。現在インドの道路の両側には樹木がうえられ、昼の炎暑をさける涼しい木陰をつくっています。古代より為政者は、道路には樹木を必ず植えて、交通の便をはかったものです。然し、インドの何処を歩いても、道路の両側に縄を張り廻らして境を作っている処はありません。では、この縄というのは、一体、何を意味しているのでしょう。
ここで思い起こされるのは、不動明王や不空羂索観世音菩薩や降三世明王などの密教系の菩薩や明王の手に持っている索縄です。この索縄が、インド古代のヴァルナ神をはじめ他の多くの神々の呪力をあらわすものから引用されたものであることはいうまでもありません。
ルーマニアの宗教学者ミルチヤ・エリアーデ博士、その著作集第四巻「イメージとシンボル」(せりか書房出版、前田耕作訳)の中で、「縛(いまし)める神と結び目のシンボリズム」と題し、一二七頁から一六三頁にかけて索縄にシンボライズされた意義を究明し、その冒頭(一二七頁〜一二八頁)に、デュメジル氏の説を紹介しながら、次のように述べています。
デュメジル氏がインド・ヨーロッパ神話の「恐るべき至上者」に帰属させている役割は、よく知られている。すなわち、一方で至上権の内部そのもので彼は司法の至上者と対立する。ヴァルナはミトラに対立し、ジュピターはフィデースに対立する、他方では、いつも軍事的手段によって戦う軍神たちに比定される「恐るべき至上者」は、いわばもうひとつの武器、つまり魔術の独占権をもっている。
「それゆえ、ヴァルナをめぐる戦争の神話というものはない。それにもかかわらずヴァルナ神は神々の中で最勝のものである。彼の最大の武器は〈アスラのマーヤ〉[魔族の幻力]であり、その魔術は形態と魔力の至上の創造者としてのものである。そしてそれこそ彼をして世界をとりしまり、安寧を保持することを可能ならしめるものなのだ。
そしてこの武器は大抵、紐とか結び目とか、実物である場合もあるし、こしらえものである場合もあるが、いずれにせよ綱という形で表されている。これに対し、軍神であるインドラは戦う神であり、雷霆[金剛杵]をもてる神であり、無数の決斗と、どんな危険をも物ともせず、勝利をあらそう英雄である」
同じ対立関係はギリシャにもみられる。すなわち、ゼウスが戦い、困難な戦争を続行するのに対して、ウーラノスは戦わない。彼は諸王の中で最も恐ろしく、いちばん王位を剥奪することがむづかしい王でもあるけれど、彼をめぐる伝説の中には、彼が戦ったという痕跡はない。仕損ずることのない捕縛によって、彼は彼の不慮の、とはいえ、なかでも特に屈強な敵を金縛りにし、雁字搦めにし、地獄につないでおく。
即ち、索縄というものは、軍神の戦う金剛杵に対するもので、戦わずして適する者や不正の者を呪縛する呪力を象徴するもの、といえるのです。エリアーデ博士は、更にデュメジル氏の説を紹介しながら次のように述べています。
ヴァルナは手に一本の縄索をもつ姿で表象されている。そして祭儀において結び目をはじめ、縛るものならどんなものでもヴァルナ風とよばれるのである。デュメジルは、この気高き撃縛者の呪術的稜威を、ヴァルナの統治権に帰している。
「ヴァルナの縄索もまた、統治権そのものが、そうであるように、呪術的なものなのだ。つまり縄索は、法の運営、行政、王権と民衆の安寧、〈権力〉と呼ばれ、族長によって保有されるあの神秘的な力すべての象徴なのである」(ウーラノス=ヴァルナ、五四頁)
このことは、まこと正鵠を射た指摘である。
ここにいう「族長」とは、種族や部族の長であり、同時に神秘的な呪力をもった司祭でもあるのです。若し、この族長を転輪聖王におきかえるならば、転輪聖王は仏法をもって国家行政を司るばかりでなく、族長の如き神秘的偉大な呪力をともなって行政する大王と申されましょう。
すると、仏国土の中の八つの交道の沿道両側に張られた「黄金の縄」とは、単に道路の境を明示したものでなく、転輪聖王の偉大なる呪力を象徴し、武力によってでなく、その仏法と呪力とによって、「法の運営、行政、王権と民衆の安寧」の十全なることを現したものと申されましょう。
通常、転輪聖王は、武器をもって戦うことなく、威徳をもって四天下を統治するものといわれて来ました。その威徳が、偉大な神秘的呪力として「黄金の縄」に象徴されているのです。
仏法に適する一切の悪、一切の魔を呪縛し、また却って魔人の縛を解くものこそ「黄金の縄」と申されましょう。従って仏国土には、いささかの悪、いささかの魔さえも、その存在を許さない呪力が満ち満ちているといわなければなりません。
大迦旃延の建立する仏国土に、
四悪道の地獄・餓鬼・畜生・阿修羅道なく、多く天・人あらん。
といい、大迦葉の建立する仏国土に、
その国の菩薩、無量千億にして、もろもろの声聞衆またまた無数ならん。魔事あることなけん。魔および魔民ありといえども、皆、仏法を護らん。
というのも、神通呪力のいたす処と申されましょう。
二乗の建立する未来仏国土を、このように解釈してみると、その浄土はメルヘンの世界ではなく、あくまでも具体的な現実の浄土であり、二乗が地涌の自覚に立つに至る時、その未来浄土は、末法娑婆世界において地涌の菩薩によって建立される仏国土の中に移されることになる、と言い切ることが出来るのです。
また末法娑婆世界に出現した地涌の菩薩にしても、その建立すべき仏国土の軌範の一斑を、二乗の浄土の様相に学ぶことが出来る、ともいえるのです。
○仏陀の右手、施無畏の印
前回「契約と授記」について述べる中に、仏陀の右手の施無畏の印相は、もともと授記の相を示すものであり、その原型は、バール神やその配偶女神の誓約・契約をあらわす右手の掌であったのではないかと推測し、更に燃灯仏をはじめガンダーラ仏像やマツウラ仏像の中に、右手をあげ、左手は衣の裾を軽く握っている姿と全く同じ姿の女神像が「NHK未来への遺産取材記」の中に紹介されていたことを思い出して、その女神が、バール神の配偶女神アスタルテであったならば大変なことであるから、その女神の名を確かめねばならない、と記しておきました。
前回、その辺の執筆は九州上野峡道場であったため、肝心の資料がなく、記述も正確を期すことが出来ませんでした。三月下旬、九州から東京へ上がり、東京から身延へ上がったのは四月七日でした。さっそく「NHK未来への遺産取材記、壮大な交流」をひもといてみますれば、仏陀の如く右手をあげ、左手で着物の裾を軽くにぎって立っている女神は、幸い、アスタルテではなく、「ハトラの女神」といわれるものであったことが確かめられたのです。
「ハトラの女神」については、NHK取材記者佐々木正則氏が「壮大な交流」(一七六頁〜一八七頁)に、取材記事を述べていますので、その中の必要な点だけ抜粋して紹介してみましょう。
イラクの北部最大の都市モースルから南へ二時間、幹線道路を首都バグダッドに向かうと、広漠たる砂海の真ん中に岩礁のような廃墟が見えてくる。シルクロードの拠点の一つハトラの遺跡である。(中略)
ハトラは、シリア北部および小アジアから中央イラク、ユーフラテスとチグリスに並行して走る二つの主要な隊商路を、危険から防備するための要塞であったと言われる。この大規模な要塞は、北、西からのローマ侵攻をくいとめるための重要拠点となった。
当時、ハトラ商人のキャラバンは、中国の商品、インドのスパイス、絹、宝石、セルシアとナシビアからの木製品を商い、西方のアンティオクよりのヨーロッパ人とも広く交易をしていた。このハトラが、いつ頃、誰によって建設されたのかという点については、確たる証拠はない。多分、紀元前一世紀頃に、アッシリア時代の小さな砦が発達したものであろうとされている。
その後、ハトラは独立して北部メソポタミアを支配したアラブ王国(パルティヤ)の一王都になった。そして、以後二〇〇年間にわたって、アラブの部族、僧王、首領、司祭などによって支配された。
イラク考古局の手によって一九六一年に解明されたアラム語の碑文の記述に「アラブの王・サナトラックの名は、彼の父である偉大な聡王・ナスルによるものであり、彼自身は、彼の先祖を祠ったシャマシュ寺院に祠られている」
とあったことから、サナトラック王が王朝の最初の王であったとされている。
サナトラック王によって建造された要塞都市であり、隊商都市でもあったこのハトラの遺跡の建築群は、すべて石灰石と石骨によって建造されている。(中略)
寺院群は、(中略)東の正面に向いてマラン寺院があり、右側(北)にミトラ寺院、左側(南)にトリニティ寺院、西側にマラン本院といわれるシャマシュ寺院がある。(中略)
マラン寺院は、「太陽の神・シャマシュ」のもとにある「ハトラの女神たち」の寺院の中でも、もっとも権威ある寺院と言われている。(中略)
マラン寺院の裏側にサヒル寺院がある。この寺院は、あの巨大な列柱で知られるレバノンのバールベックのバッカス神殿を小規模にした感じであり、様式もローマ風である。
以上は、ハトラ遺跡の説明ですが、肝心の「ハトラの女神」については、次のように述べられています。
まるで万博の会場のように、異質な建築群が存在を競い合っているこのハトラの様相を、さらに際立たせているのが、付属装飾としての彫刻、彫像群である。(中略)
彫像群の中でも、特筆されるべき彫像が、シャマッシュ本院の前庭に安置されている。「ハトラの女神」と呼ばれているこの石灰石の彫像は、高さ約二・五メートルの女性立像である。特に秀れた彫像ともみえないこの「ハトラの女神像」が、ことさら興味をかきたてるのは、その独得のポーズと衣裳によってである。
左手を前におろし、指先でそのギリシャ風衣裳を軽くつまみ上げ、右手は開いて肩のあたりまで上げている。このように奇妙なポーズをとった人物像は、同時代のものとしては稀有の珍品としか考えられない。
神を具象化することに卓越した技術をみせた古代ギリシャの文化と、時あたかも仏教時代の幕開けにかかっていた東洋の精神文化とが、その中間点に位置するハトラで、きわめて曖昧な出会いをしていたのではないだろうか。
当時、ヘレニズムは、すでにアレクサンダー大王の東征によってパキスタンまで進出、ガンダーラ地方に拠点をおいて発展していた。通説に従えば、その秀れた写実的彫像の技術は、やがて東洋人をみずからの神の具象化へと向かわせていった。仏像の誕生である。
しかし、このハトラでは、彫像が宗教と結合することはなかった。彫像は実在の人物の写しである。その中で、この「ハトラの女神」は唯一、神を具象化したものであるといわれているし、それ故にこそ特異な存在とされているのである。
ところが、イラク国立博物館に陳列されているハトラ出土のサナトラック王一家の彫像群を見ると、王妃と「ハトラの女神」とは、同一人物と見間違うほどに、よく似ている。
だが、ここで、「ハトラの女神」が「実在の人物の彫像ではないか?」という新説を展開するつもりはない。オリジナルなイメージなどというものは、そう安直に思い浮かぶものでもないし、具体化するものでもない。まして古代の人々が尊崇の念で見上げる女神像が、実在の高貴な人物の形を借りてしまうのは、至極当然のこととも考えられるからである。(中略)
公共道路跡を東門に向かって歩いていくと、かつてこのハトラが、砂漠の小さな砦として誕生し、やがてシルクロードのオアシスとして栄えたという史実が、実感となって迫ってくる。
地理的には西方に近いということもあって、東方の影よりも西方のそれが色濃く残っているとはいえ、このハトラは、オリエント、西方、東方文明の、貴重な展示場の役割を果たしていたオアシス都市であったのである。
しかし、紀元一世紀末から二世紀にかけて、ハトラは見棄てられてしまった。その原因は不明である。このころ、相前後して放棄されていったヨルダンのペトラ、シリアのパルミュラなどの衰亡と共通した原因があるのかもしれない。
NHKの海外遺跡取材記者佐々木氏は、「ハトラの女神」について、「このような奇妙なポーズをとった人物像は、同時代のものとしては稀有の珍品としか考えられない」と述べていますが、それは勿論、仏像を抜きにした上での説でありましょう。
前にも述べましたように、アフガニスタンの燃灯仏をはじめガンダーラの仏像の中にも、マツウラの仏像の中にも、この「ハトラの女神」と全く同じ右手、左手の相をした仏像は、決して少なくはないのです。
むしろ私は、「ハトラの女神」の像を原型として、そうした仏像が造形されてきたのではないか、とさえ思えてならないのです。そのため佐々木氏の取材文章を、長文にわたるも臆せず、要点抜粋して紹介してみました。
これによれば、ハトラの城塞都市は紀元前一世紀から紀元後二世紀にかけて栄えていたといわれていますが、その当時のハトラは、アルサケス王朝パルティヤ帝国の領土であり、ユウフラテス河を境としてローマ帝国に隣接し、ローマ軍団に侵入にそなえた重要な要塞でもあったのです。
パルティヤ人はイラン高原より南下して来た遊牧騎馬民族でした。特に馬を疾走させながら、騎上、後ろむきに矢を射る曲射りを特技としていました。その歴代王朝は、遊牧民族らしく首都を転々として変えていました。ハトラもその首都の一つであったのです。
イラク考古局の碑文解読によれば、ハトラに首都をおいたのはサナトラック大王であるとされており、これによって佐々木氏も「サナトラック大王が王朝の最初の王であった」と述べているのですが、足利惇氏博士の著「ペルシャ帝国」の中に掲げられたアルサケス王朝歴代の皇帝の人名表の中には、サナトラック王の名前は見出されないのです。当時の皇帝は、一人で幾つもの名称をもつのが通例であったのですから、足利博士の表の上では、サナトラック王は異名であげられているのかも知れません。
問題は、そのサナトラック王の王妃の像と、「ハトラの女神」の像とが、殆ど同じ姿をしているということです。然し、それはパルティヤ歴代の皇帝に、ティリダーテスとかミスラダーテスといった神名を冠した王名が多いといったことによっても、容易に解釈されることでありましょう。
即ち、国王が一国と大司祭として神名を称するならば、その王妃もまた女神より神任されたものとして、女神に最も近い者とされましょう。或はその王妃は、女神地母神をつかさどる巨大なシャーマンであったのかも知れません。このため必然、「ハトラの女神」の像と、王妃の像とが全く同じ姿として彫像されたのかも知れません。
ハトラは要塞都市であるばかりでなく、シルクロードの重要なオアシス都市であり、国際的な通商都市でもありました。ヘレニズムの東漸の波に乗って東西文化が交流し、仏像の造立に当たって、「ハトラの女神」と全く同じポーズをした燃灯仏やお釈迦さまの仏像が造形されたことも当然考えられることです。
時代も全く同じ時代であり、そのポーズが他に類のない独得のものであるのみならず、女神像と王妃の像とが同一であるならば、それと同じ仏像を造形することは、パルティヤ領土内に仏教を宣布する上に、より便利であり、より効果があることは火を見るより明らかな処であった、と申されましょう。
女神像を原型として、それと全く同じポーズの男性仏像を造形することには、現代人としては、いささか躊躇を覚えしめられましょうが、当時の仏教徒には、お釈迦さまの本生譚として、お釈迦さまが前世において婦人として菩薩行を行じたという神話がそのまま史実として信じられていた以上、なんら抵抗を感じるものではなかったのではないでしょうか。
はじめ私は、燃灯仏が儒童菩薩(メーガ青年)の敷いた鹿皮と儒童の髪の上を歩かれる時、その敷きものの下のぬかるみのはねあがりを避けるため、左手で衣の裾を軽くつままれたのではないか、そして燃灯仏の授記物語を主題として、そのようなポーズをされた燃灯仏の仏像やお釈迦さまの仏像が造形されたのではなかったかと思ったことがありました。
然し、すぐ後で「ハトラの女神」のポーズを思い起こした時、大乗教徒は燃灯仏授記の所作と、この女神像のポーズの相通ずる処から、女神像を原型として、そうした仏像が造形されたのであろう、と思い返したのです。おそらく大乗教徒にも、こうした心の動きがあったのではないでしょうか。
ともあれ肝心なことは「ハトラの女神」の掌を前にして肩まであげた右手のポーズです。このポーズはラス・シャムラより出土した紀元前十三世紀の「男神バール像」と全く同じものであり、このバール神像を紹介した「古代シリア展」のカタログには、同所出土、同時代の「女神アナト像」も掲載されていましたが、アナトもまた同様のポーズを示していました。
いうまでもなく女神アナトは、バールの配偶神であり、バールの敵モトと戦って勝利を得た勝利の女神であり、バールを死より復活せしめ、バールと結婚することによって大地の豊饒をもたらす大地母神なのです。
バールとアナトという男女双神が、共に右手を肩まであげ、掌を前にしているポーズは、供犠儀礼をもって大地の豊饒を願う民衆に対して、その豊饒を誓約し契約し、またはそれを保証することを象徴するものでありましょう。
そうしてハトラの女神も、おそらくアナトと同じ系譜の大地母神であり、その全体の姿がパルティヤ王妃と全く同じ相を示しているところから、この女神は、王権の権力さえたずさえた強大な女神であって、その右手のポーズもまた、民衆の絶対服従に対して、豊饒を約束し、その真実を保証することを象徴するものと申されましょう。
すると、これらのポーズを原型とした仏像の右手の施無畏の印相は、仏教の内では、仏陀の無畏の精神をさずけるという意味に解釈されて来てはいますが、本来は民衆の菩薩行の誓願に対して、未来、必ず成仏することを誓願し、契約し、その真実を保証するという、いわゆる授記を象徴するものであった、ということが出来るのです。
日本大学芸術学部講師の並河亮博士は、その著「仏像のながい旅路」(六五頁)に、如来の印相を次のように説明しています。
シクリ・ストゥパの浮彫りで見たのは「施無畏印」であった。右手を開いて、手のひらを外へ向けて、肩のあたりにあげる。「畏れることはない。来れ」の意味である。立像のばあい、左手で衣の端を握るのが多い。
次に「説法印」(「転法輪印」ともいう)である。両手を胸のあたりにあげて右手の手のひらに着くようにする。釈尊が説法するときの印相である。
次に、「禅定印」は「法界定印」ともいう。両手の五指を伸ばして左手の五指を下にして重ねる。釈尊が瞑想しているときの姿勢である。
「施願印」(施与印」ともいう)は、右手を開いたまま垂れ、手のひらを外に向ける。「あなたを護る」という意味で、立像に多い。
「触地印」は「降魔印」とも呼ばれる。右手を垂れて、座を指で触れる。釈尊が悪魔を払う姿勢である。
この中で博士は、「施無畏の印」を「畏れることはない。来れ」という意味であり、「施願の印」(或は「与願の印」)を「あなたを護る」という意味であると解釈されていますが、全く恐れ入った俗説にすぎません。多分、「無畏」という文字から「畏れることはない」と訓じたのでしょうが、本来、無畏というのは獅子王の如き仏陀の境地をいうものであって、「施無畏」ということになれば、そういう仏陀の果上の一切の功徳を与えるという意味になるのです。
これに対して「与願」というのは、如来の本願を下種するということであって、如来の一切の因行の功徳を与え、衆生をして如来の菩薩行に立たしめるという意味になるのです。
初期の仏像には、必ず「施無畏の印」はあっても、「与願の印」をともなったものは多くはなかったのですが、やがて阿弥陀如来のように「施無畏」と「与願」の両方の印を示す仏像も一般化して来ているようです。
阿弥陀如来の場合、「与願印」は弥陀の四十八願の功徳を与え、「施無畏印」は西方安養極楽浄土の往生成仏を保証するという意味になりましょう。この両印を法華経本門の立場で解釈するならば、両印をあわせて本仏お釈迦さまの因行果徳の一切の功徳を、妙法蓮華経の五字にこめて衆生に授与し、衆生をして題目色読の実践に立たしめ、地涌の菩薩道を行ぜしめるということになりましょう。
然し、「施無畏印」の原型が、バールやアナトや、ハトラの女神といった中近東の原始的土着宗教の神像の右手のポーズより由来したものであり、誓願・契約・保証といった意味を、燃灯仏の授記の相に用いたものであった、ということを忘れてはなりません。施無畏という意義は、仏像のそうした右手の印相が出来上がって後、仏教的に意味づけたものにすぎなかったのです。
恐るべきことは、前にも一寸と触れましたように、日蓮大聖人に強烈な契約思想があったということです。大聖人がその生涯を賭して如何なる法難にも屈せず、弟子壇越の離散をも恐れず、法華経の宣布に挺身されたのは、実に久遠の本仏お釈迦さまと霊山虚空会上にかわした契約を守り抜くということにあったのです。
この契約を、法華経如来神力品においては別付嘱と申しているのですが、付嘱というものが、本来、本仏お釈迦さまと地涌の菩薩との間に堅くかわされた契約によって成立しているということを見抜かれた大聖人の 眼の鋭さ、その卓絶した洞察力というものには、ただただ驚嘆するほかはありません。
眼の鋭さ、その卓絶した洞察力というものには、ただただ驚嘆するほかはありません。
仏滅後、印度・中国・日本と仏教の東漸に従って、法華経の勝れた教義を講鑚した高僧は数知れないほどですが、彼等の殆どは、法華経の付嘱を表面的に見て、仏勅ぐらいにしか解釈しておらず、付嘱そのものが契約によって成立しているという文底の意義を見抜いた者は殆どありませんでした。まして迹門の授記思想が、本門の付嘱段において摂取完結されていることを見届けられた人は、全くなかったと申されましょう。
迹門の授記思想にしても、表面上は民衆の未来成仏を印可し、その成就を保証するということであっても、その授記を成立せしめるものは、生々世々、萬億の諸仏(久遠の本仏お釈迦さま)に親勤し給仕し、供養・讃嘆して、ただひたすらに一仏乗を専修するという衆生の誓約が、本仏お釈迦さまによって受領されたことによるものでした。
若し、衆生の誓約もなく、お釈迦さまの受領がなければ、授記は成立されなかったのです。本門の付嘱においても、それと同様のことがいえましょう。地涌の菩薩は、久遠劫来、ただひたすらに一仏乗を専修し、仏滅後の末法娑婆世界において、一仏乗を宣布すべき時期の到来を待機していたのですから、付嘱に当たって、改めて、一仏乗の受持・宣布を誓約する必要はありません。
では、如来神力品の別付嘱においては、何を誓約したのか、本仏お釈迦さまと如何なる契約をかわしたのかというならば、末法娑婆世界に法華経を宣布流布して仏国土を建立するということ、仏国土を建立するまで一乗宣布に身命を捧げぬくということ、いいかえれば娑婆仏国土の成就するまでは、みずから仏陀の身にはならない、成仏しない、ということなのです。
如来神力品の別付嘱の相をみれば、在々処々において一仏乗を受持・読誦・解説・書写・供養し、本尊仏塔を建立せよ、と仰せられているのみであって、改めて仏国土を建立せよとは申されておりません。
然し、一仏乗を受持宣布し、本尊仏塔を建立する処は、
諸仏、ここにおいて阿耨多羅三藐三菩提を得、
諸仏、ここにおいて法輪を転じ、
諸仏、ここにおいて般涅槃したもう
という諸仏(本仏お釈迦さま)常住の仏国土なのです。迹門の二乗声聞に対してそれぞれ仏国土建立が授記されていながら、地涌の菩薩に仏国土建立の付嘱がなされないはずはありません。
今、如来神力品の別付嘱の段を、よくよくふりかえってみるならば、起塔供養の仏勅の方が、法華経の受持宣布の勅命よりも、より比重をかけて述べられていることに気付くことでしょう。
ところが、この起塔供養の本尊塔こそ、仏国土を象徴する方形基壇の上に、半円球の仏舎利塔を建立した一閻浮提の中心軸となっているのです。如来神力品の別付嘱では、本尊としての本仏お釈迦さまの仏像を建立せよとはいわず、本尊塔を建立せよと仰せられているのに注意しなければなりません。この塔基壇に、仏国土建立が象徴されているのです。
大聖人が観心本尊抄に、
この時、地涌千界出現して、本門の釈尊の脇仕となり、一閻浮提第一の本尊、この国に立つべし。
と仰せられ、一尊四士本尊の造形に当たって、四大菩薩を本仏お釈迦さまの四方東西南北に配座せしめた処に、既に仏国土建立を表現されていると見ることが出来ましょう。大聖人図顕の大マンダラもまた四天王を東西南北に配置し、大マンダラ全体が宇宙大の仏国土であることをあらわしているのです。
神力別付嘱は、娑婆仏国土建立という地涌の菩薩誓約、仏国土建立が達成されるまでは生々世々に一仏乗を受持宣布し、本尊仏塔を建立し供養しつづけるという誓約、その日の到来までは菩薩にとどまって仏身を成就しないという誓約、こうした厳しくもすさまじい誓約を、本仏お釈迦さまが嘉納された上で、改めてそれを勅命し、諸仏も迹化の菩薩も諸天も、その聖業を助けて、行者を擁護するという誓約をかわしあう処に成立しているのです。大聖人の国神諫暁も国家諫暁もここに起きて来ているのです。
大聖人ほど契約に生きた高僧はいないでありましょう。大聖人にあっては、もはや未来成仏の保証など、もはや眼中になかったのです。成仏の保証を確認することよりも重大なことは、本仏お釈迦さまとの契約を守り通すということであり、守り通せるかどうかということの方が問題であったのです。
般若系の大乗教徒から、癈種・破石・未来永劫不成仏の烙印をおされた二乗声聞たちにとっては、未来成仏の保証をあらわす授記は重大なことであり、欠くことの出来ないことでした。然し、それでも成仏の保証を得るには、未来永劫にわたって一仏乗を専修するという不退転の誓約を必要としました。
二乗声聞の場合、保証が表となり、誓約が裏になっていました。これに対して地涌の菩薩の場合、契約が表となり、保証はもはや必要ではありませんでした。未来成仏出来るかどうかを懸念し、必ず成仏することが出来るという保証を必要とするようでは、地涌の菩薩ということは出来ないでありましょう。
地涌の菩薩が本仏お釈迦さまの脇仕である以上、既に成仏は決定しているのです。題目受持の当処、常に本仏お釈迦さまと共に、久遠常住の浄土の内に住しているのです。
観心本尊抄に、
今、本時の娑婆世界は、三災を離れ、四劫を出でたる常住の浄土なり。仏既に過去にも滅せず、未来にも生ぜず、所化もって同体なり。これ即ち己身の三千具足、三種の世間なり。
という、所謂「四十五字法体段」は、大聖人にとって未来達成されるであろう理想的境地ではなく、日常、題目を受持する当処に顕現されていた仏国土であったのです。そこで開目抄に、
我が身、法華経の行者にあらざるか。
日蓮が法華経の行者ならざるか。
日蓮、法華経の行者にあらざるか。
という厳しい自問自答の繰り返しは、自分自身の未来成仏・来世成仏に対する危惧より起こったものでなく、実に本仏お釈迦さまとかわした契約を十全に履行しているかどうかということを、自分自身の身にあて、反芻すると共に、大聖人に続く弟子壇越に対しても、その厳しい反省を、自分の身をさらして要求している言葉である、ということが出来ましょう。
然し、大聖人の壇越へ与えられたお手紙の中には、未来成仏疑いなし、と励まされた文章も少なくはありません。それによっても、大聖人の直壇の中でさえ、成仏の保証を求めるような低い法華経信仰者もいたことがうかがわれます。
ところが話にもならないのは、現代日蓮門下の僧俗の中に、契約の履行に欠けることを危惧する者も少なく、未来成仏に関する関心もない人々が、あまりにも多いということです。こういうことでは表面は殊勝げに法華経を信仰している風であっても、内実は、ただ信心ごっこのような信仰遊技に明け暮れているにすぎません。
汽車や電車に乗っても、乗りあわせている人々の顔を眺めては、この人たちが法華経の信仰をしているかどうかと思ってみることがあります。毎月一度は身延山へ参拝するのが、私の月例コースの一つになっていますが、遠路はるばる身延山に参詣され、或は七面山へ登詣されている多くの人々の姿に接するにつけても、これらの人々の中に、本仏お釈迦さまの契約に生きぬこうとしている人が、果たして幾人いるのだろうか、と考えさせられることもあるものです。
然し、そんなことを、どんなに思いわずらっても仕方ありません。思いわずらうよりも、まず私自身が契約に生き、生涯をかけて契約履行に欠けることのないよう、心すべきでありましょう。たとえ、その成果がどのようであろうとも、常に、そういう反省を重ねて努力を積み重ねて行く生きざまにこそ、法華経の行者としての生き方があり、大聖人の門人としての生き方がある、と思うのです。
文永八年十月二十日、佐渡配流の途中、越後の寺泊に着かれた大聖人は、翌る二十一日、中山の富木入道へ遣わされた「寺泊御書」の中に、
法華経は三世説法の儀式なり。過去の不軽品は今の勧持品、今の勧持品は過去の不軽品なり。今の勧持品は未来の不軽品たるべし。その時、日蓮は即ち不軽菩薩たるべし。
という有名な一句をしたためられました。古来、日蓮門下の人々は、不軽品の色読、勧持品の色読というものを、大聖人にしてはじめて可能であったと思い、末学の者には到底色読し難いものであるかのように思いこむ傾向がありました。この傾向は現代一層濃厚のように見うけられますが、法難忍受は、退くことの出来ない契約に生きる者には必然起きて来るものであって、身にうけた苦難・法難というものは、堪えようとすれば堪えられるものです。
むづかしいのは、苦難に堪えるということよりも、誓願・契約に忠実であるということです。若し、それに忠実であるならば、忍難は却って法悦を増すものとなりましょう。不軽品や勧持品に示されている忍難弘教の実例は、一人大聖人のみ実践されたのではなく、仏滅後、法華経々典の編纂されるまでの間においても、私たちの先祖において実行された実録でもあったのです。
常不軽菩薩の自覚と歓喜に燃えたのは大聖人一人ではありません。法華経の血脈に生きた私たちの先祖の多くは、この自覚に燃え、歓喜に沸いていたのです。私たちは先祖の体験した苦難・法難を追体験するのではありません。先祖の歩いた足跡を踏んで行くのでもありません。先祖が命にかけた守りぬいて来た本仏お釈迦さまとの契約を、先祖の如く忠実に命をかけて護りぬいて行くのです。
過去の足跡を未来へついで、仏国土建立の新しき歴史創造へ、一歩を踏み出すのです。生涯をかけて踏み出した足は、ただの一歩でもいい、しっかりと大地にその一歩の足跡を印すことです。千里の道を歩こうと思ってはなりません。千里も一歩からです。その一歩が千里を照らすのです。名もなき老婆の一歩もありましょう。私のこのプリントもその一歩でありたい、と願うものです。
思うに契約思想というものは、インド仏教本来のものでなく、むしろミスラ教やゾロアスター教、或は中近東一帯の原始的土着の地母神信仰といった、そういう宗教の中の潮流でした。それが仏教の中に摂取され、やがて法華経における地涌の菩薩の使命感を奮い立たしめる不退転の思想として昇華するに至るのですが、その始めは、西北インドを第二の根拠地とした仏教を衝撃した西方のそれらの宗教との戦いの中に、燃灯仏の授記物語をはじめとする誓願授記思想が興り、これにあわせて仏像の造立に当たって、バールやアナト、或はハトラの女神といった西方の神々の、大地豊饒を誓約し契約する右手のポーズが、そのまま仏像右手の施無畏の印となり、その印が、西方の凄惨な供犠に代わる捨身の菩薩行の誓願を納受し、未来の衆生成仏と仏国土建立との授記を意味するようになったことに端を発していると思えるのです。
然し、法華経の本門に至って、迹門で最高潮に達した授記思想が、本門の法華経付嘱の内に摂取完結され、本仏因行の本願が地涌の菩薩の本願となり、授記の保証が契約に代わった時、必然、仏像の右手の施無畏の印に変化が起こり、本仏お釈迦さまの常説法教化される相をあらわす説法印が定着するようになって来たのではないか、と思われるのです。
〈「五百億塵点劫来の因果」は次回とします〉
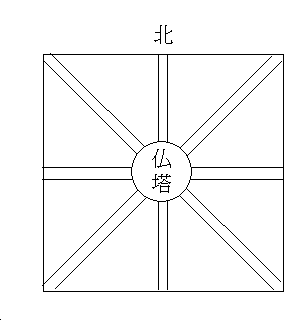
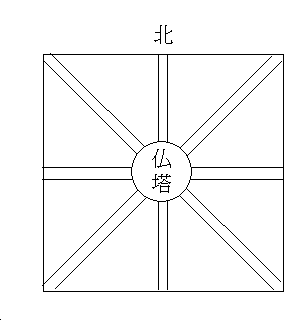
.gif)
.gif)
.gif)
.gif)