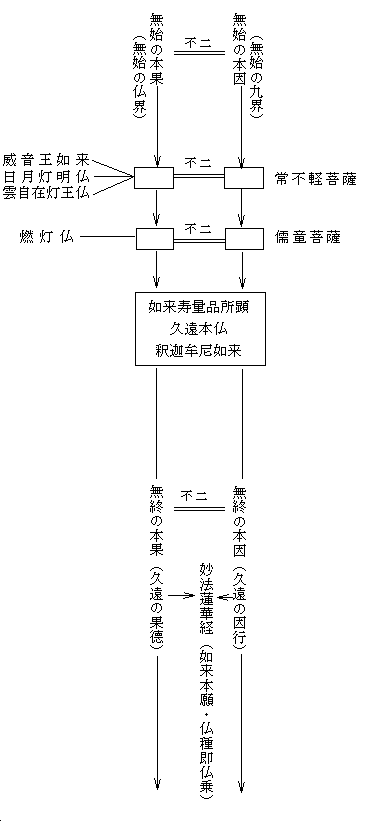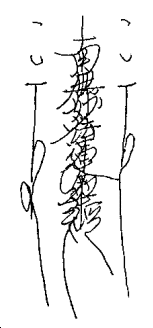自我偈の結びの経文は、有名な次の一句です。
毎自作是念 つねにみずから この念をなす
以何令衆生 何をもってか 衆生をして
得入無上道 無上道に入り
速成就仏身 すみやかに仏身を成就することを得せしめんと
建暦二年(一二一二)、法然念仏を攻撃するため「摧邪輪」を著した栂尾の明恵上人は、華厳の学匠でありながら、法華経を読誦する中、自我偈のこの文に至ったとき、生身のお釈迦さまの大慈悲にうたれて感泣し、暫し、経文を読むこともできなかったといわれています。
これは明恵上人の伝記の中でも有名な逸話ですが、法華経読誦のさなか、本仏お釈迦さまの衆生を護念されてやまない大慈悲に感動し、あふれる涙に経文を読むこともできなかったという体験は、一人明恵上人だけに限らないでありましょう。日蓮大聖人も佐渡塚原の三昧堂の内で、
現在の大難を思い続くるにも涙、未来の成仏を思うて喜ぶにも涙せきあえず。
鳥と蟲とは鳴けども涙落ちず、日蓮は泣かねども涙隙なし。
この涙、世間のことにはあらず、ただひとえに法華経の故なり。
若し、然からば甘露の涙ともいいつべし。
と仰せられています。おそらく大聖人の生涯、開いた経品を涙にぬらし、あふれる涙を黒染めの衣の袖でぬぐうことは数知れずあられたことでしょう。記録こそなくても、大聖人の門人の中でも、そういう経験を経た人は、数限りなくいたことと思われます。
私のような者でも、自我偈の冒頭
常に法を説いて、無数億の衆生を教化して、仏道に入らしむ。しかしよりこのかた無量劫なり。
という一句に至って、号泣久しくしたことがありました。私自身が、その「無数億の衆生」の中の一人であったのだ、と思われてならなかったからです。
昨年の暮れの十二月八日、千葉県下から川嶋本良師、町行象師、京都から助川円竜師をはじめ若干の人々が、身延の釈迦牟尼堂につどい、鷲峰プリントをテキストとする勉強会を開くに当たって、お釈迦さまの成道会を厳修しましたが、その法要中、読経もすんでお題目を唱えるさなか、思わず胸がつきあげられ、感涙のあふれて、お題目の声も暫く出せないことがありました。
それは、今、私が唱えているお題目こそ、本仏お釈迦さまの因行果徳の二法の相即完備するものであり、その久遠の因行をたずぬれば、お釈迦さまが常不軽菩薩として街頭罵詈打擲されたのも、また今生、ブッダガヤの尼連禅河の東北方、岩だらけの前正覚山中、ミイラの如くやせ細ってまで難行苦行されたのも、実に娑婆末法の衆生、私が如き者のためであり、今、私に、かくの如くお題目を唱えせしめんがため、あの数知れない捨身供養の難行がなされたのだ、と思われてならなかったからです。
私は二度目のインド仏蹟巡拝旅行の折り、幸いにして前正覚山に登り、お釈迦さまが苦行されたと伝えられている留影窟の内に入り、お題目を唱える機会に恵まれたことがありました。故に、去る十二月八日の成道会の唱題中、留影窟を中心とする前正覚山の風光、素足で渡った尼連禅河の砂原、そしてガヤ大塔西面の大菩提樹、樹下の金剛宝座、等々が走馬燈の如く思い起こされ、それらお釈迦さまの因行果徳が、そのまま口うつしに私の唱えるお題目として伝えられていると思い知った時、こみあげる感動をおさえることが出来なかったのです。
そこには、あたかもその日が釈迦牟尼堂開堂三周年に当たっており、また私が十九才のこの日、仏門に入って丸三十八年目に当たっていたという感激もあったのでしょうが、それよりも、私をして、このような感動に至らしめたものは、川嶋師・町師・助川師という志を同じくする青年層をはじめ、西君・安藤さんといった在家の方々まで、その数は少なくとも、遠路、成道会を期して身延の釈迦牟尼堂に集まってくれたという僧伽の尊さであった、と申されましょう。
僧伽、それは組織化されたものでなく、あくまでも自然涌出のものであり、僧伽の正純が、本尊と題目に対する信仰を相乗光顕し、お釈迦さま在世における霊山虚空浄土を末法娑婆の現実に実現せしめるのです。お釈迦さまの成道・説法・入滅の聖地が、題目を行ずる当処に復活し、法華経付嘱の風光までも眼前のものとして、仏滅後三千年の間閉ざされていた幕を開いて来るのです。大聖人は弟子一門の人々に対して、
在世は今なり。今は在世なり。
と励まされました。また「観心本尊抄」では、
在世の本門と、末法の初めとは、一同に純円なり。
とも仰せられ、更に、
仏の出世は、霊山八年の諸人のためにあらず、正像末の人のためなり。また正像二千年の人のためにあらず、末法の始め、予が如き者のためなり。
と激励されています。そこには、法華経の神力付嘱を、はっしと全身に受けとめられた大聖人が、付嘱の仏勅を遂行していく道程に於いて、二陣・三陣と大聖人につづく人々による従地涌出の本化の僧伽の実在を確信する感動がこめられていると見られましょう。
私たちは、一人でいる時、ややもすれば同じ処で足ぶみをし、やがてそこに自己満足して安逸に流れやすいものですが、善き友(善知識)のいる時、互いに刺激しあい、励ましあって、思いもかけない向上をとげることがあるものです。僧伽の尊さがここにもあります。帰依三宝は、あくまでも現実のものであらねばなりません。友がなければ、
森の中の象王の如く、独り行くがよい。
とお釈迦さまはすすめられましたが、独り行くその人の道念の沸る処、おのずから友もあらわれ、僧伽・僧宝も地上現実のものとなってあらわれて来るのです。但し、あらわれた僧伽を組織化して、これに依存しようとする時、仏法がゆがめられて来ます。僧伽は敬うものであっても、頼るものであってはならないのです。僧伽による仏国土もまた、敬うものでこそあれ、そこに安住すべきものではないのです。
若し、仮にも仏国土に安住したとするならば、その時、既にその人の菩薩行は退転しているでありましょう。菩薩行を退転するような安住の仕方であってはなりません。菩薩には、そういう安住の暇はないのです。むしろ菩薩道を行じていること自体が、既に仏国土に住していることなのです。
肝心なことは、僧伽の一人一人が、法華経受持の当処、本仏お釈迦さまと感応道交し、本仏の本願に生き、生かされているかどうかということです。本仏お釈迦さまと感応道交するということは、遙かに遠く離れて、相対峙していた私たちと本仏お釈迦さまとの間の距離が全くなくなり、父子あい抱擁するが如く、読経唱題の当処において不二相即するということです。
両者の間の距離がなくなるということは、自分の方からお釈迦さまの方へと、題目の飛行機に乗って飛んで行くのでもなければ、お釈迦さまの方から私たちの方へ飛んで来るのでもありません。無始久遠劫来、あたかも母親がそのふところに我が子を抱きしめていた姿、そういう親子一体の姿、蓮華の実と花弁とが不二相即しているし姿、そういう血のかよう一如の姿が顕発するということなのです。「縁起」といい「実相」というのも、この当処を除いては実在しないのです。
それには、まず自分自身が、法華経々典中の登場人物にならねばなりません。法華経二十八幕(二十八品)の舞台ドラマを、観客席に座って見つめていながら、如何にその劇に共感・感動し、万雷の拍手を送ったとしても、所詮、その場かぎりの観客の一人にすぎないのです。
お釈迦さまは、譬喩品の中で、私たちに対して、
今、この三界は、皆これ我が有なり
その中の衆生は、悉くこれ吾が子なり
と呼びかけられています。
この言葉は、お釈迦さまが実子ラゴラを慈愛されたように、一切衆生の一人一人を我が子としていつくしむお釈迦さまの大慈悲をうたいあげているものですが、またそれと同時に、観客席に居座っている人々をも、悉く法華経の舞台に引き上げて、仏子としての子役の自覚を、しっかりと言いつけている言葉とも申されましょう。
明恵上人は、法華経のドラマの劇中の仏子になって、「毎自作是念」というお釈迦さまの慈悲本願にむせびました。日蓮大聖人は仏子の自覚にとどまらず、遺使還告の勅使となり、その役を果たすべく、お釈迦さま在世の舞台を、末法の始めの舞台に移し、無始久遠劫来、前人未踏の地涌の菩薩の舞台をふまれました。そのドラマの中で、
「日蓮は泣かねども涙ひまなし」
という感動が、随時・随処に起きたのも、蓋し、当然であったことでしょう。
私たちも、法華劇中の一人として、その舞台に上がり、お釈迦さまが繰り返し、繰り返して私たちに呼びかけられているその呼びかけを、全身をもって受けとめなければなりません。それを受けとめる当処こそ、本仏感応の当処でもあるのです。
自我偈の始めに「常説法教化無数億衆生」といわれている衆生とは、遠い過去の名も知れない人々のことでなく、実は、今の私たちの過去の姿であったのです。また自我偈の終わりに「以何令衆生得入無上道速成就仏身」といわれている衆生もまた、遠い未来の誰とも判らない抽象的な人々のことでなく、実に今、末法娑婆世界に生きている私たちのことであったのです。
先の「無数億の衆生」という衆生とは、お釈迦さまが出現される以前、既に久遠の昔において、本仏によって「仏道に入らし」められていた人々であり、後に「以何令衆生」の衆生とは、お釈迦さまの滅後、なお無上道に入ることも出来ないでいる顛倒の衆生のことであって、この両者を表面上から見れば、時代も違い、信行も異なり、全く関係もない別々のグループと思われもしましょう。ましてこの両者が私たちの三世の姿を浮き彫りにしているとは、夢にも思われないことであるかも知れません。
若し、仮に、この両者が私たちとは何ら関係もない人々であるとするならば、自我偈は一体、誰のために説かれたのでしょう。たしかに自我偈(広くは如来寿量品)では生身のお釈迦さまの久遠実成が開顕されています。それは一切経中、未曾有の大法門であり、最勝の大法門としてたたえられて来ました。
然し、この大法門については、一仏乗を受持する本化の菩薩は、既に承知している処であり、これを知らない者、乃至これを信ずることの出来ない者は、本化以外の顛倒の衆生ばかりなのです。如来寿量品(自我偈)は、そういう顛倒の衆生に対して説かれたのです。
それは生身のお釈迦さまが久遠実成であるという理を知らしめるばかりのものでなく、本因本果不二の一仏乗に乗ぜしめ、因果不二の命、如来の久遠の本願に生き、生かしめんがためであったのです。
顛倒の衆生が一仏乗をたもつならば、本化の菩薩として蘇生します。本化の菩薩は、更に地涌の菩薩、仏勅付嘱の菩薩として、その使命に生きて行かねばなりません。ここに、久遠劫来、一仏乗を修してきた「無数億の衆生」も、顛倒していた「以何令衆生」の衆生も、共に私たちの三世の姿を浮き彫りにした姿である、ということが出来るのです。
注意しなければならないことは、曽って久遠の昔、一仏乗を専修していた本化の菩薩が、途中、退転して顛倒の衆生と化し、今生、再び一仏乗にめざめて、もとの本化の菩薩にたちかえるということではない、ということです。
では、どうして過去の本化の菩薩と、現在の顛倒の衆生とが連結するのか、というならば、一仏乗をたもつことによって、衆生本具の本化の菩薩身が顕発し、顕発した本化の菩薩身は、今、始めてその菩薩身を成就したのではなく、実は無量劫の昔、本仏お釈迦さまによって下種され、爾来、連綿として本仏お釈迦さまの下にあって一仏乗を修し末法娑婆弘教の時を待機していた歴劫久修の菩薩身であった、と開会されることによって、過去の本化の菩薩と、今の顛倒の衆生とが一体のものとして連結されるのです。
おそらく大聖人の上行菩薩の自覚も、そうであったのではないでしょうか。上行菩薩が大聖人として降誕したのでもなく、また垂迹したのでもなく、大聖人本具の上行菩薩身が顕現された、と見るべきでありましょう。
このことは、お釈迦さまの成道においても同様に言いうることです。久遠の本仏がお釈迦さまとして降誕したのではなく、お釈迦さま自身が本具の久遠の仏身を顕現されたのです。
私たちの成仏の場合でも、五十二位の段階を一歩一歩と登りながら、次第に仏陀として人格をそなえてゆくのでなく、本因妙の位にあって、因果不二の一仏乗を修する処、本因に即する本果の久遠の本仏お釈迦さまの仏身と相対照しあう衆生本具の仏身が顕発するのです。「得入無上道、速成就仏身」とは、このことでありましょう。
ここにいう仏身とは、今、はじめて完成された仏身ではなく、無始久遠の昔、既に完成されていたものであり、しかもそれは固定したものでなく、開三顕一の一仏乗をもって十方無尽に活躍されていた活仏であり、眼前する久遠実成の本仏お釈迦さまと、何ら異なることもない如来と申されましょう。
方便品の中に、本仏お釈迦さまの本願として、
我れ本(もと)誓願を立てて、一切の衆をして、我が如く等しくして異なることなからしめんと欲しき。
と述べられていますが、ここにいう「如我等無異」とは、本仏お釈迦さまと同じ仏身を成就する素質が一切衆生に内具しているという思考にもとずくものでなく、既に如我等無異の仏身が衆生己身中に本具しているという発想によるものです。
若し、如我等無異の仏身を成就する素質があるというのであれば、その仏身が成就された場合、仏身は今はじめて成就されたものであって、久遠の仏身ということは出来ません。久遠の仏身でなければ、如我等無異ということは出来ないでありましょう。
従って、「毎自作是念……速成就仏身」という仏身は、一切衆生に本具する久遠の本仏お釈迦さまと全く同一の仏身である、と申されましょう。
但し、この「速成就仏身」には「得入無上道」という大前提があるのです。この大前提を抜きにして「速成就仏身」ばかりを見てはなりません。仏身を顕発成就することは、まず無上道に入り、無上道を行じ、無上道を宣布する本化の菩薩行の結果にすぎないのです。
肝心なことは、この本化の菩薩道の遂行にあります。本化の菩薩は、神力付嘱の当初一仏一土の前提のもと、一天四海皆帰妙法、広宣流布、通一仏土の妙相成就するまで、その菩薩行を展開することを誓約しています。この誓約は通一仏土の暁までは、たとえ自力で可能であっても、仏身を成就しない、ということを裏書きしているのです。
だからこそ、お釈迦さまの本願として「速成就仏身」という「速」の一字が敢えて付けられているのです。この「速」の一字は、お釈迦さまが本化の菩薩の通一仏土の暁までは仏身を成就せずに菩薩行を遂行するという誓願・誓約を、あわれと思えばこそ、広宣流布、通一仏土の時の速やかに来ることを祈る「速」であるのです。決して個人個人の成仏の速やかであるようにという「速」ではないのです。この「速」こそ、本化の菩薩の誓願・誓約を、ただただあわれと涙する本仏お釈迦さまの、もだえるような祈りを、そのまま吐露しているものというほかはありません。
さて、ここで「毎自作是念」という本仏お釈迦さまの一念をふりかえってみましょう。一念といえば、日蓮門下の人々は、すぐ「一念三千」という言葉を思い起こすものです。ところで、一念三千の内容に関する教学的説明は、古来、まことに難解とされて来ていますが、大聖人は「一念三千」は十界互具よりこと始まる、と仰せられ、開目抄にも、
九界も無始の仏界に具し、仏界も無始の九界に備わりて、まことの十界互具、百界千如、一念三千なるべし。
と明示されているように、一念三千の骨目は、所詮、仏界と九界の不二相即、九一不二、因果不二をいい、具象的には蓮華の華果同時、本仏お釈迦さまと本化の菩薩との父子一体をあらわしている、と申されましょう。
勿論、ここにいう一念三千の一念とは、天台教学にいう衆生陰妄の一念ではなく、本仏お釈迦さまの一念であって、この一念に、九一相即し、因果相即しておればこそ、本仏お釈迦さまの限りなき大慈悲の化導が展開されているのです。
一念の念とは、ただ坐って念じているという静止的なものでなく、十方法界にあまねく燃焼し、躍動しているものです。故に「何をもってか、衆生をして無上道に入」らしめんとする行動が激発して来るのです。
ここにいう「何をもってか」というのは、善につけ、悪につけ、ありとあらゆるものを縁として、無上道なる一仏乗を信受せしめようとされているお釈迦さまの方便、てだてをさしているのです。
前にも再参申し述べたことがありましたが、仏の慈悲の「慈」とは、上から下へ、いつくしむという従果向因の立場であり、慈悲の「悲」とは、仏が衆生の中にあって、衆生の悶えを我が悶えとし、衆生のうめきに共にうめくという従因至果の立場を示しているものです。それというのも、慈悲一念心に、如来の三千が具足し、因果同時不二であることにもとずくものと申されましょう。
因果不二ということは、本因本果不二ということであり、この不二を体とする一念は、方便品に「如我等無異」といい、自我偈に「得入無上道速成就仏身」という、久遠劫来の如来の本願をこめた一念であるばかりでなく、「何をもってか衆生をして無上道に入」らしめんとする久遠の本願力、如来秘密神通の力、無量の過去仏によってあらわされ嫡々相承された強大な呪力、そういう力が悉くこめられた一念である、といわれなければなりません。
久遠の本願力、その呪力のこめられた一念であればこそ、これを敢えて強調して「毎自作是念」の「毎」の一字が付けられているのです。読み方は、同じ「つねに」であっても、一般にいう「常」であった場合、「念」は常住の念、地上はるか彼方上空の霊山虚空より、常に衆生を護念されている念願とか、或いは、そこから常に衆生に呼びかけられている限りなき慈悲一念、というように解釈され勝ちでありましょう。
ところが一方、同じ「つねに」と読むのに「毎」の字をあてた場合、お釈迦さまが霊山浄土から、遙か下方の地上にのたうつ衆生を護念され、衆生に呼びかけられるばかりでなく、久遠劫来、毎日毎日、朝に昼に夜に、私たちの一挙手・一投足毎に、私たちの心の中の一刹那一刹那毎に、全力を注いで、無上道に入らしめんとして、しかも私たちの直ぐそばにいて、働きかけられている如来久遠の本願力、秘密神通力、如来の巨大な呪力というものが、その一念の中に感ぜられるのです。
「常」と「毎」とのニュアンスの違いを云々するのは、私の個人的な感情かも知れません。然し、「毎自作是念」のこの「念」には、本仏お釈迦さまの「如我等無異」といい「得入無上道」といい「速成就仏身」という久遠の本願、念願がこめられているばかりでなく、躍動する本願力、神通之力、呪力がこめられ、その力をもって十方法界に、全力投球して働いている念である、ということを強調しておきたいのです。
曽って私は、お釈迦さまの久遠実成という仏身観について、日月灯明仏・大通智勝仏・然灯仏といった無量無辺の過去仏が、お釈迦さまの過去の本果、過去常を示し、久遠実成の実体を表明している、と述べたことがありました。今、過去仏を例にあげて、その本願をかえりみるならば、無量の過去仏もそれぞれに「毎自作是念」の本願をいだき、その本願力を尽くされたはずです。
すると毎自の本願とは、本仏お釈迦さまが、それぞれの無量の過去仏として出現される毎にいだかれた本願であり、作是念の念もまた、それぞれの過去仏が発揮された本願力であって、それが悉く今の本仏お釈迦さまの一念の中に凝集していると申せましょう。
本仏お釈迦さまの本願呪力、念力といってもよいと思いますが、それは生身のお釈迦さま一人のものではなく、実に、無始久遠劫来、無量無辺なる過去仏の本願呪力、本願念力を、そのまま継承凝集したものであり、それが作是念の「念」の一字にこめられている故に、ことさらに「つねに」を「常」とせず、「毎」という字に当てたともいうことが出来ましょう。
また、このように理解することによって、より一層、本仏お釈迦さまの本願と本願力の強烈さをうかがうことが出来るということになって来るわけです。
自我偈の結びの一句「毎自作是念 以何令衆生 得入無上道 速成就仏身」の二十字の中、本仏お釈迦さまが、久遠劫来、毎に私たち衆生にむかって呼びかけられ、働きかけられているものは、「作是念」の「念」であり、「得入無上道 速成就仏身」とは、その念の内容説明なのです。
ややもすれば、法華経を信行し、朝夕に自我偈の経文を読誦している人々でさえ、念の内容である「得入無上道 速成就仏身」という本願の方に心を注ぎ、念そのものの久遠にして毎に新鮮なる、拡大にして且つ私たち一人一人の上に凝集しているこの念の力そのもの、働きそのものに気付かないでいる、という傾向が強いようです。
ここに、本門の本尊をぬきにして、ただ法華経の経文を読誦すればよい、題目さえ唱えておればよい、という信仰の混迷がかもされて来るのです。そういうことでは本仏お釈迦さまの久遠の血脈を相承し、その本願に生き、生かされるということはなりません。本仏お釈迦さまの仏身に不二相即していなくて、どうして本化の菩薩の一分と名乗ることが出来ましょう。本化の菩薩でなければ、もとより如法に法華経を受持することは出来ないのです。
今日の日蓮門下の低迷は、無量無辺の過去仏以来、それを体とされた本仏お釈迦さまのこの一念相承を忘失している処に起きているのです。日本国土を始め全世界の混乱も、ここに起因しているというほかはありません。
○過去仏以来の久遠の本願とその願力
本願というのは、如来が成道してより衆生救済と仏国土建立の誓願を立てたものでなく、たとえば阿弥陀如来の本願とは、阿弥陀如来の前身である法蔵菩薩が、菩薩として立てていた四十八願をさすように、如来が菩薩時代より立てていた誓願を本願というのです。
法華経では方便品にお釈迦さまの本願について、
我れ本(もと)誓願を立てたり。一切の衆をして、我が如く等しくして異なることなからしめんと欲しき。
我が昔の所願の如き、今すでに満足しぬ。一切衆生を化して、皆仏道に入らしむ。
と明され、また無量の諸仏の本願についても、同じく方便品に、
諸仏の本誓願は、我が所行の仏道を、あまねく衆生をして、また同じくこの道を得せしめんと欲す。
と述べられている処です。
この意味については、後で詳しく論じなければならないと思うのですが、今、簡単に述べれば、諸仏の本願は、一切衆生をして仏と同じ本果を得せしむることにあるのですが、その前提として本果に即する本因の一仏乗を行ぜしめるということにあります。
この本因行は、曽って無量の諸仏も悉く行じて来たものであればこそ、方便品に、
若し、法を聞くこと(一仏乗を行ずること)あらん者は、一人として成仏せずということなけん。
とあるように、無量の諸仏の体験に徹しても確証される処であり、お釈迦さまが成道以来、四十余年の方便説法を経て方便品に来たり、増上慢の衆五千人が退去して、始めて一仏乗を開顕した当処、四衆が一仏乗を信受するや否や、「如我昔所願 今者已満足」という仏陀の歓喜が涌発するのです。
注意しなければならないことは、「如我等無異……我が如く等しくして異なることなからしめん」という本願が、本果を得せしめるという意味だけでなく、本因本果を得せしめるということであって、方便品では特に本果に即する本因行に重点がおかれているということです。本因を行ずる処、そこには既に本因に即する本果が実在しているのです。
本因をともなわない本果はありません。本果をともなわない本因はありません。本因本果は、本来、不二相即しているものであり、如来の本願もまた本因本果不二なるものなのです。
毎自作是念の仏陀の一念にも「得入無上道」の本因と、「速成就仏身」の本果が具足していました。弥陀の四十八願は、そのまま法蔵菩薩の四十八願であったのです。
然るに、法然上人や親鸞上人の専修念仏は、四十八願の願行を、弥陀一人にあずけてしまい、衆生の行ずべき因行は、既に弥陀が代わって行じ、行じ終わられているので、もはや改めて行ずる必要はないという立場に立って自力を極力否定し、毛にも自力の思いをすることでさえ、弥陀の摂取不捨の本願を信じ切っていないものとして排斥してしまい、他力を標榜して、その念仏行も報恩行である、とすりかえてしまっています。
ここに姑息な歪曲があります。むしろそういう歪曲をせざるを得ない念仏門の限界があったとも申せましょう。念仏門の限界、それは弥陀の本果と、法蔵菩薩の四十八願の因行とを不二相即するものと見ることが出来ず、本果の中に、成就された因行を見ようとしたことにあります。従って、弥陀の本願に乗ずる者は、更に本願を行ずる(因行を修する)という必要もなくなってしまうわけです。
大無量寿経に説かれている四十八願の中、最も重大な願とされている第十八願とは、
たとい、われ仏を得たらんに、十方の衆生、至心に信楽して、わが国に生まれんと欲し、乃至十念せん。若し、生ぜずんば正覚を取らじ。ただ五逆と正法を誹謗するものを除く。
ということなのですが、ここには既に因果同時不二ということが明確にうたいあげられているのです。即ち、法蔵菩薩が仏果を成じた後、十方の衆生が至心信楽して、弥陀の浄土に往生しようとして乃至十念、十声念仏し、若し衆生が往生しなければ仏果に留まらないということは、摂取不捨の願力を強調すると同時に、本果に即する因行の不滅をうたいあげているのです。
もとより、衆生が仏道を行じて仏国土に往生する者がなければ「正覚を取らし」仏果に留まらないということは、至極当然のことであって、若し、それでも独り仏果に留まる仏があるならば、それは仏ではなく、仏の仮面をかぶった独善者にすぎないでありましょう。
第十八願は、そのようなあたりまえのことを、ことさらに、もったいぶって言っているのではなく、肝心な点は、仏子が仏界に入らないならば「正覚を取らじ」といっていることです。ここにいう「正覚を取らじ」ということは、乃至十念の念仏の行の絶対性を強調せんがための反語であると同時に、実は仏は、常に衆生と共にあり、共に行ずるものであるということです。そしてその因行は、今、始まったものでなく、無始無終のものであるということです。
衆生が成仏しなければ、仏も成仏しないというのではありません。衆生を成仏させるためにこそ、まずみずから成仏しながらも、苦しむ衆生のいる限り、永遠に衆生の苦悩を背負って、衆生と共に行じてゆくということです。
建治三年九月十一日付け、身延山中より四条金吾へ送られた「四条鈔」に、
たとえ、殿の罪深くして地獄に入り給わば、日蓮を如何に仏になさんと釈迦仏こしらえさせ給うとも、用い参らせ候べからず。同じ地獄なるべし。日蓮と殿と、共に地獄に入るならば、釈迦仏・法華経も地獄にこそおわしまさざらめ。暗に月の入るが如く、湯に水を入るるが如く、氷に火をたくが如く、日輪を投ぐるが如くこそ候わんずれ。
と大聖人は述べられていますが、仏子と共に地獄にも入る仏こそ、まことの仏と申されましょう。弥陀の第十八願も、実は大聖人と同じ心を述べていると見るべきではないでしょうか。
然るに、親鸞上人にあっては、第十八願の「唯除五逆誹謗正法」の八字を釈して、末法の衆生は悉く五逆・誹謗正法の者ばかりである。従って末法の衆生は、もはやいずれの教えも守り難く、いずれの行も行じ難い悪人と知って、唯ひたすら念仏せよ、念仏以外に救われる道はない、弥陀は、そういう悪人こそ正機として摂取不捨の願を立てられたのである、と悪人正機説を強調し、専修念仏に集注せしめて行きました。
その結果、弥陀の本願に乗じて救われることをもって、本願に生きるとはいっても、弥陀の本願を我が本願として、本願を行ずる、四十八願を行ずるという菩薩行は、影すらなくなってしまったのです。
親は懸命に働いて、食物を作って子供に与える。子供は働きもせず、ただ与えられた食物を食べるだけ、ということが代々つづいたならば、その家庭は一体どうなるのでしょう。大聖人は「念仏無間」と批判されましたが、まさしく弥陀の本願を食う法食餓飢地獄ではないでしょうか。
これに対して法華経では、法華経を行ずる者は、如来の本願に乗じて一仏乗を行ずる場合、如来の本願を、みずからの本願とすることが明確に打ち出されています。五百弟子受記品第八の冒頭、
その時に、富楼那弥多羅尼子、仏に従いたてまつりて……而も、この念をなさく、世尊は甚だ奇特にして所為希有なり。世間若干の種性に随順して、方便知見をもって、為に法を説いて、衆生処々の貪著を抜出したもう。我等、仏の功徳において、言をもって宣ぶること能わず。ただ仏世尊のみ、能く我等が深心の本願を知ろしめせり。
といわれているのが、則ちそれです。
富楼那尊者は、お釈迦さまの十大弟子の中でも説法第一、弁説第一とうたわれた人でした。この受記品第八の中でお釈迦さまは富楼那をたたえて、
汝等、富楼那はただ能く我が法を護持し助宣すということなかれ。また過去九十億の諸仏のみもとにおいても、仏の正法を護持し、助宣し、彼の説法人の中においても、また最も第一なりき。
といい、更に、
富楼那は、また七仏(過去七仏)の説法人の中において第一なることを得、今、我がところの説法人の中においても、また第一なることを得。賢劫の中、当来の諸仏の説法人の中においても、またまた第一にして、みな仏法を護持し助宣せん。
と仰せられているほどです。つづいてお釈迦さまは、富楼那に対して「法明如来」という仏名をさずけて成仏を授記されるのですが、富楼那がお釈迦さまの在世中はもとより、過去世九十億の諸仏の仏弟子中、常に説法第一人者であり、また未来永劫の諸仏のもとにおいても常に説法第一であるということは、富楼那が、既に久遠の本果に即する久遠の本因の位に住していたことを証するもので、「内に菩薩の行を秘し、外にこれ声聞なりと現ず」る「内秘菩薩行、外現是声聞」の姿でありながら、実は本化の菩薩と変わらぬ内容をもつ身であった、と申されましょう。
如来の本果に即する如来の本因の位にあって、本因本果不二の一仏乗(因行果徳の題目)を行ずる者は、如来の本願を我が本願として体し、本願を行ずる者です。先に富楼那が「深心の本願」といい、それを能く知るものは仏世尊のみであると、お釈迦さまを賛嘆したのは、富楼那の姿が「内秘菩薩行、外現是声聞」のままであったからです。
この五百弟子受記品の中で、面白いことは、品末に述べられている「衣裏宝珠の譬え」でありましょう。この譬え話は、法華経七譬の一つに数えられているものですが、概要は次の通りです。
或る所に、貧しさに困窮した男がいました。たまたま昔の親友に出会い、親友にまねかれて、その家に行きました。親友は富豪でした。家も立派でした。さっそく親友は山海の珍味をそろえて御馳走しました。男は腹一杯食べると、そのまま眠ってしまいました。男が眠っている間に親友は、そっと男の粗末な着物の内側に、その家で一番尊い無上の宝珠を包んで、縫いつけておきました。
さて、親友が外出中、眠りからさめた男は、そのまま家を出て、またもとと同じさすらいの旅を始めました。やはり貧しさに困窮した旅の日々がつづきました。男は着物の内側に縫いつけられている宝珠に気付かなかったのです。
こうして何年もたって、男は再び親友の家の前に立たずみました。親友は男の昔に変わらぬ貧窮の姿に驚き、さっそく男の着物の内側の宝珠を取り出して、
「あの時、既に私は、この宝珠を貴方に与えておいたのに……」
と申しました。男は驚き、且つ歓喜しました。宝珠は金に代えられ、金で家を建て、財物も集めて、楽しく暮らすようになった、ということです。
この譬え話の中の貧窮な男とは、一切衆生のことであり、富豪の親友とはお釈迦さまのこと、さすらいの旅とは求道の旅、そして親友の家で食べた色々な御馳走とは仏の方便の教えであり、衣裏の宝珠とは一仏乗のこと、男が建てた家とは仏国土のことを意味しているのです。
ところで、面白いというのは、この譬喩説話の中に語られている「衣裏の宝珠」のことです。この宝珠を、一切衆生悉有仏性の仏性であると説かれる人もいるようですが、本具の仏性と解釈してしまっては、親友にたとえられているお釈迦さまから与えられていたということと矛盾してしまいます。仏性とは仏から与えられるものでなく、誰にでも本来そなわっているものであるからであるからです。
従って、この宝珠は、山海の珍味なる御馳走を、無量の方便の教え、二乗・三乗の教えに譬えるに対して、法華一仏乗でなければなりません。一仏乗であったればこそ、これを受持した時、直ちに仏国土に住することが出来、仏国土における菩薩行を楽しむことが出来たわけです。
なお男が、方便の珍味に満腹して眠っている間に、親友なるお釈迦さまが秘かに男の上衣の内側に、一仏乗なる無上宝珠を縫いつけておいたということ、そしてその男が再び親友にめぐりあい、その宝珠を取り出して見せられるまで、全く衣裏の宝珠に気付かなかったということは、お釈迦さまが一仏乗において、方便分別して三乗を説いた時、所謂、方便品に、
諸仏、方便力をもって一仏乗において分別して三と説きたもう
と誡められているにもかかわらず、表面の方便三乗にとらわれて、その三乗をあらしめている内なる一仏乗に気付かなかったということです。方便品には、
十方仏土の中には、ただ一乗の法のみありて、二もなく、また三もなし。
といわれ、更に繰り返して、
如来は、ただ一仏乗をもっての故に、衆生のために法を説きたもう。余乗の若しは二、若しは三あることなし。
といい、分別説三の教えも、実は一切衆生をして一仏乗を行ずる菩薩たらしめんがためであったといわれているのです。
諸仏如来は、ただ菩薩を教化したもう。もろもろの所作あるは、常に一事のためなり。
という「但教化菩薩」にしても、「教菩薩法、仏所護念の妙法華経」という「教菩薩法」にしても、一切衆生の中、菩薩のみを選び出して、その菩薩にだけ法華経を説く、一仏乗を説くというのではありません。全く見方は逆であって、一切衆生はもとより神々までも一乗受持の菩薩として教化するということなのです。一乗受持の菩薩とは、本仏お釈迦さまより教化された本化の菩薩にほかならないのです。
自我偈の結びに、
我、常に衆生の道を行じ、道を行ぜざるを知って、度すべき所に随って、ために種々の法を説く。
という「種々の法」とは三乗方便の説であり、方便を説きながらも「畢竟して一乗に住ぜしめ」、無上道を行じて仏身を成就せしめんとされたのです。
ところが、法然上人・親鸞上人は、法華経は上眼上機のための経典であって、末代凡夫は法華経を行ずることは出来ないとして、捨閉擱拋してしまいました。法然は次のように述べています。
ことに法華経は、三世の諸仏も、この経によりて仏になり、十方の如来も、この経によりて正覚を成り給う。然るに法華経などを読みたてまつらんに、何の不足かあらん。かように申す日は、まことにさるべきことなれども、我等が器量は、この経に及ばざるなり。
その故は、法華には菩薩・声聞を機とする故に、我等凡夫は、かなうべからずと思うべきなり。
法然も親鸞も、法華経を読み違えてしまっていました。法華経は菩薩や声聞という上根上機の人々を相手に説かれたものとばかりに錯覚していたのです。「但教化菩薩」の文を、ただ菩薩だけを選りすぐって教化するものと解釈し、如何に教は勝れていても、末代凡夫、下根下機の者には及び難しと、法華経を放げ棄ててしまったのです。
ここに法華経を読み違えたことから起こる大謗法があります。然し、日蓮門下の学匠の中にも、法然・親鸞流に「但教化菩薩」「教菩薩法」を解釈する人々がいるのは、一体どういうことでしょう。「衣裏宝珠」の譬え話を、もう一度読み返す必要があるのではないでしょうか。貧窮下賎の流浪の者ですら、一仏乗によって本化の菩薩として仏国土に住することを得たというこの譬え話は、法然・親鸞の頭上に鉄鎚を下すものでありましょう。
ところで、話を元へ帰せば、五百弟子受記品では「衣裏宝珠」の説話のあと、この無価の宝珠を「無上の願」と約し、宝珠を男の上衣の内側に縫いつけたことを、
世尊、長夜において、常に愍んで教化せられ、無上の願を種えしめたまえり。
と述べているのです。
無価の宝珠が、何故、如来の「無上の願」と訳されているのでしょう。岩波文庫本の「法華経」中巻、岩本裕博士の訳をみても、「前世の誓願」とされ、
尊師よ、われらはこのように前世の誓願を知らなかった。これは過去世に生まれたとき、永い間、如来がわれらに授けられたのであった。
と和訳されており、南条文雄・泉芳環共訳による「梵漢対照、新訳法華経」(二四一頁)においても、
世尊 我等もこのごとし 過去の願をしらざりき
長き夜ここに生ごとに 如来はこれを施しき
と訳出されているのです。
このように宝珠の意の訳出の仕方を対比する時、羅什三蔵が妙法華経の五百弟子受記品第八において「無上の願」と訳したのは、決して誤訳でもなければ、達意的訳でもなく梵本原文に忠実であった、と申せましょう。
すると、ここに宝珠は一仏乗であり、同時にそれは本仏お釈迦さまの願(本願)として、久遠劫来、衆生の心田に下種されていたものであった、ということが出来るのです。この五百弟子受記品の冒頭、富楼那尊者がお釈迦さまを賛嘆した言葉の中に、
「ただ仏世尊のみ、能く我等が深心の本願をしろしめせり」
と述べられていることも、富楼那尊者をはじめとする声聞(内秘菩薩行、外現是声聞)の衆が、みずから深心の本願として起こしていたものは、実は本仏お釈迦さまより、既に久遠の昔より下種されていた如来の本願(一仏乗の妙法蓮華経の五字七字)であったのであり、だからこそ、深心の本願を知るものは、ただ仏世尊のみである、ということになるわけです。
日蓮教学上では、下種の題目とか、題目は下種する仏種であるとか、題目は仏乗種であるなどと盛んに論じられています。然し、その仏種の題目(一仏乗)が如来の本願であり、一仏乗の下種とは如来の本願をうえることであるとは、あまり論ぜられていないようです。法本尊義の思潮の強かったこれまでの日蓮教学では、無理からぬことであったかも知れませんが、「如来毎自の大本願」を語ろうとする場合、本願下種をないがしろにしてはならないのではないでしょうか。
五百弟子受記品は、このことを強く訴えているようです。富楼那尊者をはじめとする法華経会座の二乗声聞の衆は、久遠の昔、本仏お釈迦さまによって心田にうえつけられていた如来の本願(得入無上道の因行と、速成就仏身の果徳の不二相即する一仏乗の題目)に気付いていました。そしてその如来の本願をみずからの本願とし、如来の一仏乗をみずからの行法とするとき、悉く作仏の受記を得ているのです。
就中、富楼那尊者は、本果に即する本因の位にある故に、過去九十億の過去仏の会座においても、またお釈迦さまの仏弟子の中にても、更には無量の未来仏の下にあっても、常に説法第一人者であるという不動不滅の地位が開顕賛嘆されていたのです。
法華経の迹門における二乗作仏は、小乗の灰身滅智と大乗般若の二乗永劫不成仏とを共に超克し、未来世、他土における成仏の授記をうけるという授記作仏の形態をあらわすことによって、法華経の教の勝れていることを明らかにし、本門の久遠実成の開顕とあわせて法華経教義の双璧とうたわれて来ているのですが、然し、それでも日蓮教学においては、本門八品に来現した地涌の菩薩にくらべれば、法華の二乗は遙かに劣るものであるかのように印象づけられているようです。
然し、これまで見て来たように法華二乗は、富楼那尊者の例もある通り、如来の本願そのものである一仏乗の下種にめざめ、如来の本願を我が深心の本願とし、如来の一仏乗をみずから受持して生々世々に実践するというものであるならば、既に娑婆において如来の仏界に入っているものであり、仏界に住して如来と共に一乗の菩薩道を行じ、究極においては、みずから仏身を成就し、それと同時に、娑婆を中心とする三千大千世界が本仏お釈迦さまの我が有とされる仏国土である以上、一仏一土のならわしに従って、みずからの仏国土を地上に建立するという二重構造をもっているのです。
これは浄土三部経の中の大無量寿経において、燃灯仏以来の過去仏の系譜を引く世自在王仏のもとにあって法蔵菩薩が、五劫の思惟の後、四十八願の誓願を起こし、菩薩行を成就して阿弥陀如来と現じ、西方十萬億土の彼方に安養極楽浄土を建立したということと、全く同じパターンをなしているのです。
厳密にいうならば、法華二乗者の深心の本願が、無量の過去仏の下種した本願にめざめたものであり、従って、その本願が無始以来の過去仏の連綿たる血脈譜をなしているに対し、浄土門の法蔵菩薩の本願である四十八願は、法蔵菩薩によって初めて起こされたものであって、過去仏より本願を下種されたものでなく、折角、燃灯仏以来の過去仏の系譜をうたいあげながら、本願下種を逸し、そのため本願の久遠を主張するに無理を来してしまっている、という相違はあるようです。
然し、その両者の立願、菩薩行、成仏、仏国土建立のパターンが全く同じであるということは着目すべきことであって、法華経々典の中にも阿弥陀如来が屡々あらわれ、殊に、化城諭品第七の中においては、大通智勝仏の十六王子の中、第九番目の王子に阿弥陀如来があげられているのも、法華経の開会思想もさることながら、開会の素地として、こうした経典成立史上の背景があったのではないか、と思わしめられるのです。
法華経における二乗の授記作仏、それは譬諭品の舎利弗尊者に対する授記に始まって、勧持品の耶輸陀羅比丘尼に対する授記に至るまで、お釈迦さま御在世当時の直弟子に対する授記に終始しているものですが、それは二乗の成仏として決して軽視されるものでなく、法然上人や親鸞上人をはじめとする浄土門の人々が、古来、懸命になって鼓吹して来た法蔵菩薩の立願、阿弥陀仏としての成仏、西方安養極楽浄土の建立に匹敵するばかりでなく、量においても質においても、またその現実性においても、はるかにそれを凌駕しているといわれなければなりません。
浄土門が方便であり、法華門が真実であるという以上、それは当然のことではありましょうが、これまで日蓮教学上、久遠の本仏お釈迦さまの毎自の本願を主張しながら、この本願と弥陀の本願との対比、批判がおろそかにされ、法蔵菩薩の立願作仏と二乗の立願作仏のパターンの類似していることに注目して、これを研究批判する試みも、殆どなかったようです。
日蓮門下の者として、大聖人の獅子吼された「念仏無間」の言葉を鵜呑みにして、念仏を軽視し、法華一乗を誇りとしている人々の中に、本仏お釈迦さまの本願も知らず、二乗の立願・授記作仏の真相も知らず、ために形ばかりの法華者であって、本化の自覚も持たず、二乗の自覚にも至っていない人々が、何と多いことでしょう。日蓮宗をとわず新興宗教団体をとわず、お題目を唱えている人々の大半は、殆ど信仰気取りに留まっていて、真実の信心を得ている人は、大地の土に対する爪上の土にも等しいようです。
ところで、今、法華門における二乗の立願作仏と、念仏門における法蔵菩薩の立願作仏とを、詳細に対比し批判するいとまはありませんが、「如来の本願」ということに的を絞って両者を見るとき、両者に共通する如来として、燃灯仏という過去仏がクローズアップして来るのです。
大無量寿経によれば、法蔵菩薩の師は世自在王仏であり、この仏より五十二人の過去仏をさかのぼって、最初の過去仏が燃灯仏とされています。この燃灯仏は法華経の序品では、同名同姓なる二萬人の日月灯明仏の中、最後の第二萬番目の日月灯明仏が、未だ出家しない以前にもうけた八王子の中、その仏の弟子の妙光菩薩より法華経の教化をうけ、最後に授記作仏した王子であったとされており、如来寿量品では、
我れ成仏してよりこのかた、またこれ(五百億塵点劫)に過ぎたること百千万億那由陀阿僧祇劫なり。これよりこのかた、我れ常にこの娑婆世界にあって説法教化す。また余処の百千万億那由陀阿僧祇の国においても衆生を導利す。
もろもろの善男子、この中間において、我れ燃灯仏、等と説き、またまたそれ涅槃に入ると言いき。かくの如きは、みな方便をもって分別せしなり。
と示されているように、久遠の本仏お釈迦さまが、無始久遠劫来、衆生を教化されるその中間過程において、燃灯仏として出現したといい、燃灯仏をはじめ無量の過去仏は生身のお釈迦さまの久遠の仏身を開顕する方便身であった、とされているのです。
如来寿量品において、お釈迦さまの過去の仏身をいうのに、無量の過去仏の中、特に燃灯仏をかかげたのは、法華経々典の成立する当時、その成立する地域であった西北インド、ヒンズークシュ山脈のカイバル峠の東のパキスタン、西のアフガニスタン地方に燃灯仏の物語が非常に盛んであったことを示しているものでありましょう。
東洋大学教授菅沼晃博士は、同大学教授金岡秀友博士と対談した「アフガニスタンの仏教―砂漠と幻想の国」(一六四頁)に、
「アフガニスタンを歩いてみて、私が感じたことのひとつは、こんなにも燃灯仏が多かったか、という驚きでした」
と語っています。身延山短期大学の高橋堯昭師も屡々パキスタン・アフガニスタン地方に二仏並座の仏像をたずねて仏蹟をめぐり、その旅行記の中に、菅沼博士と同様の感想を述べていましたが、たしかに仏像写真集をみても、この地方には燃灯仏に関する仏像が屡々紹介されているほどです。
法華経をはじめ西北インドで成立した大乗経典には、日月灯明仏・日月浄明徳仏・大通智勝仏・威音王仏・雲自在灯王仏・雲雷音王仏・雲雷音宿王華智仏といった多くの過去仏が説かれていながら、何故、この地方に、今日にまでも、その仏像が残されているほど燃灯仏の物語が盛んであったのか、という問題は、まことに興味深い推理テーマになりそうです。
その前に、燃灯仏の物語を概略ふりかえってみるならば、燃灯仏在世中のこと、儒童菩薩(別名―弥却、メーガ、MEGHA)が、燃灯仏の神々しい尊蓉を拝した時、その尊蓉にうたれ、自分も必ず燃灯仏のような仏陀になろうと誓願しました。たまたま燃灯仏が歩かれようとする道路は、ぬかるんでいました。儒童青年は、さっそく七茎の蓮華の花を燃灯仏に捧げ、ぬかるみの上には鹿の皮を敷き、それでも足りないところには、地面に頭をつけ、自分の髪でぬかるみをおおい、燃灯仏がその上を歩くように願いました。燃灯仏は青年儒童の真心と願いを聞き入れ、静かにその上を歩き、儒童に対して、「汝は未来世において必ず私と同じ仏陀になるであろう」と授記されました。その時の青年儒童こそ今のお釈迦さまである、というのです。
私の恩師に、立正大学の香風学寮の寮監をされていた朝比奈文貞先生がいました。副寮監が後にビルマ戦線で戦死された唐津法蓮寺の藤山英教先生でした。私の香風学寮時代、両先生に引率され、黒染めの衣に手甲脚絆、天台笠にウチワ太鼓といういでたちで、大聖人立教開宗の聖地である房州清澄山へ撃鼓参拝したこともあり、更に私的な関係もあって、生涯、忘れることの出来ない恩師ですが、その朝比奈先生が当時の陸軍部の要請で日蓮宗を代表する宣撫班員に選ばれ、教壇を去って南方ビルマへ赴かれました。
何ヶ月かたって帰国された先生が、私に次のように語られました。
「日高君、僕はビルマに行って全く驚いた。現地には日本山妙法寺の寺があって、太鼓がなり響き、門前には玄題旗がはためいていた。思いもかけない感動だった。ところが驚いたのは、それどころではない。日本山にいる永井行慈上人が、毎朝のように、自分のお寺からビルマの仏舎利塔へ太鼓をうって参拝に行くのを日課としているのだが、その沿道に現地の仏教信徒が、ずらっと列んで永井上人の通過をおがむのだ。日本式のおがみ方ではない。土下座して仏陀をおがむようにしておがむのだ。そればかりではない。永井上人の歩く道の上には、朝つんで来たばかりの美しい花を敷きつめて、女性は婦人であろうと娘であろうと、その長い髪の毛を左右から向かいあって道路の上に敷いて礼拝するのだ。永井上人は高らかにお題目を唱え、太鼓をうちならしながら、堂々と花をふみ、髪をふんで、仏舎利塔へ向かって行った。勿論、永井上人は素足だったが、この光景は、日本山のお寺から仏舎利塔まで延々とつづいていた。日高君、僕は現地にいる間、毎朝この光景に接した。毎日が衝撃だった。」
朝比奈先生は終戦直後、初めて再会された中山の大荒行堂に、僧正の位にありながら、戦後の日蓮宗行学の在り方を模索しながら、初行僧として入行し、二月十日出行するやいなや、当時、佐賀県小城の日親堂で修行していた私を訪ねられ、行中に感得された祈祷教学について情熱的に語ってくれました。これを契機として次回の中山荒行堂へ私も入行するようになり、その行中、初行僧の行堂脱出という事件が起こり、荒行堂の身延山移転と、日蓮宗・中山妙宗・日本山・国柱会(本化妙宗)の四派合同とが企画されたのです。
四派合同は失敗し、間もなく朝比奈先生は病死され、ビルマの永井上人も戦後ビルマから引き揚げられ、神戸の十文字山仏舎利塔計画中に病死されてしまいましたが、朝比奈先生のビルマからの帰国談にある永井上人の仏舎利塔参拝の道中における現地仏教徒の光景こそ、燃灯仏の物語をそのまま現代に再現し、実践したものであって、勿論、永井上人が現地人に対して、そういう礼拝供養の仕方を教えて強制したのではなく、現地人がおのずからそういう礼拝供養を行ったものであり、それだけに燃灯仏の物語の根強さが感ぜしめられ、驚かされるばかりでした。
燃灯仏の物語があらわれるのは部派仏教時代、西北インドの説一切有部の時代とされ、「四分律」の巻第三十一には燃灯仏は錠光如来としてかかげられているのですが、その後、この地方に大乗仏教が興起しても、燃灯仏の物語はそのまま大乗教徒に継承され、大乗経典成立にも多大の影響を与えているように思わしめられるのです。
その証拠として、法華経迹門における二乗作仏、念仏門の無量寿経における法蔵菩薩の立願作仏をあげることが出来ましょう。大東文化大学助教授五十嵐明宝氏は、その著「本願力の世界」(一四八頁)に、次のように述べています。
「無量寿経」における世自在王仏と法蔵菩薩の関係は、燃灯授記物語における錠光仏とメーガ青年との関係と、ほとんど同一であることは注意しなければならないし、また、法蔵比丘における本願は、メーガの誓願に源流をもつといってもよいであろう。
たとえ燃灯授記物語と法蔵菩薩説話は、すぐには結びつかないとしても、前者の影響の下に、後者の誕生がある、ということはできるであろう。
朝比奈先生の現地報告では、戦時中のビルマや現地仏教徒の中に、燃灯仏の物語は厳然として生きていました。彼等は儒童菩薩が行ったように、花をつみ、花を捧げ、鹿の皮を道に敷く代わりに花を敷き、更に自分の髪も道に敷き、お釈迦さまならぬ日本山妙法寺の法華一乗の僧侶を渡しました。彼等は自分の髪を素足でふむ永井上人を介して、永井上人が参拝に行く仏舎利塔中のお釈迦さまを感じ、お釈迦さま、法華経の行僧、そして自分自身という一本の系譜をいだき、永井上人の打ちならす法鼓、唱える大音声のお題目にお釈迦さまの声を聞く思いをしていたことでしょう。
私は、朝比奈先生にあった時も、永井上人にあった時も、ビルマで現地仏教徒が永井上人をそのように迎えた態度は、毎朝の仏舎利塔参拝に行く道中だけではなかったか、と尋ねることを逸してしまいましたが、おそらく毎朝のその時だけではなかったかと思うのです。
彼等には、仏舎利塔は絶対的な存在でした。永井上人は仏塔中のお釈迦さまの使いであり、代行者と拝されたのでありましょう。そして永井上人に対して儒童菩薩の如く礼拝供養することは、儒童菩薩の得た功徳に彼等みずからあずかろうとしたのでありましょう。
然し、こういう事実は、紀元前後の頃、西北インドの仏教徒の中でも、そのまま実行されていたのではないでしょうか。燃灯仏授記物語は、単なる説話として、人から人へ、口から口へ伝えられただけのものでなく、ビルマ仏教徒が実行していたように、実際に実行され、実践をともなった説話として語りつがれていたのではないでしょうか。
彼等は、そうしたみずからの実践の中に、燃灯仏授記の仏像を作製し、その像を礼拝することによって一層みずからの実践を鼓舞すると共に、授記の功徳にあやかろうとしたのではないでしょうか。大乗仏教の興起した西北インド、成立した多くの大乗経典の中に、無量の過去仏が説かれていながら、現在、なお燃灯仏に関する授記の仏像の多く残っているのも、この物語が民衆の中に実践されていたためとも申されましょう。
法華経の二乗作仏にしても、大無量寿経の法蔵作仏にしても、そうした実践を母胎として、発展的に成立して行ったのではないか、と思わしめられるのです。法華経第二十の常不軽菩薩品には、常不軽菩薩の礼拝授記行が強調されています。この行が日蓮大聖人の法華経実践上の軌範とまでされたことは有名ですが、今、常不軽菩薩の礼拝授記行と、燃灯仏の授記物語とを対比してみれば、常不軽菩薩の礼拝授記行そのものの中に、儒童菩薩の立願礼拝と、燃灯仏の授記とを、同時に見ることが出来るのです。
立願礼拝は従因至果の立場、授記は従果向因の立場、こういう二つの立場を同時不二のものとして行じた常不軽菩薩こそ、法華一乗の菩薩、本化地涌の菩薩である、と申されましょう。
私は、常不軽菩薩品を読むたびに、法華経々典の成立した当時、その地域の法華教徒達自身が、みずから常不軽菩薩の礼拝授記行を行じ、常不軽者として世の人々から悪口され、打擲迫害されていたのではないか、と思われてならないのです。若し、そうだとすれば、その実践は、燃灯仏授記物語にもとずく仏の授記と菩薩の立願礼拝という両方の実践を統一し、一体のものとして発展せしめたものであった、と申されましょう。
如来寿量品において、現身のお釈迦さまの過去久遠の化導を実証するため、法華経に登場した無量の過去仏の中、特に燃灯仏を代表としてかかげた所以も、実は、法華経々典成立の当時、その地域における一般仏教徒の中に、燃灯仏物語にもとずく広い実践があり、法華教徒の間においても、燃灯仏物語より発展した常不軽菩薩道というものが実際に根強く実践されていたという裏付けがあったからである、ということが出来るのではないでしょうか。
現身のお釈迦さまが、過去世において無量の過去仏として出現し、その中間、燃灯仏として衆生を教化されたという如来寿量品における、この仏身開顕は、実に重大な意義をもつものです。
それは、無量の過去仏をお釈迦さまの現身に帰納統一せしめんがための工作でもなければ、過去常を表明せんがための観念的模索でもなく、久遠の因行(本因)と久遠の果徳(本果)との時々不二、事々不二をいい、不二の本因本果が、そのまま悉くお釈迦さまの現身に成就していることを明らかにしているのです。如来寿量品におけるお釈迦さまの久遠実成の問題とは、このことに外ならないのです。
お釈迦さまの久遠開顕は、久遠の本果の開顕のみならず、本果に即する久遠の本因の開顕もともなっているのです。若し人が、お釈迦さまの前世は儒童菩薩として修行されていたと聞いていて、後にまた、お釈迦さまの前世は燃灯仏として儒童菩薩に授記されたのだと聞いたならば、誰でも、その矛盾にいぶかしがることでしょう。何故ならば、一人の人間が、同時に相対する二人の人間になることは出来ないからです。
ところが如来寿量品は、敢えて、その矛盾を犯しています。しかも燃灯仏物語とその実践の広く浸透していた当時、
もろもろの善男子、この中間において、我れ燃灯仏、等と説き、またまたそれ涅槃に入るといいき。
と宣言しているのです。そればかりではありません。常不軽菩薩品に至っては、儒童菩薩の立願礼拝行と、燃灯仏の授記行とを一体とした常不軽菩薩行を打ち出し、主張するばかりでなく、みずから法華教徒の実践行として展開しているのです。法華経の心を知らない人々は、まさしく狂気の沙汰、としか思わなかったことでしょう。常不軽菩薩を行ずる法華教徒を見ては、分裂症の狂人が燃灯仏がかって授記したり、儒童がかって礼拝すると、或いは怒り、或いは侮蔑嘲笑し、或いは罵詈打擲したことでしょう。常不軽菩薩品の中には、
衆人、或いは杖木、瓦石をもって、これを打擲す
と述べられていますが、迫害を加える人々の心中には、おそらく燃灯仏信仰が深く浸透していたことであり、この固定化した信仰から法華教徒に対する迫害が起こって来た、とも申されましょう。
法華経は、本因本果の同時不二相即を根幹としています。法華経の譬諭品第三から勧持品第十三に至る間における仏弟子の比丘・比丘尼に対する授記、それはいずれにしても未来世、無量の諸仏のもとにおいて菩薩道を行じて作仏するというように設定されていますが、実は、無量の諸仏と、諸仏のもとにおいて菩薩道を行ずる仏弟子との、時々念々における因果不二、事々不二をいい、その当処における常住の仏界を、作仏の未来に託して表現しているのです。
わけても五百弟子受記品において富楼那が、過去七仏のもとにあっても、また過去九億の諸仏のもとにあっても仏弟子中、説法第一人者として菩薩道を行じ来ったものであり、賢劫の中、当来の諸仏のもとにあっても、その仏弟子中、常に説法第一人者として菩薩道を行ずるものであるという設定、或いは授学無学人記品において、お釈迦さまの長子であった羅
汝、未来世において当に作仏することを得べし。蹈七宝華如来・応供・正偏知・明行足・善逝・世間解・無上士・調御丈夫・天人師・仏・世尊となずけん。当に十世界微塵等数の諸仏如来を供養すべし。常に諸仏のために、しかも長子となること、なお今の如くならん。
と授記された設定、これらは因果不二の当処における因行の常住を特に強調しているのです。
若し、未来世、生々世々にわたって「十世界微塵等数」という無量無辺の諸仏に供養し、そのもとにおいて菩薩道を行じた後、最後身を得て作仏するというのであれば、そこに至るまでの久遠の間、到底、安心立命することは出来ないでありましょう。
本仏お釈迦さまは、三世無量の諸仏を悉く我が身とし、そのお釈迦さまに接して本因本果不二なるその因位に住した二乗仏弟子に対し授記されたのです。そして如来寿量品に至って、はじめて本果の常住久遠を開顕されたのです。
本果常住を実証する一例として如来寿量品では、燃灯仏を代表して引きあいに出し、燃灯仏にしても無量の過去仏にしても、
またまたそれ涅槃に入ると言いき
とか、或いは、
度すべき処に随って、処々にみずから名字の不同・年紀の大小を説き、またまた現じて当に涅槃に入るべしと言い
と示しているように、その涅槃は悉く不滅の滅、方便の滅であって、すべての過去仏の寿命無量を明らかにし、総じては、
かくの如く我れ成仏してよりこのかた甚だ大いに久遠なり。寿命無量阿僧祇劫、常住にして滅せず。
と、本果の常住不滅をうたいあげ、それと同時に、本果に即する本因の常住を見落とさないように、
もろもろの善男子、我れ本(もと)菩薩の道を行じて成ぜし処の寿命、今なお未だ尽きず。また上の数に倍せり。
と入念に注意されているのです。
曽って立正大学の教授であられた茂田井教亨師は、その著「法華経入門」の中で、右にいう「成ぜし所の寿命」を、仏果を成じて以来、衆生を教化される仏の寿命と解釈されていますが、むしろ菩薩の寿命(無始の九界を代表する菩薩の寿命)でなければなりません。
菩薩道を行じて成じた寿命とは、菩薩の寿命なのです。ここにいう「成ぜし所」とは仏身を成じたということでなく、あくまでも寿命を成じたということであって、本因の不滅を明確にしようとしているのです。
普通一般には、菩薩道を行じた後に仏身を成じ、仏身を成就すれば、もはや菩薩行は必要でなく、ただ衆生を教化する仏作・仏行だけであると思いがちなものです。だからこそ、そういうあやまちを犯さないように如来寿量品に
「我本行菩薩道 所成寿命 今猶未尽 復倍上数」と断っているのです。
誰でも、寿命が尽きれば菩薩道を行ずるにも行ずることは出来ないと思っています。たしかにそれは事実です。事実であればこそ、菩薩道を行ずることによって寿命は増益し、寿量品の「良医の譬喩」における失本心の狂子すら「更賜寿命」するのです。本仏お釈迦さまにおかれては、その因行、菩薩行を行ずる寿命久遠であることは申すまでもありません。
久遠の本仏お釈迦さまにあっては、仏果も無始無終、因行も無始無終であって、両者は時々念々に不二相即し互具しているのです。従って、その功徳体である妙法蓮華経の五字に、本仏お釈迦さまの因行と果徳の二法が相即完備しつくされている、といわれるのも、また当然でありましょう。
因が果となるのではありません。果が次の果を生む因となるのでもありません。因は永遠の因、果もまた永遠の果。因は因として独立し、果は果として独立し、しかも両者は常に不二相即しているのです。
上は仏界から下は地獄界に至る十界にしても、十界のそれぞれが永遠に独立した存在であり、しかも時々念々に不二相即している状態を「十界互倶」といい、悟りの世界をあらわしているのです。日蓮大聖人が「開目抄」において、
爾前・迹門の十界の因果を打ち破りて、本門の十界の因果を説き顕わす。これ即ち本因本果の法門なり。九界も無始の仏界に具し、仏界も無始の九界にそなわりて、まことの十界互具、百界千如、一念三千なるべし。
と仰せられているのも、実は、こういうことを指しているものでありましょう。
そこで、今、本仏お釈迦さまの久遠の本果を開くならば、燃灯仏をはじめ無量無辺なる過去仏の不滅の仏身が現前し、久遠の本因を開くならば、常不軽菩薩、儒童菩薩をはじめ無量無辺なる不滅の菩薩身が現前するものであり、しかも両者の不二は、燃灯仏と儒童菩薩の関係において、或いは常不軽菩薩と二万億の威音王如来、または二千億の日月灯明仏、更には二千億の雲自在灯王仏の関係において、時々に語られ示されている処です。
このことを試みに図解してみるならば、およそ次のようになりましょう。