学生僧には、川嶋・木村・小寺・鈴木・清水・小畑という諸師がおり、その中にまじって長髪の冨村昌弘君という高校の先生もいました。冨村君は、その後、高校の教職を辞し、深層心理学を勉強するため、およそ三年間ばかりアメリカに留学し、帰国してからは北九州の某大学の英語と仏教哲学の講師をつとめていました。私が冨村君の小倉郊外の自宅によばれたのは、自宅の改築が完成した直後のことでした。
上野峡百日行以来の再会であったため、アメリカ留学中、勉強された深層心理に関する話に花が咲き、神秘修験のインドのヨガの行にまで話が及んでいました。その中、冨村君が突然次のような質問をされました。
「仏教の教理というものは、一口にいって一体どういうことでしょう。仏教の経典は八萬法蔵といわれているほど厖大なものであり、経典によって宗派が林立しています。同じ法華経経典であっても解釈の仕方で、また宗派が派生しています。こうした中にあって、仏教の根本的教理をズバリ、こうだと表明出来るものは、どういう教えでしょうか。」
もちろん、冨村君は家代々の法華経を継承し、その信仰は行を通して神秘体験にまでも至らんと志していたのですから、法華経が一切経の中で一番すぐれた経典であることは百も承知していました。然し彼の話を聞いている中、宗派仏教の在り方にあきたらず、お釈迦さま御在世当時の根本仏教に帰り、根本仏教から原始仏教・部派仏教・大乗仏教と発展して日蓮大聖人の法華経に至るまで、その間、一貫して流るる仏教の根源的真理を追究し、その真理をみずからの行によって体得し、宇宙の神秘と一体になることを願っているように思われてなりませんでした。
若し、法華経の教義大網を一口でいうのであれば、迹門の開三顕一、本門の開近顕遠と定石通りに答えることも出来ましょう。また通仏教的立場であるならば、仏教学者がよく言っているように「縁起」「実相」と、答えもされましょう。然し、そういう観念的レッテルは、既に冨村君もよく知っていたはずです。彼が耳根に徹して聞き留めたいと願っていたのは、仏教という天にもまする千年杉の大木を、根本より一刀両断にした時、その木心より発する大樹の一声の如きものであったのではないでしょうか。壁に張りつけられたレッテルでなく、骨髄より吹き上がる血汐の如きものであったはずです。
私は、
「それは因果です。因果の二字に仏教のすべてがあらわされています。」
と答えました。
彼は一瞬だまってしまいました。私の答えは彼の期待していたものより程遠いものであったようです。彼の沈黙は、期待がはぐらされた者の沈黙のようでした。
因縁・因果……善いことをすれば善い報いをうけ、悪いことをすれば悪い報いをうけるということ、こういう因果論は、無知文盲な老人の間でも、日常の信仰会話に語られていることです。こういう教えが仏教の根本教義であるはずはありません。彼は自分自身が愚弄されたと思ったのでしょうか、それとも私自身の仏教的教養の低さに不信を感じたのでしょうか、ただ頭をかしげながらだまって水割りを口にふくんでいました。会話はプツンと途切れてしまいました。
それだけに当時の彼の質問と私の応答とが深く印象づけられ、未だに忘れることが出来ず、冨村君を思い起こす時、この会話が同時に想い起こされるのです。
その後、彼とは殆ど会う機会もなく、風の便りでは、大学で教鞭をとるかたわら、小倉市の郊外に私設の幼稚園を建設し、園長として経営しているということですが、あの時、私が彼の質問に答えた「因果」ということについて、なお思索をつづけられているでしょうか。そして日蓮大聖人が法華経の上に開顕された本因本果同時不二という本来常住の事相に触れられているでしょうか。
彼の上に、そうあって欲しいと願うのは、その時の私の答えが、今なお正しいものであったと反芻されるからです。仏教学者の間では、三世因果を仏教本来の教えではなく、お釈迦さま以前からあったバラモンの教えであり、それを仏教が方便として採用したものにすぎない、という説もあるようです。
然し、たとえ三世因果の理が仏教以前のものであったとしても、それが仏教の根幹になっていることには違いはありません。若し、三世因果を否定するならば、それはもはや仏教ではなくなってしまうのです。三世因果は相対的連続の世界をあらわし、更に仏教でいう因果の同時不二は、絶対的非連続の世界をあらわしており、真実の世界は、この両面を同時に体しているのです。
世界のすべての存在は、因縁果、因縁果と流転し連続しながらも、その一瞬一瞬は因果不二として非連続的に独立し、独立しながらも、なお非連続的に連続しているのです。
法華経の本門の三宝にしても、三宝それぞれに本因本果不二の存在でした。久遠の本仏お釈迦さまも本因本果不二であり、久遠実成の果徳の仏身には、常不軽菩薩等の無量の本因の菩薩身が相即していました。如来寿量品にいう処の、
我れ本(もと)菩薩の道を行じて、成ぜしところの寿命、今なお未だ尽きず。また上の数に倍せり。
とはこのことです。
ここにいう「成ぜしところの寿命」とは、因位の久遠の菩薩行によって成就した仏果の寿命というのでなく、この寿命は、あくまでも久遠の仏身に相即している菩薩の寿命のことなのです。若し、菩薩が仏となったのであれば、その仏には、仏となったという始めがあるということになって久遠の仏ということは出来ないでありましょう。
仏とは本来衆生に内在するものであり、内在する仏が、菩薩行によって顕現されるのです。決して菩薩が仏に成るのでもなく、菩薩の因が、仏の果に変わることでもありません。
あくまでも十界は十界として常住し、互具し、相即しているものであって、成仏とは、地獄界が仏界と変革するのでもなく、畜生界が仏界と取って代わるものでもないのです。
自我偈の冒頭に、
我れ仏を得てよりこのかた、経たる所の諸の劫数、無量百千万億載阿僧祇なり。
という、ここにいう得た仏とは、既に久遠の仏であり、今ようやく完成された仏ではないのです。
ところが、因が果となり、菩薩が仏となると思いこんでいる人々は、自我偈の「自我得仏来」という「得仏」の二字を見あやまり、たとえ久遠のお釈迦さまでも、久遠の昔に仏を得た、仏身を成就することが出来たという以上、無始無終の仏ではなく、有始無終の仏ではないかというのです。その代表的な人に中国の天台大師をあげることが出来ましょう。
自我偈にいう「得仏」の真意は、お釈迦さまが無始の昔、無始久遠の菩薩行によって、本来内在していた無始久遠の仏身を顕現し、無始の九界と、無始の仏界の互具する本因本果不二の事相を生身に体現されたということに外ならないのです。
衆生内在の仏身については、大聖人が観心本尊抄に次の如く仰せられています。
我等が己心の釈尊は、五百塵点、乃至所顕の三身にして、無始の古仏なり。
「五百塵点、乃至所顕の三身にして、無始の古仏」というのは、五百塵点劫という算数も及ばない天文学的無量の時間をふくめて、その前後無始無終に、既に法報応三身即一の久遠の本仏として出現し活動されている仏のことであって、その仏身を顕現されたのは、今日の人文学史上ではインドのお釈迦さま唯一人なのですが、それと全く同一の仏身を「我等が己心」に本具しているというのです。
ここにいう「我等が己心」の「我等」とは、法華経を行じている本因妙の衆生であっても、また法華経を信じない者であっても、乃至逆謗の衆生であってもよいのです。本因妙の位に住している者は、その信一念において、自身の内外に常住し活動されているその仏を感得されましょう。本因妙の位に住していない者には、その仏を、最も身の近きにあるにもかかわらず見ることも出来ないでありましょう。いずれにせよ、正像末の三時を問わず、一切衆生は久遠実成の本仏お釈迦さまと同じ仏身を、無始以来、本来内外に具しているのです。だからこそ法華経方便品に、本仏お釈迦さまの本願として、
我れ本(もと)誓願を立てて、一切の衆をして、我が如く等しくして異なることなからしめんと欲しき。
といわれている所以があるのです。
衆生は積功累徳し、長い長い歳月をかけて次第に仏に近ずき、みずからの仏身を形成するのではありません。仏身は既に久遠実成のもの、既に無始の昔より完成されているものであって、それが本因妙の位にあって、本因本果不二の一仏乗(因行果徳の題目)を行じている中に、突如として顕現されるものなのです。それはまさしく突如としてであって、あらかじめ予期されるものではありません。相対に如何に相対をかさねても、相対の域を出るものではありません。相対が絶対に転ずるのは、まさしく突如の外はないのです。
お釈迦さまの御在世当時における有名な話として、周梨般特(別名ーチューラ・パンタカ)の成仏が伝えられています。彼は精薄児にも等しい薄馬鹿でした。兄のマハー・パンタカは衆にすぐれて賢明でした。まず兄の方がお釈迦さまのお弟子になりました。次いで弟のチューラ・パンタカも兄にさそわれるまま仏弟子に加えてもらいました。
お釈迦さまは弟のパンタカに四句の偈を与えて、覚えるように命じました。然しパンタカは自分の名前さえ忘れるほどの愚かさです。幾月もかかって、ようやく一句を暗記できたと思うと、次の句をすっかり忘れていました。何時になっても、わずか四句の偈すら覚えることは出来ません。多くのお弟子たちは彼の愚かさをあざけり嘲いました。兄のパンタカは、そうした弟の姿を恥ずかしく思い、とうとう怒って弟を精舎より追い出してしまいました。
追い出されたパンタカは、これから先、どうしてよいかも判らず、精舎の門の前に立ちすくんで泣くばかりでした。そこへ外からお釈迦さまが帰って来られました。お釈迦さまは、
「どうされたのか」
と尋ねられました。パンタカは泣く泣く兄に怒られて追い出されたわけを語りました。お釈迦さまは、やさしくパンタカの頭をなでながら申されました。
「パンタカよ、お前は私のお弟子である。私はお前の師匠である。何処へも行かなくてもよい。ここにおりなさい。何も案ずることはない。もう難しい言葉を覚えなくてもよい。これからは人々のために、人のぬぎすてた履き物をそろえたり、精舎のお掃除をしなさい」
お釈迦さまはパンタカの手をとって一枚の布切れを渡されました。それは掃除するための雑巾でした。この時、おそらくパンタカの全身には無上の歓喜が満ちあふれたことでしょう。それ以来、その精舎には毎日毎日、喜々として掃除をし、履き物をそろえるパンタカの姿がみかけられました。パンタカの手には一枚の雑巾が宝物のようににぎりしめられていました。
もはや、その雑巾は、パンタカにとってお釈迦さまの血汐のかよう付嘱の宝物でした。生きた命でした。パンタカは一日の中、何度も何度もその雑巾を頭に押し頂いたことでしょう。雑巾を押し頂くことはお釈迦さまを礼拝することであり、雑巾で精舎の柱をふき、床をふき、人々の履き物をぬぐうことはお釈迦さまと一緒になって働き、奉仕し、修行することであり、夜、すすいだ雑巾をふところにいだいて寝ることは、お釈迦さまにいだかれて寝ることであり、パンタカの日々夜々は、片時もお釈迦さまと離れることなく、パンタカの肌によってあたためられた雑巾のぬくもりに、お釈迦さまの肌の温かさを覚えしめられたことでしょう。
あの日、精舎の門前で、泣きじゃくっていたパンタカの頭をなでられたお釈迦さまの手のひらのあたたかさ、一枚の布切れを雑巾として渡される時、パンタカの手をしっかりとにぎりしめられたお釈迦さまの手の大きさ、その強さ、その温かさ、その温かさを、どうして忘れることが出来ましょう。この時、パンタカはお釈迦さまの大慈悲のふところの内に、すっかり包まれていたのです。回心は既にこの時に起きていたとも申されましょう。
その後、パンタカはお釈迦さまのそばにも近よれなかったかも知れません。多くの兄弟子たちにさえぎられて遠い末席にしか坐られなかったことでしょう。然し、たとえどんなに遠く離れていても、パンタカのふところの内には、お釈迦さまから渡された一枚の布切れ、雑巾がありました。温かい雑巾でした。お釈迦さまの血汐もかよう雑巾でした。
やがて、その雑巾も使い古されてボロボロになったことでしょう。然しそのボロボロの雑巾こそ、パンタカと共に人々の履き物をぬぐい、精舎の柱や床をふき、更に一切衆生の成仏を祈って粉骨砕身されているお釈迦さまの、尊い、輝かしい姿そのものであったのです。
多くの仏弟子の中には、掃除しかできない愚かなパンタカを嘲笑していた者も少なくはなかったでしょう。然し、どんなに軽蔑され嘲笑されても、喜々として働くパンタカは、常にお釈迦さまの温かい大慈悲につつまれ、「人々のために」というお釈迦さまの本願に生き、本願に生かされ、本願によって行動し、行動せしめられていたのです。それは、まさしく因果不二の生きざまという外はありません。
そういう生き方が始められてから、どれほどの歳月が過ぎたのでしょうか。チューラ・パンタカは舎利弗・目連と同じ輝かしい阿羅漢の位に入っていました。それは賢明な兄のマハー・パンタカも入ることの出来なかった境地であり、十大弟子の中、多聞第一とうたわれた阿難ですら、お釈迦さまの御在世中に到達することの出来なかった境地でした。
阿羅漢果とは、如来の十号の中の応供に当たり、人々より尊敬供養をうけるに価値ありとされた境地であって、仏弟子としては仏果に次ぐ修行最高の地位とたたえられたものでした。後に小乗仏教徒によって二乗的に解釈されるようになりましたが、お釈迦さまの御在世当時にあっては、決して二乗的独善の境地ではなく、まさしく如来に次ぐ菩薩の境地であったはずです。
チューラ・パンタカのひたむきな清掃行、それは自己向上のためでなく、ただひたすらに「人々のため」「人々のため」というお釈迦さまの本願に生きるものであり、全くの菩薩行、黙々たる菩薩行であったのです。従ってパンタカが発得した阿羅漢果というのも、お釈迦さまの本果に即する偉大なる菩薩果であると申されましょう。
然し、こういう偉大な境地を発得したパンタカが、そういう境地を得たからといって頭脳明晰になったわけではありません。やはり昔と同じ無知文盲であり、一句半偈すら覚えることも出来ず、自分の名前さえ忘れてしまう愚鈍であったはずです。では、どうしてこの偉大なる境地を発得することが出来たのか、ということに私たちは深く注意を払わなければなりません。
勿論、パンタカは、ひたむきな清掃行によって積功累徳しようとしたのではありません。ただお釈迦さまに命ぜられたままに、その日その日を精一杯、喜々として働いたにすぎません。人から見れば馬鹿の一つ覚えの働きにすぎなかったことでしょう。
そういう底辺のパンタカ、精博のパンタカが、賢明なる兄弟子たちの群を抜き、多聞第一の阿難をも越えて、一挙に阿羅漢果を現成したというこの事実は、パンタカに本来内在していたそれが、仏果に即する仏因の菩薩行の当処に顕現したものであることを物語っていると申されましょう。
肝心なことは、パンタカが自己内在のそれを顕現しようとしたのでなく、お釈迦さまの足下にひれ伏し、「頭面接足帰命礼」という言葉通り、我が頭をお釈迦さまの御足に接してお釈迦さまの全身を両手に戴くばかりでなく、お釈迦さまの温かい手によって、やさしく頭をなでられ、我が手をしっかりとにぎられて、お釈迦さまの大人格大慈悲にすっぽりと包まれ、お釈迦さまのその手を通して、また「人々のために清掃をせよ」というその言葉を通して、お釈迦さまの大慈悲大光明がパンタカの全身を浸透し、心のすみずみにまでも輝き渡ったということです。
更に肝心なことは、お釈迦さまより手渡された一枚の布切れそのものに、お釈迦さまの温かき息吹を感じ、生きた血汐を感じ、命を感じ、本願を感じ、その布切れを雑巾として精舎の柱をふき、床をふき、人々の履き物をふく行為が、お釈迦さまと共に働く菩薩行であったということです。そこには、もはや敢えて修行し鍛錬し功徳を積んで向上するとか、成仏を期するということもない絶対肯定の世界であり、ただただ同行二人、お釈迦さまと共に、お釈迦さまの本願に生き、生かされる無償の世界、この上ない価値にみちみちた世界であったのです。
おそらくパンタカの毎日の日常は、雑巾の語りかけるお釈迦さまの温かい声なき声を開いていたことでしょう。朝には、
「さあ、パンタカよ今日も一緒に掃除をしよう」
という声、夕暮れには、
「パンタカよ、今日もよく働いたね、楽しかったね」
という声が聞こえていたことでしょう。また精舎の柱や、一枚一枚の床、一足一足の履き物からは、
「パンタカちゃん、有り難う。今日もお釈迦さまの功徳をうけて綺麗になりました。」
という喜びの声を聞いていたことでしょう。
仏弟子たちは誰一人としてパンタカを相手にしなくても、柱や床や履き物が仲のよい友達でした。庭の樹や草も友達でした。空行く雲も友達でした。それは我此土安穏の大マンダラ仏国土でした。パンタカの行は、常住の仏国土へ入るための行でなく、お釈迦さまより清掃を命ぜられた付嘱の当初より、仏国土の中の行であったのです。
大聖人は観心本尊抄に、
釈尊の因行果徳の二法は、妙法蓮華経の五字に具足す。我等、この五字を受持すれば、自然に彼の因果の功徳を譲り与えたもう。
と仰せられていますが、パンタカの場合には、ここにいう付嘱の「妙法蓮華経の五字」を、付嘱の「布切れ」(雑巾)におきかえることが出来ましょう。題目と雑巾を一緒にするとは、けしからん、と怒る人もいるかと思われますが、パンタカにとっては付嘱された雑巾は、単なる一枚の布切れでなく、お釈迦さまの全生命のこもったものであり「因行果徳の二法」そのものであったのです。
パンタカはお釈迦さまの大慈悲の内に摂取され、因果不二の因位において、雑巾を受持しました。その受持は、雑巾を手に持っていたというのではありません。「人々のために」というお釈迦さまの本願に乗じ、仏勅のままに、雑巾がけをするという行、仏因の行、仏果の行、因行果徳の二行を修しつづけたのです。それはお釈迦さまと共に行ずる果しない行でした。到達すべき彼岸を未来にも持たず、彼岸を足下に見る充実した感謝の行でした。
この行の中に、我にもあらず、まさしく如来秘密神通の力によって、お釈迦さまの因果の功徳が譲り与えられ、群を抜き、自らは予期もしない阿羅漢果を身にそなえていたのです。観心本尊抄にいう「自然(ジネン)に」とは、次第次第に時間をかけて、というのではなく、如来秘密神通の力、如来の不可思議のはからいによって、ということであり、お釈迦さまと共に行ずる感応の行態を示しているのです。そしてその行の果報を観心本尊抄では「因果の功徳を譲り与えたもう」という「譲与」の二字にあらわしている、と申されましょう。
この譲与は、時間の経過に従って少しずつ次第に譲り与えられるのであろうという未来形ではなく、現在、如来の功徳が全一に譲り与えられているという現在形なのです。既に現在形であればこそ、観心本尊抄のこの「譲与」の言葉につづいて、
四大声聞の領解に云く「無上の宝珠、求めざるに自ら得たり」云々。
といわれ、更にこれにつづいて、
我が如く等しくして異なることなし。我が昔の所願の如く、今はすでに満足しぬ。一切衆生を化して皆仏道に入らしむ。妙覚の釈尊は我等が血肉なり。因果の功徳は骨髄にあらずや。
といわれているわけです。ここでは題目を行ずる者が、題目によって本因本果不二の久遠の本仏お釈迦さまと感応道交し、本果に即する本因妙の位に住しており、行じている題目もまた本因本果不二の仏種として行者の六根に浸透し、それによって凡夫の血肉はそのまま本仏お釈迦さまの血肉に即して躍動し、凡夫の骨髄もまた本仏お釈迦さまの骨髄に即して金剛不壊のものとなっている歓喜が語られているのです。
もし、「自然譲与」を未来形のものと見るならば、功徳の譲与を期待する明日は、何時になっても明日であり、それがたとえ修行の励みとなり、人格向上の糧とはなり得たとしても、遂に本因妙の位に住することもなく、功徳の完全譲与を得ることなく、不安は増しても安心歓喜の絶対境は得られないでありましょう。
然し、譲与とは、子供が親の財産を譲りうけるといったようなことではありません。そういう単なる他力ではないのです。親の保護をうけるだけの子供では、主体性も独立心もない軟弱な人間になってしまうものです。本仏お釈迦さまが一切衆生に譲与される因果の功徳は、一に妙法蓮華経の五字の題目であり、この題目が衆生の絶対信の心田に下種され、下種されるばかりでなく、下種された題目が、常にたゆまず強盛に唱えられ行ぜれる時、題目の因果の功徳力が、衆生本来己心中に内具されている本果に即する本因、無始の仏界に即する無始の菩薩界を薫発せしめ、潜在識下より涌発した本化の菩薩の、相・性・体・力・作・因・縁・果・報・本末究竟等という十如是が、衆生の六根に現成するのです。
衆生本具の本因に即する本果が、薫発涌出して六根に現成することを「仏身を成就する」といい、自我偈の結文における本仏お釈迦さまの本願として、
毎にみずからこの念をなす、何を以てか衆生をして無上道に入り、速やかに仏身を成就することを得せしめん。
と述べられているところであり、また衆生本具の本果に即する本因が、薫発涌出して六根に現成することを、「本化の菩薩の大地涌出」といっているのです。
一切衆生に本来、本果に即する本因、即ち本化の菩薩が内在していることは、大聖人が観心本尊抄において、衆生本具の仏身について「我等が己心の釈尊は、五百塵点、乃至所願の三身にして、無始の古仏なり」と仰せられた後、これにつづいて、
経に云く「我れ本(もと)菩薩の道を行じて、成ぜし所の寿命、今なお未だ尽きず。また上の数に倍せり」等云々。我等が己心の菩薩等なり。
地涌千界の菩薩は、己心の釈尊の眷属なり。例せば、太公、周公旦等は周武の臣下、成王幼稚の眷属、武内の大臣は神功皇后の棟梁、仁徳王子の臣下なるが如し。上行・無辺行・浄行・安立行等は我等が己心の菩薩なり。
と言明されているところです。
これによれば一切衆生すべてのものは、無始久遠劫来、十界互具して本因本果を相即不二のものとして具し、久遠の本仏お釈迦さまの仏身も、本化の菩薩の菩薩身も同時不二のものとして内在していることになります。然し、これを涌出顕現せしめることは難中の難というよりは、むしろ不可能に近いものです。ここに本仏お釈迦さまの本願により因行果徳の題目が仏種として衆生の心田に下種され、如来秘密神通の力によって、題目の如説に行ぜられる処、本具の本因を薫発開顕して本化の菩薩たらしめ、本具の本果を薫発開顕して仏身を成就せしめるのです。
次に本仏お釈迦さまの因果と、題目の因果と、本化の菩薩の因果と、衆生の因果を、顕現、秘奥に配して図示すれば次の如くでありましょう。
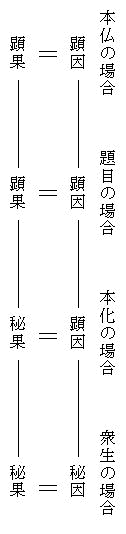
上の図を説明すれば、久遠の本仏お釈迦さまの仏身には、久遠の本因と、久遠の本果とが、共に相即しながら悉く顕現しつくされています。因行を修して仏果を得たのであるならば、因は果と変わり、因行は果徳の裏に包摂され秘奥されたということになりましょう。秘因顕果ということになってしまいます。
然し実はそうでなく久遠本来不二相即している本因と本果とは、共に顕現しつくされているのであり、本果に即して本因行を修して来た無始久遠劫来の無量の本化の菩薩は、過去の時間の中に滅したのでもなく、本果に摂取されて消えたのでもなく、悉くお釈迦さまの仏身に顕現して、なお生々として本化の行を修し、本願に生きて活動しつづけているものであって、仏身における菩薩行は未来永劫に亘って絶えることはないのです。
また本因に即する本果の場合も同様であり、無始久遠劫来の無量の過去仏も悉くお釈迦さまの仏身に顕現し、毎時悲願の本願に活動され、その寿命・活動は未来永遠に尽きることはないのです。
ここに、本因本果不二というお釈迦さまの仏身に、無量の本化の菩薩のエネルギーと、無量の諸仏のエネルギーの不二相即する、その強力さ、その偉大さに瞠目せざるを得ないものです。そしてこの本因本果のエネルギーが、そのまま本仏お釈迦さまの本願によって妙法蓮華経の題目の五字七字に顕現され、衆生成仏の仏種とされているのです。よく引用する観心本尊抄の、
釈尊の因行果徳の二法は、妙法蓮華経の五字に具足す。
という因行と果徳とは、共に顕現し、互いに相即しているものであり、そうであればこそ、題目を受持信行する者は、従果向因の仏果に摂取されながら、従因至果の本因行を修するということが出来るのです。この時、修行者は、既に本仏お釈迦さまの本因行を、お釈迦さまと共に修していると申せましょう。
客体の本仏お釈迦さまの本果妙に即しながら、その本因妙を修する者を本化の菩薩というのですが、この菩薩に内在する因果は、顕因秘果であり、秘果でありながらも、その秘果は本仏お釈迦さまの顕果と一体のものである、というのです。
常不軽菩薩は、過去仏である二萬億の威音王如来の中、最初の威音王如来の滅後像法時代の末に出現し、一切衆生に対して「我深敬汝等……」という二十四字による礼拝授記行を敢行し、生々世々に二千億の日月灯明如来に給仕し、更に二千億の雲自在灯王仏に給仕し、また更に千萬億の過去仏に給仕して法華経を受持宣布し、今番、釈迦牟尼如来としての仏身を成就したとされていますが、このことは常不軽菩薩の本因行の久遠を具体的に示すと共に、釈迦牟尼如来としての仏身の現成は、その本因が本果となったのではなく、久遠の顕因に即する久遠の秘果の顕発を示すものであり、しかもその秘果が無量の過去仏の顕果と等一のものであって、更にお釈迦さまの顕果に無量の過去仏の顕果の包摂一味とされていることを物語っているのです。
常不軽菩薩は無始久遠劫来、常不軽菩薩という同一の名のもとに、生々世々、無量の過去仏に給仕しながら法華経を受持宣布したのですから、その因行の久遠にしても、因行の無量の功徳の絶大なることも理解されやすいことでしょう。然しお釈迦さまの仏果と、無量の過去仏の仏果が等一であることは判っても、そのお釈迦さまの仏果に、無量の過去仏の仏果が包摂一味となっていることについては理解し難いものがあるかも知れません。
然しながら、若し仮に常不軽菩薩が生々世々に仕えた威音王如来や日月灯明如来、雲自在灯王如来等々の過去仏の名が、同一に釈迦牟尼如来であったとしたならば、常不軽菩薩が生々世々無量の釈迦牟尼如来に相即給仕し、仏果を成じて釈迦牟尼如来となった時、今番出世の釈迦牟尼如来に、無始以来の無量の釈迦牟尼如来が同体一味となっていることが納得されましょう。如来寿量品は、このことを明らかにしようとして、
処々にみずから名字の不同・年紀の大小を説き、またまた現じて当に涅槃に入るべしと言い、
と述べているのです。
涅槃経には「一切衆生悉有仏性」と説かれていますが、日蓮大聖人は法華経の真によって「我等が己心の釈尊は、五百塵点、乃至所顕の三身にして、無始の古仏なり」と仰せられました。更に大聖人は己心中の本果に即する本因を明確にして、「地涌千界の菩薩は、己心の釈尊の眷属なり」ともいい 、「上行・無辺行・浄行・安立行等は、我等が己心の菩薩なり」とも仰せられています。
この言葉は、仏滅度後仏教史上、三国未曾有の大宣言であり、みずから本化上行菩薩の自覚に立たれた大聖人にして始めて宣言し得ることでありましょう。この宣言は、佐渡流島中、一ノ谷の滴居において撰述された観心本尊抄の中に述べられているものですが、おそらく大聖人の己心中には「五百塵点、乃至所顕の三身にして、無始の古仏」という久遠実成の本仏お釈迦さまと、これを中心として四方に囲繞する上行・無辺行・浄行・安立行の四大菩薩を始め、六萬恒河沙の本化の菩薩衆の本因本果不二一体となった行動世界が厳然として確立していたことでしょう。
そしてそれは客体である霊山虚空会上、本門八品の儀相の己心に投影した影ではなく、本因本果不二の題目が、仏種として大聖人の心田中において胎動し、全身に横溢することによって、それに比例して大聖人本具のそれが、行動的に顕在化して来たものであり、大聖人は客体の霊山虚空仏界の中にありながら、同時にその全体を自己の全身に背負う主体的存在になっておられた、と申されましょう。
さきに示した本仏と題目と本化と衆生の因果の秘顕に、話をもどせば、本仏お釈迦さまの仏身にしても、その題目にしても顕因顕果同時不二のものであり、本化の菩薩にあっては顕因秘果同時不二、衆生にあっては秘因秘果また同時不二のものであり、これは無始無終に変わることなく、しかもいずれの秘因も顕因も因として一であり、いずれの秘果も顕果も果として一のものであるのです。
蓋し、ここでよくよく注意しておかねばならないことは、衆生己心に秘奥する秘果が、客体として実在する久遠の本仏お釈迦さまと全一のものであるということから、如何に題目を修するとはいえ、客体の本仏お釈迦さまを軽視したり無視して、己身本尊観に堕ち入ってはならないということです。己身本尊を主張した代表的偽書として、次の諸法実相抄をあげることが出来ます。
されば釈迦・多宝の二仏というも用の仏なり。妙法蓮華経こそ本仏にてはおわし候え。経に曰く「如来秘密神通之力」これなり。如来秘密は体の三身にして本仏なり。神通之力は用の三身にして迹仏ぞかし。凡夫は体の三身にして本仏ぞかし。仏は用の三身にして迹仏なり。然れば釈迦仏は我等衆生のためには主・師・親の三徳を備え給うと思いしに、さにては候わず。返って仏に三徳を蒙らせたてまつるは凡夫なり。
これは法本尊から己身本尊へと転落していった顛倒の妄見邪説にすぎません。こういう邪説が大聖人の思想として羅り通っている間、日蓮教学の正統は確立されないでありましょう。
たしかに久遠の本仏お釈迦さまが衆生に対して主師親の三徳を備えているといっても、雲のかなたの遠い遠い観念的な存在にしか考えられないかも知れません。然しその仏が自己自身の内に理仏としてでなく、生きた命として実在していると知り、しかもそれを顕わすには自力では顕わしようもないとあきらめ、仏のさし述べる題目を受持するならば、題目の生きた因果の功徳を媒介として、遠いかなたにしか考えられなかった久遠の本仏お釈迦さまが眼前に立たれるばかりでなく、自分の全身から環境のすべてを包摂している輝かしき大慈悲の尊容を見、同時に己心内具の仏が、そこにあらわれていることを見ることが出来るのです。
自己内在の仏を内在するままに、本仏お釈迦さまの現身に顕現されていると見、本仏お釈迦さまの命が自己の全身に遍満して芳香を薫じ、光芒を放っていると感ずる時、自己をかくも価値あらしめる本仏お釈迦さま、しかも自己本来の命と同一体のお釈迦さまに対して、切々として主師親の三徳の偉大さが感謝されるのです。
仏とは救済するばかりでなく、現在生きている私自身を本当に価値づけ、その価値を知らしめ、価値に法悦せしめるものでなければなりません。精薄にも等しい愚鈍なチューラ・パンタカは、精舎の門前で、お釈迦さまに頭をなでられ、手をにぎられ、一枚の雑巾を渡された刹那、お釈迦さまの大いなる命に摂取され、その命に生き、生かされる人間になっていました。それからの彼の生活は、仏の本願に生き生かされる毎日でした。この上、何ものも求めるものもない無上の価値に充満した日常でした。パンタカの物語は、法華経信仰に生きる人々に、多大の教訓を示していると申されましょう。