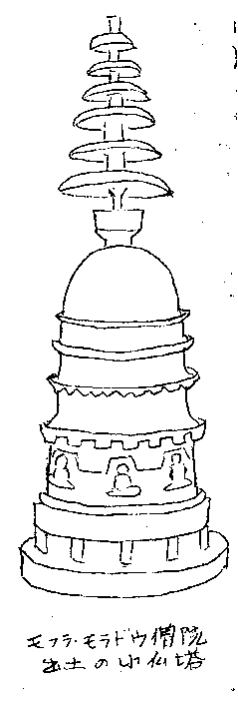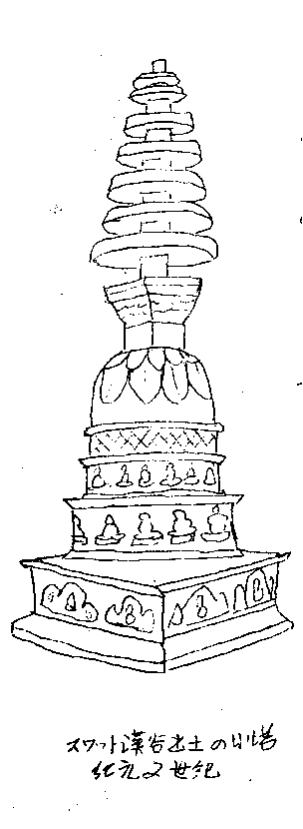����z�@�k��\����l�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@�@�{���̕�F�ɕt�����ꂽ�{�ł̘œ��Ƃ��̍\���@�\�\ ��i
����R�ʕt���ƈ�鑦�O��̖@��
�@����܂Ŏ��́A�@�،o�@���_�͕i�ɂ����ċv���̖{�����߉ނ��܂��A�{���̕�F�ɑ��ĕʕt�����ꂽ���̂́A��@�t�ɂ��@�،o�̎��H�����łȂ��A�N�����{�Ƃ��������{���̌����ł���A���̂��Ƃɂ���ċv���̖{��̎O���������A�Əq�ׂė��܂����B
�@�N�����{�̕������A�{���̕�F�ɂ���Č�������A��ㅁE�e�d�����Ƃ���̋v���̖{�����߉ނ��܂̕����ł���A�O�k���E�ɂ����Ă͌Í����\�L�̕����ł���Ƃ������Ƃ��咣�������̂́A�]��ɂ����Ȃ������ɁA��������l�X�̒��ɂ͋����ꂽ�l������ꂽ���ƂƎv���܂��B
�@�������A�N�����{�̕t���́A�Ƃ�_�͕i�����ł͂Ȃ��̂ł��B�O�ɂ����p���Đ����������Ƃ�����܂����A�@�،o��F�{���i���\�O�ɂ́A���̂悤�Ɏ�����Ă��܂��B
�@���̎��ɓ��������A��؏O���،���F�ɍ������܂킭�A
�u�P�j�q�A�䟸�ς̎�����A�Ős�̎�����ʁB���A������{���ׂ��B�䍡��ɂ����ē��ɔʟ��ς��ׂ��v
�@�܂���؏O���،���F�ɒ������܂킭�A
�u�P�j�q�A��ꕧ�@�������ē��ɏ��݂��B�y�я��̕�F�A���q�A���Ɉ��ӑ����O�W�O���̖@�A�܂��O����̎���̐��E�E���̕���E���A�y�ы����̏��V�������Ď������ɕt���B�䂪�œx�̌�A���L�̎ɗ��܂����ɕt�����B���ɗ��z�����ߍL�����{��݂��ׂ��B��������̓����N�ׂ��v
�@�ܘ_�A�����ɂ������������Ƃ͉ߋ����̂��Ƃł���A��؏O���،���F�Ƃ͌�̖�F�̂��Ƃł�����A��F�����������u��������̓��v�ɂ����锪���l��̕����́A�_�͕t���ɂ����Ė{���̕�F�Ɍ�������悤�t�����������Ƃ͈قȂ������̂ł���A�����ɖ{瑂̑��Ⴊ���邱�Ƃ͐\���܂ł�����܂���B
�@�R���A����ɂ��Ă���F�ɕt�������u��������̓��v�͖{�����ł���A���ɂ̕t���ɂ́A���@�t���ɂ��킹�Ė{�������t��������Ƃ����p�^�[����������Ă���̂ł��B
�@�Ȃ��_�͕t���ɂ́A�t���̂悤�ȁu���̕�F�A���q�v�u�y�ы����̏��V�v�A���тɁu�O����̎���̐��E�v�Ƃ��������y�A�����y�̒��́u���̕���E���v�Ƃ������̂͋L����Ă��܂��A�R�������͓��R�A�t���ɂƂ��Ȃ����̂ł����āA�_�͕t���ɂ͋L�q���ȗ�����Ă���ƌ���ׂ��ł���܂��傤�B
�@�Ⴕ�A�����ł���Ȃ�Ζ{���̕�F�ɂ́A���ɖ{�����߉ނ��܂̕����y���͂��߁A�����y�̒��̕���E���͂������̂��ƁA���߉ނ��܂ɂ���ċ������ꂽ���ʂ�瑉��̕�F���A���̑��q�������{�����ő��Ƃ��ĕt������Ă���Ɛ\����܂��傤�B�����Ė@�،o��M���鎄�������A�܂��Ƃɖ{���̕�F�ł���Ȃ�A�������̓���A�s�Z����A�����ł������ł������y�͌������A�{瑗���̕�F�E���̕���q�A�i��̏��V�͏[�����đ�}���_���̕������������Ă���Ƃ������Ƃ��o����͂��ł��B�����ɑ�}���_�������y�̒��S�҂Ƃ��ċv���̖{�����߉ނ��܂�{���Ƃ��镧������������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃ͐\���܂ł�����܂���B
�@���āA�����ŐG��Ă����˂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���@�@�̓`���I�@�w��ɂ����Ă���u��鑦�O��v�Ƃ����@��̂��Ƃł��B������w���@���w��������芧�s����Ă���u���@�@�ǖ{�v�i��l���Łj�ɂ́A
�@���̈�O�O��́A���̂܂ܖ{��̊̐S�ƂȂ邱�Ƃɂ���ċ�ۉ����A��ۉ����邱�Ƃɂ���Ĕ��@�ƂȂ�A��唒�@�Ƌ���邱�Ƃɂ���āA�O��̖��s�ɊJ�o������̂ł���B
�@�Ƃ����A�X�ɁA
�@���̌��̋��@�ɂ��~�ς̕��@�Ƃ��ĎO��̍s���J�����B
�@�Əq�ׁu��鑦�O��v�̖@�傪�m�肳��Ă��܂����A�������ɖ]���������́A���̒��u���@���w�̌����v�̒��ŁA�u�O���@�̐����Ƒg�D�v�Ƃ������i��Ł`��l�Z�Łj���������A���ɐ�t�̏�������ނ��Ȃ���A����@�ƎO���@�Ƃ̊J���W���ڂ�����������Ă��܂��B
�@�����ł��]�����́u�O���@�͍s��̕��K�ł���v�ƒf�肵�A�O��̉��ɁA�O����J�������߂���̑��݂��咣����Ă��܂����A�s�R�łȂ�Ȃ����Ƃ́A���́A������������ݒ肵�Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂��A�Ƃ������Ƃł��B�]�����̏��������F�A��鑦�O��Ƃ����O��ɗ����������ɂ����܂���B�ʂ����Ă��̑O��͐��������̂Ȃ̂ł��傤���B�ǂ����Ă��������O�N���Ă����̂ł��傤���B�O�鑊���A�O���́A�O���s�O�A�s�O���O�ŏ[���ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�R��ɁA�O�鑊�����咣���邽�߂ɍX�Ɉ��𗧂Ă�Ȃ�A���̈�邪�O������炵�߂鍪���I���݂ƂȂ�A�]���ĎO��̒��́u�{��̖{���v���s��̎{�݂ɂ����Ȃ����̂ƂȂ�A�O��̒��́u�{��̑�ځv��}��Ƃ��Ĉ��̗��������߂�Ƃ����s�@���N���ė��邱�ƂɂȂ�̂ł��B����ł͋��s�؈�̂Ƃ͂����Ȃ��Ȃ��Ă��܂��܂��傤�B�O��͐����̎�i�łȂ��A�ړI���̂��̂ł���A�����̓������������̂łȂ���Ȃ�܂���B
�@�������ɓ��@�吹�l�́A���@�@�،o�̌��i���@�̌��j�Ƃ����A�����͓얳���@�@�،o�̎����i���@�̎����j�Ƃ����A�����Ɂu���@�̌������v�Ɛ\����܂����B�R���A���@�̌����O����J�������߂���ł��Ȃ���A���@�̎����������J�o���ꂽ�{��̑�ڂł��Ȃ��̂ł��B�吹�l�͊ϐS�{�����ɁA�L���Ȍ��t�Ƃ��āA
�i�v���̖{���j�ߑ��̈��s�ʓ��̓�@�́A���@�@�،o�̌��ɋ���B�䓙�A���́i���@�́j��������A���R�ɔނ́i�{�����߉ނ��܂́j�i�v���́j���ʂ̌��������苻���������B
�@�Ǝ�����Ă��܂����A�����ł������@�̌��͕t���̑�ڂł���A������O�������铖���ɂ����āA�������̂܂ܓ얳���@�@�،o�̎����ƂȂ�̂ł����āA���̖��@���A�����̖��@�����ɓ������s�ʓ��̓�@�Ȃ̂ł��B
�@�������ϐS�{�����ɁA������L���ȕ��͂Ƃ��āA
�@���̖{��̊̐S�얳���@�@�،o�̌��ɂ����ẮA���Ȃ�����E���ɂ������t�������܂킸�B�����ɂ����₻�̖�������B�����n�O��E�i�̖{���̕�F�j�������Ĕ��i������āA�����t�����������B
�@���̖{���̑̂��炭�A�{�t�̛O�k�̏�ɕ�ɋ����A�����̖��@�@�،o�̍��E�Ɏ߉ޖ��E���B�ߑ��̘e�d�͏�s���̎l��F�B����E���ӓ��͎l��F���ő��Ƃ��Ė����ɋ����A瑉������̑召�̏���F�́A�ݖ��̑�n�ɏ����ĉ_�t���������邪�@���B�\���̏����͑�n�̏�ɏ����������A瑕�瑓y��\���邪�̂Ȃ�B
�@�����̔@���{���́A�ݐ��\�]�N�ɂ���Ȃ��B���N�̊Ԃɂ��A�������i�Ɍ���B
�@�Ǝ�����Ă���u�����̖��@�@�،o�v���A���͕t���̑�ځA�O��̒��́u�{��̑�ځv�Ȃ̂ł��B���݂������]�����m�́u���@���w�̌����v�i��Z�ܕŁj�ɁA
�@�������@�����u�{�����v�ł͗�R�����i�̋V���ɂ����āA�_�͕i�t���̋V�ɂ���Ď��^�������ł���ƍl������B
�@�Əq�ׁA�X�Ɂi��Z�Z�Łj
�@���@�t���̗�R���i�̋V����{���U�̂ƌf���āA������u�������@�@�،o�v�Ƃ����B���̌����t���̗v�@�ł��邱�Ƃ͖����ł���B
�@�Ƃ����A�����ŁA
�@�߉ޑ������ŁA���̖��@�͖{���ł͂Ȃ��B
�@�ƒf������Ă��܂��B�ꑸ�l�m�{���`���咣���ꂽ�]�����m���A��}���_�������̑�ڂ��A�u�t���̗v�@�ł���v�Ƃ����A�����āu�{���ł͂Ȃ��v�Ɣے肳���̂����R�̂��Ƃł��傤�B
�@�R��ɁA���X�ɂ��ē��@���w��_����l�X�́A��鑦�O��̑O��ɗ����āA��}���_�������̑�ڂ��A�@�{���Ƃ݂�ɂ���A�l�@�s��̖{���Ƃ݂�ɂ���A�Ƃ������O������炵�߂鍪���̈��A�O�g����Ȃ�v���̖{���̖@���ƍl���A�����̂��߉ނ��܂����g瑕��Ɖ����Ă��܂��Ă���̂ł��B
�@��鑦�O��̖@�傪�A�����̂��߉ނ��܂����g瑕��Ƃ݂Ȃ��Ɏ����ẮA���͂�@�،o���掂���`�Ƃ����ق��͂���܂���B���̂Ȃ�A�����̂��߉ނ��܂݂�����@�����ʕi�ɂ����ċv���������J������Ă��邩��ł��B
�@�������ɎO��͖{���������Ă�����̂ł�����A�O�鑦��Ƃ͐\����܂��傤�B�R���A����̈�Ƃ́A�����ĎO��̐[���ɂ����ĎO����J�������߂鍪���I����@�Ƃ������݂��������̂ł͂���܂���B�����������݂͂Ȃ��̂ł��B��}���_�������̑�ڂɂ��Ă��A����͌��ۊE�̏\�E�z�����{�̊E����A�����̂��܂˂��P���悤�ɁA�\�E�����܂Ȃ��Ƃ炵�Ă���Ƃ������̂łȂ��A���E�̏������͂��߂Ƃ��ď\�E�̂��ׂĂ̏O�����A�ٌ������ɏ�������Ă����ڂ��A���Ƃ��Ė@�E�S�̂ɍ����A���Ƃ��Ė@�E�S�̂ɋP���킽���Ă���̂�����킵�Ă���̂ł��B
�@�܂��}���_�������̑�ڂ́A����@���Ɠ����̋V���𐮂���ꂽ�v���̖{�����߉ނ��܂��A���s�ʓ��̓�@�i���ʕs��j���̂��̂Ƃ��ĕt�����ꂽ�{��̑�ڂł���A�{��̑�ڂ���z����{���̕�F�̏o�����鎞�オ�A���Ō�̖��@��������ł�������A�_�͕i�̕ʕt���ɂ����āA�{�������Ƃ��Ă̋N�����{����������Ă����̂ł��B
�@����܂ł̓��@���w�ɂ����ẮA�{���������Ӗ����Ă���_�͕i�ʕt���̋N�����{�̑厖�ɂ��ẮA�w�NJS���͂���Ă��܂���ł����B�����Ė@�،o�����H���铖���́A���Ƃ����̒��ł����Ă��A�т̒��ł����Ă��A���̉��ł����Ă��A�����͑m�[�A���߂̎ɂł����Ă��A�����͓a���A�R�J�L��ł����Ă��A���̔@�����Ƃ킸�A�����u��������v�ł���A�Ƃ������Ƃ͋������Ă��Ă��A�������ꂪ�N�����{�̎��H���R������������̂ł��邱�Ƃɒ��ڂ����A�܂��ċN�����{���{���������Ӗ����Ă��邱�ƂɋC�t�����̂́A�܂��ƂɋH�ł������悤�ł��B
�@�t���̑�ڂ��J���A�O�邪�������Ƃ����̂��A�N�����{�̕t�����{���������Ӗ����Ă��邱�ƂɋC�t���Ȃ�����������N���Ă��������Ƃ��\����܂��傤�B�Ⴕ�A�N�����{���v���̖{�����߉ނ��܂�{���Ƃ��đ������邱�Ƃ�t���������̂ł���ƒm���Ă����Ȃ�A�����͈��̖��@�����O�邪�J�o�����Ƃ����������N����Ȃ�������������܂���B����A���������������N�����K�v�͂Ȃ������Ɛ\����܂��傤�B
�@��鑦�O��Ƃ����@�傪�A�吹�l�̖Ō�A�����̍����猾���͂��߁A�ǂ������w�������ɂ���ċ��w�I�ɑg�D����Ă��������m��܂��A�]�����m�́u���@���w�̌����v�̏��_���A�ŋ߂����Ƃ��������ꂽ���̂Ƃ����邩���m��܂���B�R���A�O��̍���Ɉ��������A���̈����O�邪�s��̕��K�E�{�݂Ƃ��ĊJ�o���ꂽ���̂ł���Ƃ��������ɂ́A�����A�^�����邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł��B�O�鑊���A�O�鑦���\�����邽�߂Ɉ�鑦�O��Ƃ����ɂ��Ă��A���������\���́A����܂����v�z�ɑ�����₷���댯���𑽕��ɂ����Ă�����̂Ƃ����˂Ȃ�܂���B�ނ���O�鑦��A�O���̂Ƃ����ɗ��߂āA��鑦�O��Ƃ����\���͔p�~���ׂ��ł���܂��傤�B
�@�_�͕i�ʕt���̒i�ɂ�����N�����{�̕t���́A�{��̖{�������������������̂Ƃ��āA�v�炸���吹�l�̖Ō�ɐ������A�����ł͓��@���w��A���ȋʏ��̔@�����Ȃ����Ɏ����Ă�����O��̖@����A�ے肷���ʂ������Ă���A�Ǝv���ĂȂ�Ȃ��̂ł��B
�@�]�k�ɂȂ�܂������A���ɖ{��̖{���������Ӗ�����N�����{�̕����A�Z�ݍP�͍��̖{���̕�F�ɂ���đ�������A��ㅘe�d�����v�������̖{�����߉ނ��܂̕����A���̋v���̖{�����߉ނ��܂̕����̍\���ɂ��čl���Ă݂邱�Ƃɂ��܂��傤�B
���v���̕����\��
�@������w���_�������������m�́A���N�O����\���ɏ��ł��ꂽ�u�k�Ђ́u���E�̗��j�v�V���[�Y�̑�܊��u�K���W�X�̕����v�i��l�l�Łj�ɁA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
|
�J�j�V�J���Ȍ�̐���
�@�J�j�V�J���̖v��ɂ̓��@�[�V�V�J���i�����ܓ�`��ܘZ�����j�A�t���B�V�J���i�����l�`�ꔪ�������j���Â����B�i�Ȃ��t���B�V�J���̖萢�ɃJ�j�V�J�̂������Ƃ��m���Ă���j�B
�@�t���B�V�J�̂��Ƃ��p�������́A�����炭���@�[�X�f�[���@(vasudeva) �ł���B���k�C���h����уq���h�D�X�^�[���ɂ��镧���̑����̃X�g�D�[�p�́A��Ƃ��āA���̃��@�[�X�f�[���@���̎����݂��ꂽ�Ƃ݂��Ă���B�����@���Ă݂�ƁA���̉��̂Ƃ��̉ݕ����Ƃ��ɑ��������邩��ł���B
�@���̗��j�I��������݂�ƁA�u�@�،o�v������ꂽ�̂́A�����炭���@�[�X�f�[���@���̂Ƃ��ł��낤�A�ƍl������B���̂킯�́A�u�@�،o�v�ɂ����Ă̓X�g�D�[�p�̐��q���ɓx�ɍ�������Ă��邩��ł���B
�@�O���I�̒��t�A���@�[�X�f�[���@���́A�y���V���̐V�����T�T�������i���Z�`�Z�l��j�̃V���[�v��(shapur)�ꐢ�Ɛ���Ċ��S�Ȕs�k���i�����B���̂Ƃ����琼�k�C���h�̓C�����̉e������悤�ɂȂ�A�N�V���[�i�鍑�̓C���h�ɂ����Ă͐��͂����Ă��A�N�V���[�i���͂��̌�̓J�[�t�����ƂȂ����炵���B |
|
�@����ɂ��Β������m�́A���k�C���h��q���h�D�X�^�[���n���̕�����蔭�@���ꂽ�ݕ��̐����琄���āA�����̕����͎�Ƃ��ăN�V���[�i�����̃��@�[�X�f�[���@���̎���Ɍ������ꂽ���̂ł��낤�Ɛ��肵�A�X�Ɉ�،o�̒��ł��ł������������q�����������o�T���@�،o�ł���Ƃ��납��A�@�،o�����@�[�X�f�[���@���̎���ɕҎ[���ꂽ���̂ł��낤�Ɣ�肳��Ă���̂ł��B
�@�ܘ_�A���̌����͐���̈���o����̂ł͂���܂��A�@�،o�����̔w�i�Ƃ��āA�N�����{�̑S�������z�肷�邱�Ƃ͒��ڂɂ�����������̂ł���܂��傤�B�����A�@�،o�o�T�̒��ł́A���\�L�̑��̑�n�O�o���͂��߂Ƃ��āA�����ɕ������{��������Ă���A���������̋V���̂��Ƃɖ{�唪�i�̑厖�������ꂽ�����ɂ���Ă��A�@�،o���k���@���ɕ����𐒔q���Ă������Ƃ������Ƃ��A���Ȃ��������̂ł��B
�@�R���A�@�،o�̐����N������@�[�X�f�[���@���̎���Ɍ��邱�Ƃ͊댯�ł���܂��傤�B������������w�����̓c���F�N�t�́A�����V���́u�@�،o�v�i�l�l�Łj�Ɏ��̔@�������N����肵�Ă��܂��B
|
���Ȃ킿�A���֕i�����w���w�l�L�i���܂ł���ނƂ��A����\�N���̐����ƌ��Ȃ��A�@�t�i��\������ݕi���\��܂łƏ��i���Ƃ���ނƂ��A�����Z�Z�N����̐����ƌ��Ȃ��A��F�{�n�i���\�畁����F�����i���\���܂ł��O�ނƂ��A�����܁Z�N����̐����ƌ��Ȃ��̂ł���B�c�c�i�����j�c�c�B
�@���̍Ō�𐼗��܁Z�N����ƌ��Ȃ����̂́A��Z�Z�N�O��̏o�g�ł���i�[�K�[���V���i�i�����j�́u��q�x�_�v�ɁA�u�@�،o�v�̍Ō�̏͂܂ň��p����Ă��邩��ł���B |
|
�@����ɂ��Β������m�Ɠc�����m�Ƃ̖@�،o�����N��Ɋւ��錩���ɂ́A���҂Ƃ�����Ȃ��瑊���ȊJ��������悤�ł��B�R���A���̂�����ɂ��܂��Ă��A�@�،o���J�j�V�J���_�Ƃ���N�V���[�i��������ɐ����������Ƃ́A�قڊm���ł���܂��傤�B���̃N�V���[�i�����������������ɂƂ��āA����剤�̃}�E���������Ɏ����d��ȉ����ł������̂ł��B
�@�ʏ�A�N�V���[�i�����͌������Ƃ������A�N�V���[�i���̓g���R�l�Ƃ��C�����l�Ƃ������A�����ł̓T�J�����g�J�����ł��邱�Ƃ��w�E�̒���ɂȂ��Ă���悤�ł��B�N�V���[�i���͋I���O��̍��A���k�C���h�ɐN�����A�₪�Ē����A�W�A�E�C�����E���C���h��̓y�Ƃ��A�V���N���[�h���͂��ߊC��q�H�̎劲�ʏ��H�����������A���̎劲�H���ɂ���ċ���Ȏ��{��~�ς���Ƌ��ɁA���������̗Z�����v��A�K���_�[�������E�}�g�D���[������n�������̂ł��B
�@�������m�́u�K���W�X�̕����v�i��l�Z�Łj�Ɏ��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
|
�C���h�ɂ����ď��Ǝ��{�̐��͂������Ƃ��L�������̂́A�N�V���[�i��������ɂ����Ăł���B��敧�����o�������̂́A���̎����ɂ����Ăł��������A�������l�̐��͂����債���Ƃ�������́A��敧�T�̂����ɂ����f���Ă���B���Ƃ��u�@�،o�v�i���\�M��i�̒��ҋ��q��栂��j�ɁA����̑�Ȓ��҂̗ՏI�̂��肳�܂������āA
�@�u�I����Ɨ~���鎞�ɗՂ�ŁA���̎q�ɖ����A���ɐe���E�����E��b�E�����E���m�����ނ�ɁA�F�������łɏW�܂�ʁv
�@�Ƃ����B�ЂƂ荋�x�ł���ɂƂǂ܂炸�A��������ؕ|��g������悤�Ȏ��{�Ƃ̑��́A���ɉݕ��o�ς̐i�W��������łȂ���Ό���ė��Ȃ��͂��ł���B�������A������������Ȏ��{�Ƃ̑��́A���̌�̃C���h�ɂ͌����Ȃ��Ȃ����̂ł���B |
|
�@����Ȏ��{�Ƃ̏o���́A�@�،o栚g�i�̒��ҋ��q��栂��ɂ�������Ă��܂����A����͖@�،o���c�O��҂̒��ɁA���������厑�{�Ƃ������Ƃ����̂łȂ��A�����������{�Ƃ̌Q���Љ�w�i�Ƃ��Ď��݂��Ă������Ƃ��������̂ł���܂��傤�B�@�N�V���[�i�����̏��Ɨ��ʂ́A���H�����邱�ƂȂ���A�C���_�X�͂�����A�C����o�ă��[�}�֒ʂ��邱�Ƃł����B�ϐ�����F����i�ɁA
�@�����͋��C�ɕY�����āA�������S�̓���ɁA�ނ̊ω��̗͂�O���A�g�Q���v���邱�Ɣ\�킶�B
�@�Ƃ���̂��A�p�ɂȊC��f�Ղ̈�[����Ă���̂ł��B��C���h�ɂ����閳���̐ΌA���@�̑����ɂ��Ă��A�A���h���n���ɂ�����ʎ�n��敧���̋��N�ɂ��Ă��A���[�}�Ƃ̊C��f�Վ��{�̔w�i�Ȃ����Ă͍l�����Ȃ����Ƃł��B
�@�u�K���W�X�̕����v�i��O���Łj�ɁA�N�V���[�i�����̎��{�̒~�ς����̂悤�ɏЉ�Ă��܂��B
|
�@���̎���ɂ́A�C���h���烍�[�}�ɗA�o���ꂽ����Ț��ʕi�ƌ����ɁA���[�}���������ʂɈړ����ꂽ�B�N�V���[�i�鍑�̏��l�̓��[�}�Ƃ̌��Ղ��J���A���E�����E��E�����Ȃǂ��ă��[�}�̉������l�������B
�@�v���j�E�X�̓`����Ƃ���ɂ��ƁA���̓����C���h�́A���N�܁Z�Z�Z�� sestertius �̋������[�}����������������A����ɑ��đ���ꂽ���i�́A�����̈�Z�Z�{�Ŕ���ꂽ�Ƃ����B�lsestertius
����denarius�ł���A�E�̋��z�́A�قڎl�܁Z�Z�Z�|���h�ɑ�������B�����̊C��f�Ղ̋K�͂��l����ƁA����͋���Ȑ����ł������ɂ������Ȃ��B
�@�����āA�N�V���[�i�鍑�̔e���̊m���A�Ȃ�тɂ���ɂƂ��Ȃ����X�̕������ہA�Ƃ��ɑ�敧���̋����́A���̂悤�ȎЉ�I��Ղ����͂Ȃ��ė������邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂ł���B
�@�N�V���[�i���͖{���A�V�q�R�n�����ł������Ƃ����Ă��܂����A�����������r�������v�閯���ł�����������A����E�C��̊댯�Ȗf�Ղ��E���ɂȂ��Ƃ��邱�Ƃ��o�����̂ł���܂��傤�B�Ⴕ���C���h�̓y���_�k�����ł������Ȃ�A����v�������Ƃ���o���Ȃ����������m��܂���B |
|
�@�N�V���[�i�����̉��̒��̑剤�̓J�j�V�J���ł����B�J�j�V�J���͐���V���N���[�h�̗v���ł���R�[�^���̏o�g�Ƃ����A�R�[�^�����o�����ē쉺�������ɁA�܂��o�����̂̓M���V����ł������Ƃ����Ă��܂����A�o�g���R�[�^���Ƃ����Ă��邾���ɒ����Ƃ̖f�Ղ�����ƂȂ�A��s�𐼖k�C���h�̃y�V���[�����ɂ����A�����Ɏ��{��~�ς��A�L��ȗ̓y�̔e�����m�����A���Ղ̖{�����߂�Ƃ��A���R�A���̌ď̂��e���̉��̌ď̂������ɗp������悤�ɂȂ��Ă��܂��B
�@�u�K���W�X�̕����v�i��l�Z�Łj�ɁA
|
�@�N�V���[�i����̔蕶���݂�ƁA�鉤�̏̍��Ƃ��āA�V���[�q�A�����[�_�A�}�n�[���[�W���A���[�W���A�e�B���[�W���A�f�[���@�v�g���A�J�C�T���ȂǂƏ̂����B�ŏ��̓�͌�������уT�J���̎咷�̌ď̂ł���A�}�n�[���[�W���̓C���h�̑剤�̂��ƁA���[�W���A�e�B���[�W���̓C�����œ������Ӗ����A�f�[���@�v�g���̓V�i�́u�V�q�v���C���h�̌���i�T���X�N���b�g�Ȃǁj�ɂȂ��������́A�J�C�T���̓��[�}�̃J�G�T���icaesar�j�ł���B
�@�N�V���[�i����̐l�X�́A���̂悤�ȎG���Ȍ���̏̍����ɂ��킹�Ė��̂邱�Ƃ��D��ł����B���̂悤�ȕ�e�Z�����́A���m�ł����m�ł��A�Ñ�ɂ́A�Ƃ��Ă��l�����ʂقǂ̂��Ƃł������B |
|
�@�Əq�ׂ��Ă��܂����A���������G���ȉ��̏̍��́A�A�N�Z�T���[�̂悤�ɒP�ɖ��_������킷���̂łȂ��A�����i��l���Łj�ɁA
|
�@�N�V���[�i�������݂�����_�I���Ђ�W�Ԃ������Ƃ����ڂ����B�E�F�[�}���J�h�t�B�Z�[�k�����S���E�̎�ɐ_�Ƃ����ɐ_�Ƃ��̂��������́A�鉤�̐_�I���Ђ̊ϔO���͂����茻�ꂽ���邵�ł���B
�@���̂悤�ȕω���������̂́A���邢�̓��[�}�̒鉤���q�̉e���ł͂Ȃ����ƍl������B���@���̐M�k�̂Ȃ��ɂ��A���������鉤�̏@���I���Ђ�F�߂�l�X������Ă����B |
|
�@�Əq�ׂ��Ă���悤�ɁA�鉤�̐_�I���Ђ�����킷�̂ɁA�F�X�ȏ̍����p����ꂽ���̂Ǝv����̂ł��B����͌Ñ�y���V���̏������]���A�X�^�[���̐_�A�t���E�}�Y�_���n��ɂ�����_�I���Ђ�t�����ꂽ���ƂƓ��O�̂��̂ł��邩���m��܂���B
�@���́A�������m�̂��̕��͂��݂����A�����v���N�������̂͏\���̏������J����v���̖{�����߉ނ��܂̂��Ƃł����B�@�����ʕi�ɂ́u�����̕s���v�u�N�I�̑召�v�Ƃ����A�X�ɁA
�@���͌Ȑg������A���͘ǐg������A���͌Ȑg�������A���͘ǐg�������A���͌Ȏ��������A���͘ǎ��������B
�@�ƘZ������������Ă��܂��B�ܘ_����͖{�����߉ނ��܂̕��E�ɂ�����ω����݂̉������������̂ł����A�O�k�̋���{�����߉ނ��܂̏�������̕��Ɋς������J�������w�i�ɂ́A�N�V���[�i�����̏����̒鉤�ρA�����A�n��ɂ�����_�I���Ў҂Ƃ��Đ��E���̏����ɌN�Ղ������łȂ��A�咷�E�剤�E�����E�V�q�E�J�C�[���Ƃ��������̏̍����݂�����̏̍��Ƃ��邱�Ƃɂ���āA�����̏����������̕��g�Ƃ݂Ȃ��Ƃ����鉤�ς��������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv����̂ł��B
�@�����i��l���Łj�ɂ́A���̂悤�ɂ��q�ׂ��Ă��܂��B
|
�@���̃N�V���[�i���̐����l���́A�����A�W�A�I�Ȃ��𑽂̂��ێ�����ƂƂ��ɁA�w���j�Y���I�ȗv�f�����`���A�܂��A�C���h�ɓy������ɂ�ăC���h�×��̏K���E�K���ɓ������Ă������B
�@�N�V���[�i�����̏ё�������ƁA���̕����͒����A�W�A�I�ł���B�܂��A������N�̌��̖���\���̂ɁA�}�P�h�j���̌��̖���p���Ă������Ƃ�����B�ݕ��ɂ��\�ɂ̓M���V�������A���ɂ̓C���h�̃J���[�V���e�B�[������p���Ă���B�ݕ��̖͗l���A�\�̓M���V���I�A���̓C���h�I�ł���B�܂��C���h�ƃV�i�Ƃ̊Ԃɂ͕����k�̌�ʘH���Z����������B
�@���̂悤�ȗZ���I�E��e�I�X���́A�@���̕��ʂɂ����Ă������ł���B���łɏq�ׂ����Ƃł��邪�A���Ƃ��J�j�V�J���̉ݕ��ɂ́A�M���V���̐_�X�A�C�����̃]���A�X�^�[�̐_�A�q���h�D�[���̐_�X���������Ă���B���ɂ̑������������̂��A����߂Ă킸���ł͂��邪���݂���B�N�V���[�i�����͎�X�̏@����F�߂Ă����̂ł���B
|
|
�@���������̐ړ_�ƂȂ����N�V���[�������̐��k�C���h�E�A�t�K�j�X�^���ɂ����镶���E�@���̕�e�I�E�Z���I�Љ�v����w�i�Ƃ��đ�敧�������N���A�ƑP�����Œ艻���`�[���������敧���ɑ��Ď��R�z���ɁA�������@���̐_�X���ɂƂ����ď��������A��F�����A���V�Ɖ����āA���X�ɑ��o�T��Ҏ[���A�@�،o�ɗ������Ė@�J��E�l�J��̖@�傪�ł��o����Ă����킯�ł����A�@�،o�̎O��J��̔w�i�ɁA�N�V���[�i�����̏@���ɑ����e���E�Z���������������Ƃ͌����Ƃ��ĂȂ�Ȃ����Ƃł���܂��傤�B�@�،o�o�T�̐����́A�N�V���[�i�����Љ��Ƃ��Ă͂��߂ĉ\�ł������Ƃ������Ƃ��o����̂ł��B
�@�R���A���̐������e�ՂłȂ��������Ƃ́A�J�j�V�J������Ƃ��ėi�삵�������́A����̐���ؗL���ł���A�������Ɩw�ǂ�����肪�Ȃ������Ƃ����Ă��邱�Ƃɂ���Ă����ʂ����Ƃ���ł���A�����i�E�s�y�i�̔E��́A���̂܂ܓ����̖@�؋��k�̑̌������Ƃɂ��ċL���ꂽ���̂ł������̂ł��B
�@���āA�v���̕����\�����q�ׂ悤�Ƃ��đO�������蒷���Ȃ�܂������A�͂��߂ɒ������m�������鐼�k�C���h�E�A�t�K�j�X�^���n���Ɍ������鑽���̕����Ɩ@�،o�����̊W���Љ�Ă����܂����悤�ɁA�@�،o�̕����́A�N�V���[�i�����̗Z���I�E��e�I�����v����w�i�Ƃ��āA�����̂��ׂĂ̕������~�g������̂ł��������Ƃ́A�e�Ղɑz�����邱�Ƃ��o���܂��傤�B
�@���̍ł������ȗႪ���ł��B���̋K�͂́u�����ܕS�R�{�A�c�L��S�\�R�{�v�Ƃ����A��ӂƍ�������Γ�̔䗦�ɂȂ��Ă��܂��B���̔䗦�͒��C���h�̃T���`�[�̕����ƑS����������̂ł����āA���C���h�Ñ�̕�������ꡂ��Ɋ�d�������Ȃ��Ă���A���������X���͐��k�C���h�̕����ɑ����݂�������Ƃ����Ă��܂��B
�@���k�C���h�̕�����d�ɉ~�`�ƕ��`�̓�킪����܂����A�~�`�͒��C���h�̌Î��̕��������̂܂܍����������̂ł���A���`��d�͐��k�C���h�ł͂��߂đn��o���ꂽ���̂ł��B���̊�d�͉~�`�����`���A���̂�����ł��邩�Ƃ����A�����ɏオ���āA�~�`�̐{��R�̏㕔�ƕ��s���邱�Ƃ���l�����킹��ƁA���`�����~�`���ӂ��킵�����̂ł�����A�����~�`�ł������Ƃ�����ׂ��ł���܂��傤�B
�@���ɁA���ɂ́u�ܐ�̗��|�����āA꜎��疜�Ȃ�v�Ƃ����Ă��܂����A���|�Ƃ͓����߂���ㅓ��̊O�I�̂��Ƃł���A꜎��Ƃ͕ǖʂɕ��������u���镔���������̂��Ƃł�����A���̕ǖʂɂ͐疜���ʂ̏����̑������u����Ă������ƂɂȂ�܂��B�ܘ_�A�����̕����͑����ߋ����̓��ł���ȏ�A�v�������̖��ʂ̉ߋ���������킷���̂łȂ���Ȃ�܂���B�\�����g�̏����͎O�ϓy�c�̌�A���𒆐S�ɁA���W���A������̎��q����ɍ���̂ł�����A���ǐ疜��꜎��̏����͓��R�ߋ����ł���ƒf�肳��܂��傤�B
�@�Ƃ���ŁA�����������̂悤�ȍ\�����������������k�C���h�A�����̓A�t�K�j�X�^��������Ɏ��݂������Ƃ�����肪����܂��B�ܘ_�A���͖��ʖ��ӂ̉ߋ����̓������������ے��������̂ł�����A���̋K�͔͂@���ɍL��ł����Ă��A�L�傷����Ƃ������Ƃ͂���܂���B�u�����ܕS�R�{�A�c�L��S�\�R�{�v�Ƃ����K�͂́A�ܘ_���z�����ꂽ���̂Ɛ\����܂��傤�B�R���A���Ƃ��K�͂͏������Ă��A���Ɠ����l���̕��������݂������ǂ����A�Ƃ������Ƃ����Ȃ̂ł��B
�@�K���A�c��`�m��w���_���������Z�Y�����A���̒��u���E�̌Ó��v�i��Z�ܕŁ`��Z�Z�Łj�Ɏ��̂悤�ɕĂ��܂��B
|
�@�K���_�[������������̋M�d�����Ƃ��āA���y���Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A�i���t���E�����h�E�j�m�@���m�[�Ŕ������ꂽ��������̏����ɂ��Ăł���B
�@�O�ɂ��q�ׂ��悤�ɁA�K���_�[�������Ō���������̂́A�قƂ�ǂ��Ђǂ��j�����āA���ւ͂������A���g���犮�S�Ɏc����͈̂����Ȃ����A�����ɂ��Ă��鏬���k�͍K���ɂ��قƂ�NJ��S�Ȍ��`�������Ă���B�����Ƃ����ꂪ�o�y�������ɂ́A���̉~�`���d�ՊW���т��S���̙��i�ƁE�x���j�͐܂�A�ՊW�͏����k�̂��ɒu����Ă����Ƃ����B������������A���̑��ւ͔����̕�����A�����܋��~�`��d�ƂƂ��ɁA�܂�ɂ݂�������`�Ԃ������悤�ɂȂ����B
�@�K���_�[�������ɂ́A�ɓ��������������悤�ɁA���~�O��̊�d���F�߂��A���̂����ɉ~�`�́A�C���h�Ð��X�g�D�[�p�̉e���ł���A���`�̓K���_�[���ɔ��B�����l���ł���B�������~��P�w�̓��́A�_���}���[�W�J�[���Ɍ���ꂽ���A�~��d�w�̓��Ɏ����ẮA���̃��t���E�����h�E�����������Ė�����������Ă��Ȃ��B
�@���Ă��̏����́A���j���J���W���[���ł���A���̎��͂��g�E�E���Ȃǂ̍ʐF����X�^�b�R�̌J�`�ƕ�������Ƃő����������̂ł���B�܋��̉~�`��d�͒����������A���̍Œዉ�ɂ́A�ۂ̌`�ƒj�����Ƃ����݂ɍ��݁A���ꂩ���̏����́A����������`�̊Ԃ�꜂�݂��āA���ꂼ�ꕂ������̕����������u���Ă���B
�@�Ȃ��~�`�ՊW�̉��ɂ͍E�������Ă��邪�A����͂����炭�A�}�[�V�����̑z�������悤�ɁA�����Ɖ�顂����邽�߂̂��̂ł������炵���B
�@���̏����́A���̕������A�ʼn��̔ՊW�Ƃقړ������a�ŁA�������������Ȃ��Ă��邱�ƁA�܂���d�����S�̂̎啔���Ȃ��āA�قƂ�Ǔ��g�̂悤�Ɍ����邱�ƁA����ɑ��ւ����ɍ����ނ��Ă��邱�ƁA�Ȃǒ�������{�̍��w�̓��k�ւ̔��B�̑O�������������̂̂悤�Ɏv����B |
|
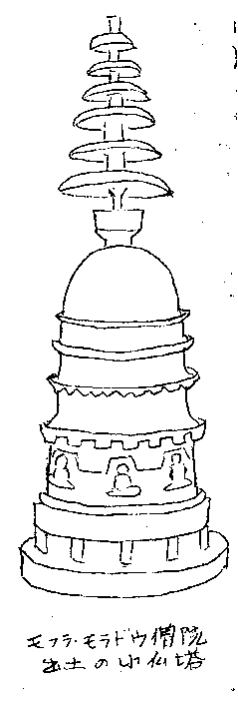
��̐}�͎����ɂ���ׂĒ�ӂ̒��a�ƍ����Ƃ̔䗦�������Ⴂ�A�������������Ă��邱�Ƃ����f�肵�܂��B
�@���t���E�����h�E�̑m�@�Ƃ����A��Ɂu�����̐����Ƃ��̈Ӌ`�\��i�v�̍��ɂ����āA�g���R�Z����w����������t�����N�̊ԁA���x�������̕�����q���Đ��k�C���h����A�t�K�j�X�^�������ꂽ���ʁA���Ƀ��t���E�����h�E�̔p���̓��ŎO�̓����̐Ε���������L���Љ�����Ƃ�����܂����B
�@���̍ہA���͂��̎O�̐Ε����哃�̕�꜂Ɉ��u���ꂸ�Aㅓ��̕ǖʂɂ����Ă��ꂼ��哃�ɑ��Ă������Ƃ���A�ʂ����Ė@�،o�̓������ǂ����A�^���悵�A�u����ɂ��Ă��A���̑��`�ɂ͍���A�傫�ȈӋ`�����o����Ă��邱�Ƃł��傤�v�Əq�ׂĂ����̂ł����A���̑m�@�̑��m�[��蔭�����ꂽ�����������A�������镧���̒��A�ł����ɋ߂��m���������Ă���̂ł͂Ȃ����A�Ǝv���ĂȂ�܂���B
�@�ܘ_�A���ɂ͊J�̔������A�����ɓ��������Ԃ��������̂ɑ��A�����[�����h�E�̏����ɂ���͂���܂���B����͌���I�ȑ傫�ȑ���_�ɂȂ��Ă��܂����A�������ɗ������K���Ƃ𑍍����ꂷ��ړI�����ȏ�A����͓��R�̑��`�ł���A�����[�����h�E�����ɃX�g�D�[�p�[�ƃ`���C�e�B���̓����ړI�̂Ȃ��ȏ�A�����������Ȃ��͓̂��R�̂��Ƃł���܂��傤�B�Ⴕ�A���╔��������A����͑����̂��̂ł����āA�����[�����h�E�����͕o���O��ɂ�����ł����ɋ߂��l���ł��낤�Ǝv����̂ł��B
�@�A���A���N�̘Z������A�u�����O���t�v�����W���s���ꂽ�u�����E�V���N���[�h�v�Ƃ����G���ɁA�͕��ݗ������u�K���_�[���[���p�v�Ƒ肵���ʐ^�W�Ɂu�����[�E�����[�h�E�m�@�̕����v�Ƃ����S�i�ʐ^���f�ڂ���Ă���A����ɂ͋I���l�`�ܐ��I�̌����Ƃ����������Ȃ���Ă��܂����B�]���āA���̏��������̂���̐���Ƃ������ƂɂȂ�܂��傤���B�Ƃ���Ŗ@�،o�o�T�͈ꐢ�I����I�ɂ����Đ��������Ƃ����Ă��܂����A�������m�̃��@�[�X�f�[���@������Ƃ��Ă��O���I���t�ł�����A���̏�������͖@�،o�o�T�����ȍ~�̂��̂Ɛ\����܂��傤�B
�@�R���A���̏����Ɠ��^�̕������A�召���܂��܂ɐ��k�C���h�ɑ]���Č�������Ă����ł��낤���Ƃ͗e�Ղɑz���������̂ł��B���̏؍��̈�[�Ƃ��Č��݃J���J�b�^�����قɒ�Ă���K���_�[���n���̃X���b�g�k�J�Ŕ������ꂽ��Β����̏������������邱�Ƃ��o���܂��傤�B����͋I���I���̍�Ƃ����Ă�����̂ł��B
�@���̃X���b�g�����́A�����[�����[�h�E�����Ƃ���ׂĂ݂�Ɗ�d�����`�ł��邱�Ƃ������A�w�Ǔ��ނ̗l�������Ă���A���p�H�|�i�Ƃ��Ă��X���b�g�����̕���������Ă���Ƃ��\����Ă��܂��B�����ŁA�I���̃X���b�g�����ƁA�l�E�ܐ��I���̃����[�����h�E�����Ƃ�������ׂ鎞�A���̊ԂɁA�܂������@�،o�o�T���������A���z���n�߂����ɓ������Ă���Ƃ��납��A���Ƃ������̕������������ؗL���̐l�X�̌����������̂ł������ɂ���A�����̐l�X�̌����������̂ł������ɂ���A�@�،o�̑��ɋ߂����`���Ȃ��Ă������̂ł���A���̑������ݕi�ɂ����镧���ɂ����ꡂ�������E�A���Ă������Ɛݒ肳�ꂽ�Ƃ��Ă��A�_�͕i�ʕt���̋N�����{�̕����l�����܂��A�����̕����l����O���ɂ����Ă����̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�킵�߂���̂ł��B
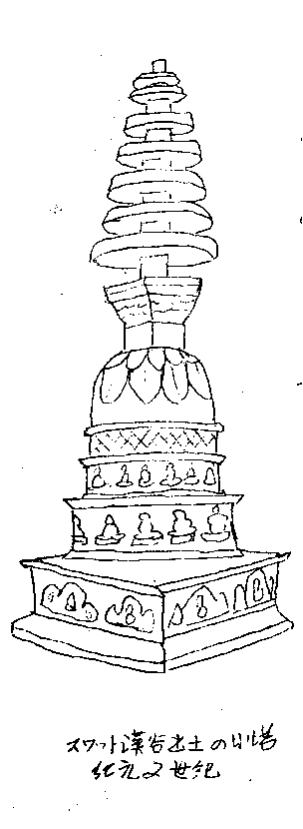
��̐}�͎����ɂ���ׂĒ��������̕������P�W�ɑ��Ă�⏬�����Ȃ��Ă��܂��܂����B���f�肵�Ă����܂��B
�@�Ƃ���ŁA������������悤�ɂȂ����̂́A�K���_�[���n�����悩�A�}�g�D�[���n�����悩�A�����͖w�Ǔ������A�Ƃ����_�c������܂����A������ɂ��敧���̏o���͋I���ꐢ�I�����A�������Ƃ��I�̑O���ɂ͊m���ł���Ƃ����Ă��܂��B����Ɩ@�،o�̕��֕i���l�L�i���܂ł̑��ގ���ɂ́A�܂������͏o�����Ă��Ȃ������Ƃ��Ă��A�@�t�i��\�ȍ~�̑��ތo�T�A��O�ތo�T�̐������铖���ɂ́A���ɕ������o�����Ă����Ƃ����Ȃ���Ȃ�܂���B�����̑���@���̑��݁A���тɎ߉ޑ���̓����̋V���́A���炩�ɕ������ӎ������V���ł���A�����݂�꜎����܂��A�疜�̕��������u�������Ƃ��ӎ����Ă������̂ɂق��Ȃ�܂���B
�@���ɓI���̍�Ƃ�����X���b�g�����̕�����d�ɂ́A�O�w�ɕ�꜂����������A���̓��ɏ��������u����Ă��܂��B�����[�����h�E�̏������܂������ł���A�����Ƒ���꜕��Ƃ��v�����킹��A�_�͕i�ʕt���̋N�����{�̕����ɂ́A�v���̖{�����߉ނ��܂̕����𒆐S�ɁA���ʂ̉ߋ����̏����A���ʂ̕��g�̏����̏������A�d�w�I�ɕ����̎��ǂ�꜎��Ɉ��u�������̂ł������̂ł͂Ȃ����A�Ǝv�킵�߂���̂ł��B
�@���Ƃ��A���̖{���̕����͖{���̕�F�ɂ���Č�������A��ㅘe�d�������̂ł�����A�{���̏��ł����s�E���Ӎs�E��s�E�����s�Ƃ����l���F���A���ʖ��ӂȂ�{���̕�F��O���\���āA�����{�����߉ނ��܂����E���e�d����悤���`����܂��傤�B�ł́A���̎l���F�̑�����ɂǂ̂悤�Ɉ��u���ׂ��ł��邩�A�Ƃ�����肪�N���ė��܂��B
�@�R���A���̂��Ƃ��l����O�ɁA�K���_�[���������������o�āA���{�֓n���Ă��Ĉȗ��A�������`���ǂ̂悤�ɕς��A�ǂ̂悤�ɕώ����Ă��������l���A�����{���݂̍�ׂ����`��q�˂Ă݂����A�Ǝv���܂��B
�@���ɁA�q�ׂ܂����悤�ɃK���_�[�������́A�T���`�[�̕����̂悤�ȌÙ����̂��̂ɂ���ׂāA��d���d�w�I�ɍ����Ȃ�A�P�W���܂������Ȃ��ė��Ă��܂����B���ꂪ�����Ɏ����Ă͍X�Ɍ֒�����A�����̍��O���z�ɉe������āA�܂��܂��d�w�����ė��܂����B�����E�_���E�哯�̐ΌA���@�̓����ɂ́A�����̑������[�t���c����Ă��܂����A���̓��̌`���́A�ő��C���h���̂��̂łȂ��A�����ɂ����������́A�d�w���鉮���̒���ɏ����Ȃ��̂Ƃ��Ă�����Ă���A������p���������{�̕����́A��������O�d�̓��E�d�̓��ƂȂ�A�����͑��ւ̕��ɂ����Ȃ����̂Ɖ����Ă��܂��B�����Ĉ�ʂ̐l�X�����Ƃ��ċ��ł���O�d�E�d�̉��������������͎��̓K���_�[�������̊�d�̕ό`�ɂ����Ȃ��̂ł��B
�@�������́u���E�̌Ó��v�i�\�O�Łj�ɁA
|
�@�킪�@�����d���́A���̑��ւƓ��g�Ƃ̍����̔��A�͋����u�˂̋ϐāA�e�K�����̎��R�ŗ����I�Ȓ����̓x�Ȃǂ̖����ɂ����āA�f�R��z���Ă���B����ɖ�t�������́A���������オ�鑊�ցA�����A�֊K�A�y�ю����̌y���ȊK���Ɏ����ẮA���ɂ��̔�����Ȃ�����T��̋ɒv�ł���B |
|
�@�ƁA���̌��z�����^���Ȃ�����A���̂悤�Ȕᔻ�������Ă��܂��B
|
�@�����������ɂ͂Ȃ����p�I�@�\���������A�ނ��됒����ڎw���M�̉��I�ے������߁A�����I�������z�ɈЌ���Y���A�Q�w����P�j�E�P���ɉ��]������ڕW��^���A����ɁA���߈�т̗��̓I�i�ς𑽍ʂɂ���l�X�̐S���I���@�Ɋ�āA���k�̑��c���s��ꂽ���̂ƌ��Ă��������Ȃ��ł��낤�B |
|
�@�܂��������{�̊e��̕����́A���ɂ���A�O�d�̓��A�d�̓��A�����͏\�O�d�̓��ɂ���A�����͕��ɗ��̎��́E�͂������߂����̂ł������Ƃ��Ă��A���̎��́E�͂͋����̕����ւƈڂ�A���͂����s��Ȍ��z���𑝂��Ȃ���A���@�̗֚�̔�����������̂Ɖ����ė����̂ł��B
�@�`����t�����썑�Ƃ̂��ߑS���Ɍ��������Z�����̑��֓��́A����܂ł̓��̊e�w�̎����������ȗ����āA�~���̓��g�Ƒ��ւɂ��A�l���Ɏx���l�{�����������̂ɂ����܂���B���Ƃ����̑��֓��ɁA���ɗ���@�،o�̌o���[���Ă����Ƃ��Ă��A���̑S�̂̎p�́A�C���h�{���̕����Ƃ͎��Ă�������Ȃ����̂ƂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B����͖��[���镧�ɗ���o�����A���̐S���̒��ォ�A�����͍ʼn��̒�̑b�ɂ���Ƃ��납��A�S���ɕ������鑤�ʂ̂��̂��������āA�̐S�ȂƂ��낾��������킻���Ƃ������̂ł������̂����m��܂���B
�@�R���A�C���h�̕����ɂ����ẮA�������d�A�����A�����A���ւ̎l��������o���A�͂��ߕ��ɗ���o���͕����Ɉ��u����A����⎩�R�̔j��������ĕ����̓��ɔ[�߂���悤�ɂȂ������̂ŁA�����̒��S�͕����ƕ����ɂ���A��d�Ƒ��ւ́A���S���𑑌����邽�߂ɂ�������ꂽ���̂ł������̂ł��B�����������́A�P�ɕ��ɗ���o����[�߂�e����̂łȂ��A���߉ނ��܂̐l�i�A�\�E�̂��ׂĂ̂��̂������������ێ悷��~���Ȑl�i���ے����Ă����̂ł��B
�@���@�吹�l�}���̑�}���_�����@��̐l�X�́u�։~��̑�}���_���v�Ƃ����A�����́u�\�E�~�Z�̑�}���_���v�Ɛ\���Ă��܂����A�����̕����̎p���̂��̂����A�����ʂ�{�����߉ނ��܂̗։~�E�~�Z����v�������̐l�i���ے��������̂ł���Ɛ\���܂��傤�B
�@�R��ɁA���̕����͒����ɂ����Ċ��ɍ��w�O���̒���ɂ�����������̂ƂȂ�A���S���̕����ɑ����Ē����̌��z���o���A��������̂܂܌p���������{�ł͑��֓��ɂ����ďȗ���������Ă��܂��܂����B����͂��߉ނ��܂̐l�i�����āA�������ɗ��̎��́A�o���̎��͂ɂ�������Ă��܂������ʂɂق��Ȃ�܂���B
�@�����J���Ɋ����Ȃ��̂́A���@�@���{�R�g���R�v�������A�吹�l���S�������^���Č������悤�Ƃ��đ�{���̑O�̑��֓����v��ł��B�g���R���ǂ��@�֎��u�݂̂ԁv�ɔ��\�����Ƃ���ɂ��A��{���̑O�ɒr���@��A�r�̒����ɑ��ւ����Ă邱�ƂɂȂ��Ă��܂����A���J���ꂽ�����\�z�}�ɂ��A����͓`����t���n���������֓��Ƃ��S����������̂ŁA��������ȑ��ւ����ɂ����܂���B
�@�ܘ_�A���̑��ւ̓��ɖ@�،o�̌o�������[����邱�ƂɂȂ��Ă��邻���ł����A���ւƂ͓��𑑌�����P�W�̏d�w�������̂ł����āA�P�W�����𗧂Ă�Ƃ������Ƃ��������ĕ��������Ƃ̂Ȃ����̂ł���A���̎P�W�Ɍo���[����Ƃ���������������Ƃ͂���܂���B�܂��Ă��̎P�W�̒r�̒��ɗ��Ă�Ƃ����͈̂�̂ǂ������Ӗ��ł��傤�B����ł͈�ㅗ�q���邱�Ƃ��ł��܂���B
�@�g���R���ǂ֚͗�����Y����̂ɁA��قǎ��Ɋi�\���悢�Ǝv���āA�����������v������Ă���̂ł��傤���B�Ⴕ�����ł���Ȃ�A������`�����邱�ƂɂȂ�͂��Ȃ����A�Ƌ������̂ł��B�O�ɂ��q�ׂ܂����悤�ɓ��{�̕����́A�͂��ߔ��E�@�����E�l�V�����̂悤�ɏ����̒��S���Ɍ�������Ă��܂����B
�@�R������ɑS���𑑌�����ʒu�Ɍ��Ă���悤�ɂȂ�A�~���Ă͂��������̗֚�������������̂Ɖ����ė��Ă��܂��܂����B�`����t�̑��֓��ɂȂ��ẮA�����S�������ƂȂ�A���x�̐g���R�̎��S�����L�O���Ƃ̑�{�������v��̒��ł́A��{���O��́A�������r�̒��̑��ւ����ƂȂ��Ă��܂��܂����B����͕����ɑ��鉽�̗������Ȃ��҂�掖@�̏��ƂƂ����O�͂���܂���B
�@�����Ƃ���ɂ��A������w�̐Ԗ�̓��ɒr������A�r�̒��ɑ��ւ��������Ă��Ă��邻���ł��B��������������������߂ɍs���˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���Ȃ���A�܂��@��Ă��܂��A�Ⴕ�{���ɐԖ�̓��̒r�ɑ��ւ݂̂������Ă���Ƃ���Ȃ�A�g���R���ǂ̑������v��́A����̂����^�������̂ł��傤���B
�@����̒�r�ɑ��ւ������Ă��A������Ƃ����ᔻ���ׂ����̂ł�����܂��܂����A��腕�����̗�R�g���R���A���S�����L�O�ɓ���̂����^�������Ƃ����ẮA�g���R�̏@���I���Ђ��n�ɑ����Ɣ���Ă��d���͂���܂���B���N�u�݂̂ԁv����ꌎ�������ɁA�v�҂ł���H�w���m�J���g�Y�搶�̂��Ƃ����̂悤�ɏЉ��Ă��܂��B
�@�u�搶�͓����H�Ƒ�w�̖��_�����ŏ��a�O�N����H�w�����z�Ȃ𑲋ƁA���a�O�\�l�N���{�|�p�@����A���a�l�\���N�ɂ͕����M�͂��Ă�������{���z�ō��̂����ł���B���̎�v��i�ɂ͓��{�䏊�A�������������ق̓��m�فA�}�o�٘a���ʊفA�����ߑ���p�فA�w�m�@�A��������v
�@�J���搶�͌��z�ƂƂ��Ă͐��ɗ��h�ȑ�ƂƎv���܂����A�R�����@���z�E�������z�ɑ��āA�ǂ�قǂ̑��w��������̂ł��傤���B��{���̑O��ɒr���@���Ă��܂��ẮA����܂łł��L�̂Ђ����̂悤�ɋ��������͈�w�����Ȃ����ł��B�܂��Ă��̒r�̐^���ɑ��ւ��������Ă�Ƃ����ẮA�����̈Ӌ`���Ȃ�猤�������A��������̐Ԗ�̓��̂����^�������Ƃ��������悤������܂���B�g���R���ǂ͒J�����m�ɑ��ĉ��߂Č�������蒼�����A�v����蒼������ׂ��ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@�C���h�̉��ɏ鑽��R���ɗ����E���牤��S�̒n�J�����K���ɗ����E���@�@�����R���ɗ����E���h�R�同�����ɗ������͂��ߓ��{�R���̑�\�I���ɗ�����v���ꂽ���{��w�剪���H�w���m�́A�Y�R�t�̌���u�����l�Êw�u���\���E���k�v�̒��ŁA�u�C���h�̕��ɗ����v�Ƒ肵�āA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
|
�@���@�@�̈�h�ł�����{�R���@���̓�����B��l�Ɍ䉏���ł��āA�ߑ��̌��n�I�ȃV���{���ł��镧�ɗ����i�����A�ߑ��̍���[�߂�����ł���A�C���h�ł̓X�g�D�p�[�Ƃ����j��v����悤�ɂȂ����̂́A���a��\��N������̂��Ȃ�Â��b�ł���B
�@�����܂ł��Ȃ����́A�Â����z�̌����҂Ŏ��ۂ̐v�Ɍg���Ă���l�����ɏ��Ȃ��̂Łu�����Ȃ���ł悯��v�Ƃ��������ň������̂ł������B�����Ɏ肠���莟��A�{���W�߂Ďʐ^���͂ł��邾����������A���z�̎��̂����o�I�ɔc������ɂ͎��n�����ȊO�ɂȂ��B�����x�C���h����ю��ӂ̍����������Ǝv���Ă����B
�@�Ƃ��낪���a�O�\��N�̏t�A�ˑR�A�������W�̌��z�Ƃ���ыZ�p�҂̍��ۉ�c���p���ŊJ����A����ɏo�Ȃ��邱�ƂɂȂ����̂ŁA���̋@��Ƀ��[���p���ꏄ������A�C���h�A�Z�C�������̌Ì��z�����ۂɌ����������ƍl�����B�i�����j
�@�{���x�C��U�o���ɁA�A�W�����^�A�G�����A�T���`�[�A�o�W���[�A�J���[�����̐ΌA�n���̕��ՂȂǂ����w���A�����͕s�ւ������J�W�����z�[�A�p�b�^�_�J�[���A�A�C�z�[���Ȃǂ��K�ꂽ�B�i�����j�c�c���̃C���h���s�Ō�����ꂽ�啔���̌��z�́A�₽��ɔώG�ȕlj�ɏ[�������Ă��邾���Ȃ̂ŁA��̃C���h�̌��z�Ƃ����́A���z���̊�{���ǂ��ɒu���Ă����̂����킩��Ȃ��Ȃ�A���Ɏ������g�̐_�o�����������Ȃ��Ă���̂ł͂Ȃ��낤���A�Ƃ����v���悤�ɂȂ������A���̃p�b�^�_�J�[���A�A�C�z�[����A�}�[�}���v�����̃O�v�^���̌��z�����āA���z���̍����͈�ł���Ƃ̔F�����Ƃ�߂��ăz�b�Ƃ����̂ł������B�i�����j
�@���_�I�Ɍ����ƁA�C���h�ŕ��ɗ����̌��n�`���ɋ߂��`��m�蓾��̂́A�l��̎����Ɍ��肳���B���́A�J���[���A�o�W���[�A�A�W�����^�Ȃǂ̐ΌA�̒��Ɍ@��c���đ���ꂽ���X�g�D�p�[�ł���B�i�����j
�@���́A�C���h���k���i�̂̃K���_�[���n���ɑ�����j�̃X���b�g�k�J�Ŕ������ꂽ�����i���J���J�b�^�����فj�ł���B
�@��O�́A�}�h���X�̋߂��A�}���o�e�B�ɂ��������ŁA�I���O�ꐢ�I�ɑn���A�I����I�ɑ呝�z���ꂽ���a�܁Z���[�g���ɂ���Ԃ��̂ł��������A�ɂ������\�㐢�I�Ɋ��S�ɔj��Ă��܂����B�R���K���Ȃ��ƂɁA���̓��̎p�𔖓�����ɂ����̔��A���̑����Ƃ��ėp�����Ă��āA���ꂪ���Ȃ�̐��c���Ă���B�i�����j
�@�C���h�ɂ����ČÂ����̑S�i��m�蓾��̂́A�ȏ�̎O��ɂ����Ȃ��̂ł���B�C���h�ł͂Ȃ����A�X�������J�i�Z�C�����j�ɏd�v�Ȉ�u������B�Ós�A�k���_�v�[���̑�X�g�D�[�p�̊�d�̏�ɓ[�g���ɂ�����Ȃ������ȓ��������Ă���B���A���E�F���̓��Ƃ���������̂ŁA��X�g�D�[�p�̎��݂̓��Ƃ����`���ł��邪�A����͑�X�g�D�[�p�̎��͂ɑ������Ă�ꂽ�����{���̈�ł��낤�B���̓��͋I����`�O���I�̂��̂ƌ����邪�A���������璤��o����Ă��āi���ւ͕ʐł��낤���A�����̐���ł��邱�Ƃ͖��炩�ł���j�A�m���Ɍ��`��ۑ����Ă�����̂ł���A���������`�I�Ɍ��āA�S�̂̃o�����X�A���g�i�����j�̋Ȑ��Ȃǎ��ɔ������B
�@�ȏ�̌v�l��̃X�g�D�[�p���A�S�̂̌`���m���ɒm�蓾�鐔���Ȃ������ł���Ƃ����̂��A���̌��_�ł���B |
|
�@�剪���m�́A���̂悤�ɑ��N�̊ԁA���ɗ����̍\�����������A�C���h�E�X�������J�����n�������A�m�M�Ă͂��߂ē�����B��l�ɕ��A��l�̈ӌ���u�x���Đ����R��同���̕��ɗ����A�y�щ��ɏ��J�����K�̕��ɗ����̐v�ɂ��������Əq�ׂĂ��܂����A���͑剪���m�̕��ɗ����v�ɑ��錪���ȑԓx�ƁA�剪���m�����Ă���قǂ܂ł������Ɍv�悹���߂�������B��l�̐M�Ɍh��������Ȃ����̂ł��B����͐g���R�̑�{���O�̑����݂Ƃ���ׂ�A�܂��ɓV�n�_�D�̑���Ɛ\���܂��傤�B
�@���́A�����k��ɐg���R�̑����v�����U�����Ă���̂ł͂���܂���B�_�͕i�ʕt���̋N�����{�̕������A�v���̖{���̕����A���@�Ɍ�������ׂ��{��̖{�����Ƌ��A���̕����\���݂̍����Nj����鎞�A�������z�̕ϑJ�A��ɒ����ŕώ����A�X�ɓ��{�ő����A���ɂ͑��̋ɂ̈�ǂ��g���R�����v��Ƃ��Ă�����ė��Ă��邱�Ƃ�Q���A�g���R���ǂ̔��Ȃ���邱�Ƃ�����Ă���̂ł��B
�@���đ剪���m�́A���ɗ����̌��n�I�l����m��l��̎������f���Ă��܂������A���̎l��̎�����ΏƂ���A�����̓��g�̔��~���̋Ȑ��������ʂ��Ă���悤�ł��B���̋Ȑ��������A�������̂��Ȃ߂ł���A�����ɕ����̐S���ے�������̂ł���܂��傤�B
�@���s��w�������ƕv���m�́A���̒��u�C���h�̔��p�v�̒��A�u�������p�̐i�W�A�X�g�D�[�p�v�i�O��Ł`�l�l�Łj�ɁA���̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
|
�@�X�g�D�[�p�̍\���́A�������ցA���A�����A�����A�P�W�̏���������Ȃ��Ă��邪�A�`�ԏ�͕������������̑啔�����߂Ă��āA�S�̂̌`�͔����`�̔������悤�ȁA����߂ĒP���Ȃ��̂ł���B
�@�X�g�D�[�p�́A���̔����`�̌`���A�����̐l�������悤�ɁA�{���͓y��グ���`�ɗR������Ƃ��Ă��A��������̂悤�Ȑ������������������`�ɂ��A�܂����̌`���A�̂��̃X�g�D�[�p�Ⓝ�̈ꕔ���Ɉ�̒�^�Ƃ��ē��P���ꂽ���Ƃɂ́A���ꂪ�����͓���Ȋ����������Ă����Ƃ������Ƃ��Ȃ���Ȃ�ʁB
�@����͂����܂ł��Ȃ��A�~���ł����₩�ŖL���Ȋ����ł���B�������Ă��ꂪ���ɂ̐��_�ɂȂ���Ƃ������Ƃł���B�T�[���`�[�̋u�ɂ̂ڂ��āA��O�ɑ傫�������`�̃X�g�D�[�p��������Ă������A�����͏��߂Ă��̂��Ƃ��悭�������邱�Ƃ��ł���B�G�W�v�g�̍L���Ƃ��������ɁA���͂̏ے��Ƃ��Ă��т������т���s���~�b�h�̊p�����Ј��I�Ȋ����ƁA�ꌩ���Ă���͑ΏƓI�Ȃ��̂Ȃ̂ł���B
�@�����`�̕�������̂Ƃ����{���̃X�g�D�[�p�A���Ȃ킿�������̌`���́A����ɑ����`����Ă���B��C���h�̃A�}���[���@�e�B�[��i�[�K�[���W���i�R���_�̃X�g�D�[�p�́A�����͔j�ꂽ���A������p�l���Ɏʂ��ꂽ�p�ɂ���āA�����̏��m����B�Z�C������r���}�A�^�C�ɂ��������͑����B�����Ƃ��A����n�̃X�g�D�[�p�̕����́A�T�[���`�[�ɂ�����{���̃X�g�D�[�p�̂���̂悤�ȁA�����������`�ł͂Ȃ��B��C���h�̏ꍇ�ɁA���łɕ����̌`�����������Ȃ�A�Z�C�����ł͐��̕��ɂЂ낪���đS�̂����m���̒ޏ��̊i�D�ɂȂ�A�r���}��^�C�ł́A����ɒ�������āA�~���`�ɂ����������ɂȂ��Ă��܂��B�����ł͂��͂�A�{���̃X�g�D�[�p�̉~�����̂��̂̎p��������̂ł���B
�@����A�k���n�̃X�g�D�[�p�ł͂܂�����������B���̑�\�ł���K���_�[���̂��̂��݂�ƁA��ʂɊ�䂪���B���Ċ�d�ɂ��Ȃ�A�~�`����`�̊��̕\�ʂ�꜁i������[�߂鉚�݁j�����������A������������āA��䂪�X�g�D�[�p�̖{�̂̂悤�Ȍ`�ɂȂ��Ă���B����ɂ��āA�{���͒��S�ł���ׂ��������A�S�̂Ƃ̔��Ŏ���ɏ������Ȃ��Ă䂭�B���̌X���́A��������{�ɂ����āA���������ɒ[�ɂȂ��Ă���B�������k���n�ł́A���̂��̂��̂̌`�Ɍ��`�Ƃ��Ă̔����`����������Ă���̂����ڂ����B
�@�X�g�D�[�p���ꎩ�́A���Ȃ킿�A��������ɂ́A���Ƃ��Ƒ����̂��߂̒����͂��Ă��Ȃ��B�p�[���t�g��T�[���`�[�̗���݂Ă����炩�Ȃ悤�ɁA�����̓X�g�D�[�p���Ƃ肩���ޗ��|�i�ʊ_�j�Ⓝ��Ɏ{���ꂽ�̂ł���B�������I����ɂȂ�ƕω����N����B�K���_�[���ł͊��ɁA��C���h��A�}���[���@�e�B�[��i�[�K�[���W���i�R���_�ł͊��E�����̗����ɁA�����E���`�}�A���̑����܂��܂̒������݂���悤�ɂȂ�B���̕ω��́A�I����ɂȂ��ĕ����������͂��߂����Ƃɂ��̂ł���B
�@���̂��Ƃ́A���Ƃ��A�A�W�����^�[��\�A�̃X�g�D�[�p�i�O�ꐢ�I�j�Ƒ��\�Z�A�̂���i�Z�Z�Z�N���j�Ƃ��݂�Ζ��炩�ł���B�O�҂̓X�g�D�[�p�̕\�ʂɂ܂����������͂Ȃ����A��҂͊�䐳�ʂ̕��������͂��߁A����ʂɑ����̕����A�����ɂ͐��̒j���̑����������Ă���B�����̌`���A�O�҂������������ɋ߂��A�`���傫���A�X�g�D�[�p�S�̂����̂��߂ɂ����������ɂ��̂��̂ł��邩�̂悤�ȉ~�����������Ă��邪�A�㉺���爳�k���ꂽ�悤���\���`�ɂȂ�A���Ȋ��ɑ��đS������肪����B
�@�X�g�D�[�p�̌`�Ԃ̂��̂悤�ȕς����́A�\�ʂɕ������̑��̒����������Ƃ����A�P�Ɍ��ۓI�Ȃ��Ƃ��炾���l�����邱�Ƃł͂Ȃ��A���{�I�ɂ́A�X�g�D�[�p�ɑ���l�X�̍l�������A����ɂ���ĕς�������Ƃ��痝������˂Ȃ�Ȃ��B
�@�X�g�D�[�p�́A�ŏ��A���ɗ����܂邽�߂ɂ���ꂽ���̂ł���B���ɗ��͕��ɂ̐g�̂̈ꕔ�ł��邩��A�X�g�D�[�p�͕��ɂ��̂��̂Ƃ����C�����ł݂�ꂽ�ɂ������Ȃ��B���ɗ��Ɍ��炸�A�����A�����Ȃǂ����܂߂āA���悻�╨���q�̔O�̂悩�����I���O�̃C���h�ɂ�����X�g�D�[�p�́A���ꎩ�̂����Ƃ݂�ꂽ�̂ł���B����q�����̎ɗ������u�����X�g�D�[�p������ꂽ�B�T�[���`�[��O���͂��̈��ŁA�\���q�̒��̎ɗ����A�� �A�̎ɗ����܂�ꂽ�B���������ꍇ���A���ꂪ����q���̂��́A�Ђ��Ă͕��ɂƂ݂Ȃ��ꂽ�̂ł��낤�B �A�̎ɗ����܂�ꂽ�B���������ꍇ���A���ꂪ����q���̂��́A�Ђ��Ă͕��ɂƂ݂Ȃ��ꂽ�̂ł��낤�B
�@�Ƃ��낪�I����ɂȂ��ĕ����������͂��߂�ƁA�l�X�̓X�g�D�[�p���������Ƃ��Ĉӎ�����悤�ɂȂ����B�����ŃX�g�D�[�p�͕��ɗ��Ƃ̊֘A���������Ȃ�����A���ꎩ�̂����ł���Ƃ������_�I�Ӗ��������āA�ނ���l�ԓI�Ȏp�����������������Ƃɂ���āA���̈Ӗ��������Ȃ��悤�ɂȂ����B��䂪���B���ĕ���������։������ꂽ�̂��A���̎�̐����╨���瑜�ɂ��������߂ł���B
�@���̌X���͓��i�ނɂꋭ���Ȃ�A���{�̓��Ȃǂ́A���������u��������ɑ��āA���ɗ������u����̂����ł���Ƃ����{���̂��đO�͎c���Ȃ�����A���́A���͂⏃���ɕ����ꎩ�̂ł͂Ȃ��A�ɗ��ɂ��땧���ɂ���A�v����ɕ��I�Ȃ��̂����߂錚���ɂ����Ȃ��Ȃ��Ă���B�����ŕ����͉����̏�ɁA�\���킯�̂悤�Ɏc����Ă���ɂ����Ȃ��B
�@���B�������́A�������z�Ƃ��Ă͊m���ɓƓ��̔����������d�v�Ȃ��̂ł���B���������̎p�́A�E�̂悤�ɕ������_���牓�������Ă��Ă���B������v���ƁA���߂ăT�[���`�[�̃X�g�D�[�p�́A�Â��ɗ����������~���Ȏp�ɁA���I�Ȃ��̂����݂��݂Ɗ�������̂ł���B�������Ă������肩����ŁA��������ꂽ���X�̒������A�����̕������p���\���邷���ꂽ��i�ł��邱�Ƃ̕K�R�������Ȃ������̂ł���B |
|
�@���p���������ƒ����Ȃ�܂������A��씎�m���剪���m�������̒��S�����Ƃ��A�剪���m�͕����̋Ȑ������������A��씎�m�͕����ɏے�����Ă��镧�ɂ̉~���Ȑ��_����������Ă��܂��B���̕��������g���̂��̂ł���Ƃ������Ƃ͗����m�̌������܂܂ł��Ȃ��A�l�p�[���̃J�g�}���Y�̕������͂��߃`�x�b�g�n�̕����̕������ɁA���ɂ̊�Ɣ��Ƃ��O���e�X�N�ɉ悩��Ă��邱�Ƃɂ���Ă���ڗđR�Ƃ��Ă��܂��B�悩�ꂽ��Ɣ��́A���܂�ɂ��O���e�X�N�ł���A���������Ȃ����Ɛr���������̂ɂ��v���A�l�ɂ���Ă͓f���C�����o���邩���m��܂���B
�@�������A�`�x�b�g�n�����k����������ɉ悩����Ȃ��������͉̂��ł��������Ƃ������Ƃ��l���Ă݂鎞�A�����ɕ��������g���ے�������̂ł���Ƃ������Ƃɂ������炸�A���g���̂��̂Ƃ��ċ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��R�x�����̂��т����A�����̑������Ɏv�������邱�Ƃł��傤�B
�@��Ɏ��́A�����̒��S�����Ƃ��A�����̔��~����։~��E�\�E�~�Z���ے�������̂Ɛ\���܂����B�܂��_�͕i�ʕt���̋N�����{�̕����́A�{���̕�F�ɂ���Č�������A�{���̕�F�ɂ���Ĉ�ㅘe�������v���̖{���̕����ł���Ƃ��\���Ă��܂����B�����Ŕ��~���̕����ɏے������։~��E�\�E�~�Z���A�@�،o�{��̗���ʼn��߂���A�܂��������@�吹�l���u�J�ڏ��v�ɂ����āA
�@��E�����n�̕��E�ɋ�A���E�����n�̋�E�ɔ����āA�^�̏\�E��A�S�E��@�A��O�O��Ȃ�ׂ��B
�@�Ƌ���ꂽ���s��Ȃ�{���ʏ�̕��E�Ɛ\����܂��傤�B���E�Ƃ͕������̐��E�łȂ���E���������̂łȂ���Ȃ�܂���B�Ⴕ�A�������̕��E�ł���Ȃ�A����͋�E�ɑ��������̂ł����āA��̐��E�Ƃ͂����Ȃ��̂ł��B�@��씎�m�͕����̎p�ɕ��ɂ̉~���Ȃ鐸�_�����o���A���̉~������������Ă��܂����A�~���Ƃ́A�܂��������s��łȂ���Ȃ�܂���B�����ċ��s����Ƃ��đ��`����Ȃ�Ε��������̎��ǂ̕�꜂ɋv���̖{�����߉ނ��܂̕��������u���A����𒆐S�Ƃ��Ė��n�̋�E���\�����s�E���Ӎs�E��s�E�����s�Ƃ����{���̎l���F���A������k�ɔz�u����邱�ƂɂȂ�܂��傤�B
�@�O�ɂ����́A�{���̕�F�̂��Ƃ��v���̖{�����߉ނ��܂ْ̑��̕��q�E�ّ��̕��q�Əq�ׂ����Ƃ�����܂������A�{���ْ��̋v���̕��q�i�ّ��s�ł̕��q�j�Ƃ��Ė{�����߉ނ��܂̖{����������킵�A�̋�̖��n�̋�E������킷���̂ł���Ȃ�A�{���̎l���F�����ǂɑ������邱�Ƃ́A�ނ��듖�R�Ɛ\����܂��傤�B
�@�J���J�b�^�����قɒ�Ă���I���I���̍�Ƃ����X���b�g�k�J�o�y�̏������A���̌����ȍH�|�i�̕��������ʂɂ͓ˋN�����O�w�̕�꜂�����A��꜂ɂ͕��ɗ���r�A��꜂ɂ͍����̕��ɂ̍��E�Ɉ�l���̘e�d������A��꜂ɂ͍����̕��ɂ̍��E�ɓ�l���̘e�d������o����Ă��܂��B�Ⴕ���̏��������k�C���h�̎嗬�ł���������ؗL���̏��拳�k�ɂ���đ���ꂽ���̂ł���Ȃ�A�����炭���̘e�d�͎ɗ����E�ژA�E�ޗt�E����Ƃ���������q������킵�����̂ł���܂��傤�B
�@����͈��ɂ����܂��A�����̕�꜂ɘe�d�����u�����́A�����ď��Ȃ�����܂���B����ɂ���Ă��_�͕i�t���̕����ɁA�{���̎l���F��e�d�Ƃ��Ċ�������Ƃ������Ƃ́A�@�،o���������̖@�،o�k�̊Ԃɓ��R�l�����Ă������ƂƐ��ʂ����̂ł��B�ܘ_�A���̏ꍇ�̎l���F�́A���s��Ȃ閳�n�̋�E���\����{�����߉ނ��܂ّ̑��v���̕��q�Ƃ����Ӌ`�������̂ł����A�܂������ɂ��̎l���F�́A��g�ҍ��̕��g�Ƃ��Ė{���ْ���薖�@�O�k���E�ɏo�����A�@�،o���z����g���������Ă��܂��B
�@���̏ꍇ�̎l���F�́A�����̊O���ɂ����āA�����ɑ��Ȃ��畧�����쎝����p�ɑ��`����܂��傤�B�u�b�_�K���̑哃�̊�d�̎l���ɏ���������A������꜂ɂ͂��ꂼ�ꗧ���̕�F������������Ă��܂����B�܂��Z�C�����̕����̎l���ɂ��l��̏��������Ă��Ă��܂����B���̏����ɍՂ��Ă���͕̂��ɂ���F���m���߂邱�Ƃ͏o���܂���ł������A���̓��̔z�u��^�����̂��P�H�̕��ɗ����Ȃ̂ł��B
�@���̂悤�Ɏ哃�𒆐S�Ƃ��������l��̎l���z�u�����\���A���̎l��̏����������Ӗ�������̂ł��邩���m�ɒm��܂��A�@�،o�{��̗��ꂩ��A���̎l��̏�����{���l���F�̓��Ƃ��ĊJ�����邱�Ƃ��o���܂��傤�B
�@�吹�l���g���R���ŊJ�Ⴓ�ꂽ���R�@�،o���̔镧�ꑸ�l�m�{���`�̂̍\���A�{�����߉ނ��܂𒆐S�Ƃ��Ďl���F��������k�ɔz�u����Ă���\���́A�����ɖ�Ȃ�A�l���F���̊O�ǂɔz����ꍇ�ɂ��A�����l���̎l��̏����ɔz����ꍇ�ɂ��ʂ�����̂ł���܂��傤�B���̂������D�Ƃ��đI�Ԃׂ����͔��肩�˂܂����A������ɂ��Ă��_�͕i�ʕt���̕����\���́A���������ꑸ�l�m�`�̂̕����ł������ł��낤�Ǝv����̂ł��B
�@�Ⴕ�A�����ł���Ȃ�Α吹�l�̈ꑸ�l�m�{���̌����́A�����ɕ����̌`�͂Ȃ��ɂ��Ă��A�܂������_�͕i�ʕt���̋N�����{�Ƃ����{�������̕����ɂ����̂ł���A���Ƃ��l���F�𓌐���k�ɔz�u�����Ɠ��̍\�����A�ޗǓ��厛���d�@���̊Ӑ^�a�������ɂ�����O�w�y�d��A�߉ޑ���������鑽�𒆐S�Ɏ����V�E�����V�E�L�ړV�E������V��������k�ɔz�u����Ă���\���Ƀq���g�����̂ł������Ƃ��Ă��A�_�͕i�N�����{�̕����\�����ꑸ�l�m�`�̂̂��̂Ƃ��ē��@���ꂽ�吹�l���v��ɂ͋��Q����ق��͂���܂���B
�@�������ɑ吹�l�̈ꑸ�l�m�{���`�̂ɂ͕���������܂���B���́A�������Ȃ��̂��B�_�͕i�̖{���������N�����{�Ƃ��č�������Ă���Ȃ�A���̈ꑸ�l�m�̕\���������ɂ���ĂȂ���Ȃ���Ȃ�Ȃ��͂��ł��B�R��ɁA�����ĕ����`�̂���������Ă��邱�Ƃɂ́A���{�̕������ޗLjȗ��A���̓��ɍՂ镧�ɗ������͐M�̑ΏۂƂ݁A���̐M�������ֈڂ��A�����͎��@�����̗֚�̔���Y���錚�z���Ɖ����ė����Ƃ������ƁA�@�،o�̕����͓����̑��ł���Ȃ���A���͓����̋V���ɂ���Đ��g�̂��߉ނ��܂̋v���J�������A�������ւ̉����ƂȂ�A���ݕi�ɂ����ē�����E�A���čs���A���@�ɏo������ꑸ�l�m�̕����́A���͂⑽�ł͂Ȃ��Ƃ������ƁA�Ƃ������悤�ȗ��R���������܂��傤�B
�@�吹�l�̈ꑸ�l�m�{���`�̂́A�{�������u���镧���Ƃ������z���ɔ�d������̂łȂ��A�{�����̂��̂ł����B���{�̕����͎O�d�̓��ɂ���d�̓��ɂ���A����͕��ɂ��̂��̂ł��Ȃ��A���ɂ̉~���Ȑ��_���ے��������̂ł��Ȃ��A�ł����I�Ȍ��́E���͂��֎��������̂ɂ����܂���ł����B�����������z����吹�l���ꝱ���ꂽ�͓̂��R�ł���܂��傤�B
�@���́A�ނ���吹�l���ꑸ�l�m�{���̑��`��A�����ɕ���������킳��Ȃ��������ƂɊ��ӂ�����̂ł��B���̂Ȃ�A����ɂ���Ē����ɖ@�،o���������̐_�͕i�̋N�����{�Ƃ����A�ꑸ�l�m�����̌��_�ɋA��A���������ɕ\�����邱�Ƃ��o���邩��ł��B�Ƃ����ĕ��������̂Ȃ��ꑸ�l�m�`�̂ƁA���������ɂ��ꑸ�l�m�`�̂Ƃ��r���ėD���_���悤�Ƃ�����̂ł͂���܂���B���Ƃ�藼�҂ɉ��l�̗D����͂��͂���܂���B
�@�R���A�Ⴕ�吹�l���C���h��Z�C�����̌��n����������ꂽ�Ȃ�A�K������������Ɉꑸ�l�m���������u����{���`�̂��J�����ꂽ���Ƃł��낤�A�Ǝv����̂ł��B
�@�����Ŏ��̍l����_�͕i�N�����{�̕����\���̊T�v�����_�Ƃ��ďq�ׂ�Ȃ�A���悻���̒ʂ�ł��B
��A�@�،o�������I���ꐢ�I����I�ɂ��������k�C���h�ł������Ƃ��납��A���̕����l�����A���̒n�ɂ����邻�̍��̂��̂����^�Ƃ���͓̂��R�ł���܂��傤�B
��A���̍��̕����́A�������𒆐S�Ƃ��āA���ւ���d���d�w���A�d�w��d�̊e�w�ɂ͏��������u����A�ʼn��̊�d�ɂ͕��`�}�������[�t�Ƃ��Ē�������Ă��܂��B�����ʼn��Ɋ�d���l�w�Ƃ���Ȃ�A�ォ����w��꜂ɑ����̉ߋ��������u���A���w��꜂ɑ����̕��g�̏��������u���A��O�w�̎l���l��꜂ɂ��ꂼ��{���̎l���F�������A���ʂɂ͑��w�����O�w����ʂ��c����꜂ɋv���̖{�����߉ނ��܂̕������A���ʕi�̐����ɂ���Đ��@��ɂ���đ������u���A���̌�w�ɂ���ڂ������A�l���F��꜂̊ԂɁA���`�}�̃����[�t������̂ł��B
�@�ܘ_�A���̌`���͎l���F��{���ّ��̕��q�Ƃ��Ă���킵���ꍇ�ł����A�l���F�̖��@�O�͂̈ӂɏd�_�������Ȃ�A�l���F�͕����̊O�̓�����k�̏����Ɉ��u����A�����̐��ʂ͎哃�ɑ���悤�ɑ��`����܂��傤�B�A���l���F�������ł��邱�Ƃ͂����܂ł�����܂���B
�O�A���̎l���F�̑��`�ɂ��ẮA�u�ϐS�{�����v�ɁA
�@���̎l��F�́A�ܕ��������鎞�́A�����ƂȂ��ċ������r�ӂ��A�ێ���s���鎞�́A�m�ƂȂ��Đ��@���O�����B
�@�Ǝ�����Ă��邱�Ƃɂ��A�o�Ƃƍ݉ƁA�ێ�Ɛܕ����l���F�ɂ��ꂼ��z�����邱�Ƃ��l������Ƃ���ł��B
�@�ȏ�́A�����܂ł��u�N�����{�v�Ƃ��������������ӎ������ꍇ�̈ꑸ�l�m�����{���\���ł����āA�����͕��������ɂƂ������n�����̓`�����p���������̂ł���A�ꑸ�l�m�̕����́A�\���܂ł��Ȃ��@�،o�{��̖{��������킵�A�����ƈꑸ�l�m�����ɂ���ċ��s��̋v���̕��E������킷���̂Ƃ������Ƃ��o���܂��傤�B
�@���̕������ǂ̕�꜂Ɉ��u���鑽���̉ߋ����E���g���̏����́A���g�̂��߉ނ��܂��v���̖{���ł���Ƃ������Ƃ����o�I�ɍĉ�������̂ł���A���`�����[�t���܂��v���̖{���Ȃ���̂��P�Ɍ`����̕��łȂ��A���g�̂��߉ނ��܂��̂��̂ł��邱�Ƃ�i������̂ł��B
�@�A���A��꜏����̒��A���̒��S�͈ꑸ�l�m���ɂ�����̂ł����āA���ꂪ�����Ȃ�A�ߋ������E���g�����A���тɕ��`�����[�t�́A����ɂ��������Ƃ͂���܂��A�Ȃ��Ă������ĕs���Ƃ�������̂ł͂���܂���B
�@�Ȃ��A�ߋ����ƕ��g���Ƃ�Δ䂷��Ȃ�A���߉ޗl���g�A���ɉߋ����̌n�����������̂ł���A�{���̕�F���ߋ����̋����ɂ����̂ł������̂ł�����A�ߋ����̕������g������d��������A�]���Ă��̑��`�ɂ����Ă��ߋ����̑��̕������g���̑������傫������킳���ׂ��ł���܂��傤�B�Ⴕ�A�߉ޑ���̓�����@�؋V���̓��F�Ƃ��ĕ����Ɉ��u�������Ƃ����Ȃ�A�ߋ����̑w�̒��S���Ɉ��u���邱�Ƃ��l�����܂��傤�B
�@���ɍl�����邱�Ƃ́A���������ꑸ�l�m�����Ƒ�}���_���{��̉��d�Ƃ̊W�ł��B���˂Ď��́A���@�吹�l�}���̑�}���_���͖{����d��}���������̂ł���Əq�ׂė��܂����B�R���A�����̑��_�Ƃ����}���_���̍\���́A���߉ނ��܌�ݐ������A�@�،o�{�唪�i�̒��ł��_�͕i�ʕt���ɂ��킹�đ��ݕi�̑��t���̐��������_�Ƃ������̂ł���A���Ō㖖�@�ݔN�̖{��̉��d�́A�ݐ��̑�}���_���@�ɂ����Ȃ�����A���̒��_�̓����̑��́A�ꑸ�l�m�̋v���̕����ƂȂ�̂ł��B�����A���@�ɂ�����{��̉��d�\���́A�ꑸ�l�m�̕����_�Ƃ��A�d�w������d�ɏ\�E�։~�������}���_�����ł���Ɛ\���܂��傤�B
�@��ɂ��ӂ�܂����悤�ɒ����C���h�̕������A���Ƃ��T���`�[�̂悤�ȕ����l���́A���k�C���h�̃K���_�[���̒n���ł́A���ւƊ�d���d�w���ė��܂����B���̗l���������֓n��A�X�ɓ��{�ɓ`��钆�ɁA��d�͎O�d�E�d�̉��������Ȃ��A���S���̕����͏�w�����̒���ŁA���ւ��������长�̂悤�ɏ����Ȃ��̂ƂȂ��Ă��܂��܂����B�Ƃ��낪�K���_�[���l���̊�d�͓���֓`���ƁA�k����d�������ɍ������т��̂ɑ��āA���ɍL���O����A�ɒ[�ȗ�̓W�����̃{���u�h�[���̕����̔@���L��Ȗʐς������̂ƂȂ����̂ł��B
�@�ޗǓ��厛���d�@�̎O�w�y�d�̑��A�t���R�̘[�̓����A�����̐Α����d�A���쎛�̓y���͊F�A����n�̕�����d�̌n���ł���A�吹�l�̑�}���_�����d���܂����̌n���ɓ�����̂Ƃ����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@���@�剺�̐l�X�́A�O���@�̖{��̉��d�Ƃ����A�������ʂȌ������̂悤�Ɏv���Ă���悤�ł����A���͏d�w��d�̉��ւЂ낪��������n�����Ȃ̂ł��B�ܘ_�A�����ŏ�d��ɂ͈ꑸ�l�m�̖{�����������u�����̂ł����A���̕����̉��̊��w���̊K�d�́A�{���K���_�[�������̏d�w��d�̕ό`�ɂ����܂���B�吹�l�͍ŏ�d�Ɉꑸ�l�m�{�������u���ċ��s��Ȃ��Z�̕��E������킵�A����ȉ��̊��w���̊K�d��瑉��̕�F�E�ȉ���E�̐��E������킻���Ƃ��đ�}���_����}�����ꂽ�̂ł��B�A�����̑S�̂��{�����ʉʏ�̕����y�ł��邱�Ƃ́A��}���_�������̑�ڂ��\�E��ʊт��A�\���ɋP���n���Ă��鏑�����ɂ���Ă����炩�ł���܂��傤�B
�@�ʔ������Ƃ̓T���`�[�̕����̎��͓�����k�Ɏl���̐Ζ傪���Ă��A�Ζ�ƐΖ�Ƃ��̗��|�ɂ���Ăނ���ĕ����������ތ`�����Ă���Ƃ������Ƃł��B���̐Ζ�͓��{�̒����̂悤�Ȍ`�����A�����Ȓ������قǂ�����Ă��邱�ƂŗL���ł����A���͂��̐Ζ傪���́A������k�Ɏl�������Ă��Ă��邩�Ƃ������Ƃł��B
�@����i������\����j���̕�Z�c�쒆�w�̓������ł��錚�z�ƌF�J�����A��심�̕��ɗ����v�̈˗��������A�����������n���������邽�ߗ�������܂����B���w����͈ꏏ�ɏ_���̌m�ÂȂǂ��ĉ����������ł������A�Ȃɂ��둲�ƈȗ��O�\���N�Ԃ�̑Ζʂł����B�ނ͌Ñ㌚�z���猤�����͂��߁A�����̌��z���������Ȃ��猻�݂̎��@���z�ɖ{���͂Ȃ��Ɣߕ����Ă��܂������A���������b�̒��A���z�͑f�ނ̏c�Ɖ��Ƃ̑g���킹����n�܂�B���̍ŏ��̂��̂��h�������ł���A�h�����������E���炠�킳�������̂������ł���Əq�ׂĂ��܂����B�h�������Ƃ͌Ñ�̋M�l�̂���Ƃ������Ă��܂����A�T���`�[�̐Ζ���h�������̔��B�������̂Ɛ\����܂��傤�B
�@�������ɕ��ɗ����́A���߉ނ��܂̂���ł�����̂ł�����A�h�������Ƃ��Ă̐Ζ傪�A�T���`�[�̕����ɕ������Ă��Ă��s�v�c�ł͂���܂���B�R�����̐Ζ傪���ꂼ�����k�Ɍ��Ă��Ă���͔̂O�����肷���Ă��܂��B�ł͉��̂��A�Ƃ����ƁA�����Ɏv���N�������̂��A���߉ނ��܌�ݐ������A�C���h�̗}�K�_���̎�s���ɏ�ɂ��Ă��A�R�[�T�����̎�s�ɉq��ɂ��Ă�������k�ɖ傪����A���߉ނ��܂̑��V���s�����N�V�i�K���Ƃ����Ƒ��̒��ɂ������ڗ��̓�����k�ɖ傪�������Ƃ������Ƃł��B�����炭���̓����A�����ĕ��Ō�̎���ɂ����ẮA�����̑�s�s�ł����Ă��A�����ڗ��ł����Ă��A���̎��͓�����k�ɂ��ꂼ��傪�������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���������傪�����Ɍ��Ă��A��Ɩ�Ƃ��Ȃ����|�ɂ���ĕ������������Ă���Ƃ������Ƃ́A���͂╧�����P�Ȃ邨��łȂ��A���Ō�Ƃ����ǂ��A�Ȃ��������Ă�����s�ł̂��߉ނ��܂̏�Z�̕���������킻���Ƃ������̂Ɛ\����܂��傤�B�Ⴕ�A�����ł���Ȃ�A���̖���������ĕ������Eㅗ�q����Q�q�҂́A�P�Ȃ邨��Q��ł͂Ȃ��A�ܘ_�A���҂̍��ɓ��邱�Ƃł��Ȃ��A�䍟�y�����̏�Z�̕����y�̒��ɓ����āA�s�ł̂��߉ނ��܂��^�Q�E���h��q���邱�ƂɂȂ�܂��傤�B
�@�����O���̑哂����L�ɂ��A�K���_�[���̃J�j�V�J���̌��������哃�̗Y�傳���L�^����Ă���A�������Ղ������Ȃ��j��Ă͂��܂����A���̕����}���݂�A���d�̎l���ɂ��ꂼ�ꏬ���̂��Ƃ�����A���d�̓�����k�ɂ����ꂼ������̖�̕������ˋN���Ă��܂��B���̓ˋN�������������A�����y�ւ̓������������̂ł������̂ł͂Ȃ��ł��傤���B
�@���厛�̉��d�@�̎O�w�̓y�d�ɂ��Ă��A�����̎O�w�̐Βd�ɂ��Ă��A���̕��d�l�ʊe�w�ɁA���ꂼ�ꏸ�~�̊K�i�����������Ă��܂����A���̎l���̊K�i���A���͎l���̖�����邱�Ƃ�����킵�����c�ł���܂��傤�B
�@���̂悤�ɍl���ė���Ȃ�A�吹�l����}���_���ɐ}�����ꂽ�{��̉��d�ɂ�������k�̎l���ɕ����̖傪����A��̓��͋v���̖{�����߉ނ��܂𒆐S�Ƃ������s��̏�Z�̕����y������킷���̂ł������A�Ƃ������Ƃ��o����̂ł��B���ӂ��Ă����˂Ȃ�Ȃ����Ƃ́A���d�ŏ�d�̕����������������ł͂Ȃ��A���d�̑w����d�ł������Ƃ��Ă��A����͕����̊�d�ł���A��d�̔��B�������̂ł���Ƃ������Ƃł��B
�@�A���A�����̊�d�ł�����d��ɏ���҂́A�����̓��ɓ���̂ł͂Ȃ��A�����y�ɓ�����̂ł����āA�P�H�̕�����A�k��B��i�̃r���}�̃p�S�_�A�ᏼ�̍����R�̕����̔@���A���̓��ɓ���悤�ɐݔ�����Ă���̂́A�������ό��̕ւɋ����Ă�����̂ł����āA���������������Ɛr���������̂ł��B�P�H�̓��ɂ��Ă��A�ᏼ�̓��ɂ��Ă��A���̓��ɓy���œ�����悤�ɂȂ��Ă���A�P�H�̔@���͓����ɓ��{�����e�@�̑c����Ă��܂��B
�@�����̔@���́A���g��y���łӂ݂ɂ�����̂Ɠ������Ƃł���A���g����ɂ��Ă���̂ƕς�肠��܂���B�����������Ȃ��畧���������A���𗘗p����ɓ��������̂ł��B�����̓��ɐl�Ԃ������Ă͂Ȃ�܂���B�܂��l�Ԃ�����悤�Ɍ������Ă͂Ȃ�܂���B�����͕��g���̂��̂ł��邩��ł��B���@�@�̋��w�҂̒��ɁA�̓��ɓ����đ��g��������Ɛ����l������悤�ł����A����͐l�Ԗ}�v���{�����߉ނ��܂Ɠ������Ȃ��Ă���̂��Ƃł����āA����܂ł͖{���̕�F����ʈꕧ�y�̋ł܂ōs���ׂ��ł���܂��傤�B�݂�����{���̕�F�����s�����A���̒��ő��g�����̑������l���A���̊ϔO���O�ɐ����āA�̓��ɓ����đ��g�������܂��傤�Ƃ����߂邱�Ƃ͊댯����܂�Ȃ�掖@�̏��ƂƂ����Ȃ���Ȃ�܂���B
�@���́A�_�͕i�ʕt���̋N�����{�̕��������A���@�O�k���E�ɁA�{���̕�F�ɂ���Č��������Í����\�L�Ȃ�ꑸ�l�m�̖{�����ł���A�{���Ɩ{���Ƒ�ڂ̎O�����邱�̕����́A���̂܂܋v����Z�̕����y������킵�A������d���l���ɏd�w�g�傳�ꂽ���̂��A���̂܂ܖ{��̉��d�ł����āA�吹�l�}���̑�}���_���́A���߉ނ��܌�ݐ������A�@�،o�t���̎��_�ɂ����镧���y���d������킵�����̂ł���A�Əq�ׂė��܂����B
�@���̖{��̑�}���_�����d�́A�吹�l�Z�\��N�̐��U�ɂ����Ă����������A�吹�l�Ō㎵�S�N�̊Ԃɂ����������A���͂���@�剺�̐l�X�͉��d�̍\�����m�炸�A�����������@���m��Ȃ���ԂƂȂ��Ă��܂��Ă��܂��B
�@�n���w��͕x�m�̑�Ύ��ɉ��S���~���̑���𓊂��ĉ��d�{���Ə̂����}���_����������吳�������z���܂����B������͓�������Ɉꑸ�l�m�{�����Ղ�q���Y�[���@�̂悤�ȑ�{�����������܂����B�R����}���_���ɂ��Ă��A����͗��̓I���d�̐}�Ăɂ����Ȃ��̂ł��B�܂�������̈ꑸ�l�m���ɂ��Ă��A���߉ނ��܂͗����ł���A�{���̎l���F�͂��߉ނ��܂̌��w�̒��ɔz������Ă���L�l�ł��B
�@�����������`������悤�ł͔@���ɋ���Ȃ��̂��Ă��A�{���̎��`�����d�̎��`���m��Ȃ��ӎ҂̓Ƃ�悪��ȗV�тɂ����܂���B�n���w��̉�r�c��쎁�ɂ��Ă��A������̉�����h���ɂ��Ă��A�N�����{�̕����ɖڂ��J���Ė{���E��ځE���d�̎O���@���l�������ׂ��ł���܂��傤�B���̂��Ƃ͓��@�@�ɂ����Ă������Ȃ���Ȃ�Ȃ����Ƃł��B���@�@���{�R�g���R�v�������ǂ͎��S�������L�O���Č������悤�Ƃ��Ă����{���̖{�������݂̍���A��{���O�̒r�̒��̑��ւ݂̍������Ō�����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�A���̒��Ɍ������Ȃ����ׂ��ł��B
�@������Ɖi��H�q���͂��̒��u��t���E�����v�i��O��Łj�ɁA���厛������˂Ȃ�Ȃ������Ӑ^�a���ɂ��Ď��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B
|
�@���厛�𗣂�邱�Ƃ́A�Ƃ���Ȃ��������d�𗣂�邱�Ƃ��B�ނɂ���Ă͂��߂Ēz���������d���A�ގ��g������Ă䂭�\����͂ǂ��������ƂȂ̂��B���̎��A�Ӑ^���ǂ��v�������͂킩��Ȃ��B���A�B��A���̗ՏI�̐܁A
�u�䂪���߂ɉ��d�@�ɂ����ĕʂɉe�������Ă�v
�@�Ƃ��������t���c����Ă���B���Ă݂�ƔނɂƂ��āA��͂蓌�厛���d�����A���{�n���̈Ӗ���q�������̂ł͂Ȃ��������B���Ȃ݂ɁA�ނ̂��̈⌾�́A���Ɏ�������Ȃ������B��������ۂ������̂͒N�Ȃ̂��B |
|
�@�Ӑ^�a���̑J���́A�V�����N�܌��Z���A�������\�Z�˂ł����B�a���͐��Ɍ������Č����卿�����܂܍��S���ꂽ�Ƃ����A����O�������Ă������͉������A䶔��̎��͍��C���R�ɖ����������Ƃ����Ă��܂����A���̔N�̏t�A��q�̔E����̒��ōu���̓�������܂��̂����A�t�̘a���̎��̑O���Ɗ����āA�����ɘa���̍�������ɂ��������Ƃ����Ă��܂��B
�@�i�䎁���`����a���̈⌾�Ƃ������̂́A�@���Ȃ鎑���ɂ����̂ł��邩����܂��A�Ⴕ���̈⌾�������ł���Ƃ���Ȃ�A���厛���d�@�̂��Ɍ��Ă�悤�Ɉ⌾���ꂽ�e���Ƃ́A�����ɂ���č쐬�����a�����g�̑������u�����e�����������̂ł��������Ƃł��傤�B�Ⴕ�A�����ł���Ƃ���Ȃ�A�Ӑ^�a���͎����Ă����厛���d������낤�Ƃ��ꂽ�Ƃ������Ƃ��o���܂��傤�B
�@���̉��d�́A�a�����\��N�̊ԁA�Z�x�̓n�C�����݂ď��߂Č����������U�B��̉��d�ł����B�����Ă��̎O�w�̓y�d�́A�C���h�̃i�[�����_�̓y�ƁA�����̓V��R�̓y�ƁA���{���̓y�i���厛�̓y�j�Ƃ�����Ēz�������̂ł���A��O�w�����ɓ����̑������u�����@�،o�{��̋V���ɂ����̂ł����B�a�������̏�M�́A���{�Ɏl������`����Ƌ��ɁA�V��@�؋��w��`���邱�Ƃɂ������̂ł��B���Ƃ��a���̈⌾���㐢�̓Y���ł������Ƃ��Ă��A�a���̍��͂��̉��d�ɂ������Ƃ����Ă������ĉߌ��ł͂���܂��܂��B
�@���́A���@�吹�l�̖{��̉��d���l����Ƃ��A�a�������̂��̉��d���������˂Ȃ�Ȃ��Ǝv���̂ł��B�}���̊ϐ������̉��d�ɂ��Ă���b�R�̑����d�ɂ��Ă��A����͓��Ƃ��Ă̍\���������̂łȂ��A���d�Ƃ������͉���Ƃ����ׂ����̂ɂ����܂���B���厛���d�����A�����ɑ��𗧂āA�O�w�y�d����d�Ƃ��A�l�����ꂼ��ɏ��~�K�i�����Ȃ��āA�Î������̌n�����p�����Ă���̂ł��B
�@�吹�l�͓ޗǗV�w����A���̉��d�����x�ƂȂ��A�������茩�߂��Ă����͂��ł��B�����Ă�������^�Ƃ��Ė{��̉��d�������\�z���A���̐}�Ă��}���_���Ƃ��Ă���킳�ꂽ�̂ł���܂��傤�B
�@�@�؋��w�́A���Y�O���E�V���t�E���闥�t�E�Ӑ^�a�����o�ē`����t�ɓ`���A�吹�l�ɂ���Đ^�����J���܂����B�{��̉��d�́A�N�����{�̕������K���_�[�������ƂȂ�A����n�����Ƃ��Ĕ��B���A���闥�t�E�Ӑ^�a�����o�đ吹�l�Ɏ���A�{���}���_���������d�ƂȂ��Ă��̎����͌�l�ɑ�����܂����B�����đ吹�l�Ō㎵�S�N�A�����ɂ��̎������݂Ă��܂���B���{�R���̐��E�I�n��Ɍ������Ă��閳�ʂ̕��ɗ����́A�{����d�����̑O���ł��萐���ł���܂��傤���B
�@���@�@�̊w���҂̊Ԃł́A���{�R���ɑ���Ό��������Ă��A����Ƃ��@�{�����w�ɂ��̂��A���������ɗ����̌������D�܂Ȃ��悤�ł��B�R���吹�l�}���̑�}���_���͓����̑������S�ƂȂ��Ă��܂��B���̑��͐_�͕i�ʕt���ɂ����Ă͈ꑸ�l�m�̕����Ƒ�����̂ł��邱�Ƃ́A����܂ŎƁX�q�ׂĂ����ʂ�ł����A�Ⴕ���̕�������{���d�̓��̔@������Ȃ�A��}���_���̋�E�`����ꍇ�A��d�Ɋ�d���d�˂���A�̐S�̕����́A�Ȃ���w�����̒���ɁA���ւ��������鏬���Ȃ��̂Ƃ��ė��߂��A���s��̗։~��\�E�~�Z�̐��_���ے�����̂Ɍ������Ɛr���������ʂ��܂˂��ł���܂��傤�B
�@�吹�l�}���̕����}���_�����A�����ɗ��߁A�ꖇ�̎��ɗ��߂Ă͂Ȃ�܂���B���̈�X�̕��E��F�E���V�E�e���𗧑̓I�ɑ������A�����𒆐S�Ƃ��Ĕz�u�����ꍇ�A�ǂ������\���ƂȂ邩���l���˂Ȃ�܂���B���̏ꍇ�A���~���̓��X���镚�����Ɉꑸ�l�m�ܑ̌���z���A������d�ɋ�E�̏����������A�ʼn��d�̎l���Ɏl�V���A�l����������A���̑S�̂��Ƃ���Ȃ���ꂪ���̂܂܉F���̒��S�Ƃ��ꂽ�{��R�i�X���[���R�j�ɑ���A������d��ㅓ����߂��邱�Ǝ��̂������y�V�s�̎������N�������߂邱�Ƃł��傤�B����ɂ����镧���y�̑��`�͑��ɂȂ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B�����̕��ɁA
�@�䂪���̓y�͈����ɂ��ēV�l��ɏ[������B���т������̓��t�A��X�̕�������đ������A����؉ʑ������ďO���̗V�y���鏊�Ȃ�B���V�A�V�ۂ������ď�ɂ������̋W�y���Ȃ��A�֑ɗ����ӂ炵�ĕ�����ё�O�ɎU���B
�@�Ƃ������y�Ƃ́A�܂��ɂ����̔@����}���_���������E�̏�ɏW�����̂ł���܂��傤�B��ɂ��q�ׂ܂����悤�ɕ���؉ʂƂ́A�؉ʓ����s��A���ʕs��A���s�������킷���̂ł��B�{��v���̕������܂����ʕs��E���s��ł���A�����͕��E��F�E�l�E�V����̂Ƃ��ĕ����y��\�����A�����̂��̕��͕�������̂Ƃ��ĕ����y��\�����Ă��܂����A���e�͑S������̂��̂ł���̂ł��B
�@�ȏ�u�䍟�y�����v�̏�y�̐l�X�̂��Ƃɂ��ďq�ׂ悤�Ƃ��āA��������������b�ɂȂ��Ă��܂��܂����B�{���ɂ��Ă͂��̂��炢�ɂ��āA����͕ʂ̍��֓��肽���Ǝv���܂��B